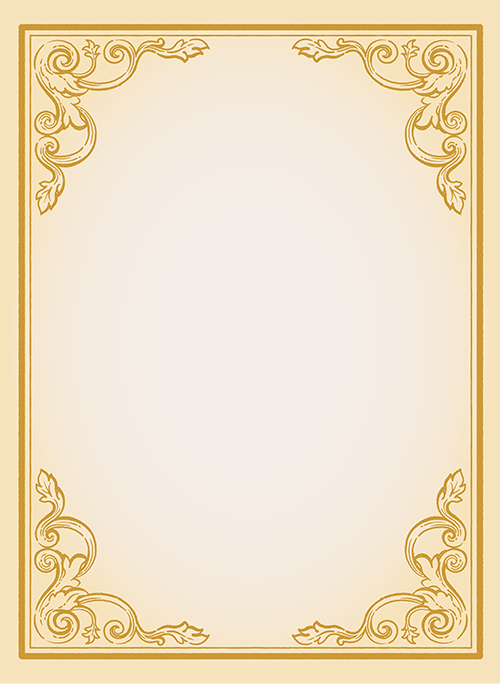鳴り響く電子音を止めようと、ベッドの中から細くて白い腕がにょきっと飛び出した。枕もとに置いてある目覚まし時計を何度叩いても音が止まない事に腹が立ち、おもむろに掴んだ目覚まし時計は、叶子の手によって遠くに放り投げられた。
「……。」
いつまでも鳴り続けるうざったい音の正体が自分の携帯電話であることに叶子はやっと気付いたのか、すぐさま携帯電話に手を伸ばした。そして、それが彼からの着信であった事に驚き、ぼんやりとしていた頭が一気に覚醒した。
「もしもし!」
朝の七時をさしている時計に目を向けながら、寝起きと悟られないように少し高めの声で電話に出た。
(こんな朝早くからどうしたんだろう?)
どんな用件だとしても、彼の声で目覚めるのはとても気分がいいものだった。
(もしもし? 僕だけど寝てる所ごめんね)
あっさりと寝起きを見破られてしまい、気恥ずかしくなる。女性であれば身支度や朝食を作るために既に起きているのが当たり前なのかも知れないが、叶子にとっては食い気や色気よりも眠気の方が優先だった。
それよりも、電話の向こうの彼は少し元気がない様に思える。朝早い所為なのかと話し始めた時は特に気にも留めていなかった。
◇◆◇
「だ、大丈夫!?」
肩を大きく上下させ、息も絶え絶えとなっている。そんな叶子の様子からして急いでここへ来たのだという事が顕著に表れ出ていた。
勢い良く開けた彼の部屋の扉。叶子がそこで見つけたのは、普段と何ら変わらぬ様子で仕事をしているジャックの姿だった。
突然の叶子の訪問に、ジャックは目を丸くしている。だが、すぐに状況が飲み込めたのか、みるみる口角が上がり始めた。
「カナ! 本当に来てくれたんだ」
掛けていた眼鏡を取って立ち上がると、そのままの勢いでキツク抱きしめられる。だが、叶子はすぐに彼の腕を掴んで二人の間に少しの距離を取った。
緩みきったジャックの表情に、叶子は首を傾げている。
「倒れたんじゃないの? 仕事して大丈夫なの?」
「うん、さっき医者が来てね。ただの貧血だって。今日一日ゆっくりしてれば良くなるだろうだってさ」
「……そっか、――良かった」
「──。」
ホッと胸を撫で下ろしている叶子の顔をジャックが覗き込んだ。、
「心配してくれたんだ?」
「……っ」
そう言いながら叶子の頬に手の甲を滑らせると、叶子の睫毛がピクリと震える。ゆっくり顔を上げると、大きな目を細めて彼が微笑んでいた。
顔の角度を変えて次第に近づいてくるの感じる。それにつられて閉じられようとしていた叶子の瞼は次の瞬間、大きく見開かれると共にジャックの腕の中から慌てて抜け出した。
「ル、ルール違反しちゃだめです!」
「……はーい」
数日前、彼の家に行った時に決めた二人のルール。それは、彼の家にいる間は彼女に手を触れてはいけないと言う内容のものだった。彼にとってはとても辛いルールのようだが、そのルールを作る事で叶子が家に来てくれるならと、ジャックは渋々その条件を呑んだ。
両手を顔の横に持っていき、『あなたにはこれ以上触れませんよ』とアピールしながらむくれた顔で部屋に備え付けてあるバーカウンターへと向かう。ケトルを探し当てるとお湯を沸かす準備を始めた。
「ごめんね、仕事休ませちゃって」
「いえ、いいんです。――どうせしばらく休みになったんで」
腑に落ちないと言った表情で、叶子はソファーにボスッと座った。
「しばらく休み?」
「――なんだか貴方と私の事が会社にバレちゃったみたいで」
「バレた? 恋人同士だっていうのが?」
何の臆面もなくそう言われてしまい、頬を赤らめながら叶子は小さく頷いた。
「バレたからってなんで会社が休みになるの?」
叶子の表情の変化に気付かないまま、ジャックは意味が判らないと言った面持ちでティーポットに紅茶の葉を入れようとした。
「──私、今回の仕事外されたんです」
「……はぁっ!?」
一瞬の間の後、ジャックの頭のてっぺんから聞こえて来たのかと思えるほどの驚きの声が部屋中に響いた。
「……。」
いつまでも鳴り続けるうざったい音の正体が自分の携帯電話であることに叶子はやっと気付いたのか、すぐさま携帯電話に手を伸ばした。そして、それが彼からの着信であった事に驚き、ぼんやりとしていた頭が一気に覚醒した。
「もしもし!」
朝の七時をさしている時計に目を向けながら、寝起きと悟られないように少し高めの声で電話に出た。
(こんな朝早くからどうしたんだろう?)
どんな用件だとしても、彼の声で目覚めるのはとても気分がいいものだった。
(もしもし? 僕だけど寝てる所ごめんね)
あっさりと寝起きを見破られてしまい、気恥ずかしくなる。女性であれば身支度や朝食を作るために既に起きているのが当たり前なのかも知れないが、叶子にとっては食い気や色気よりも眠気の方が優先だった。
それよりも、電話の向こうの彼は少し元気がない様に思える。朝早い所為なのかと話し始めた時は特に気にも留めていなかった。
◇◆◇
「だ、大丈夫!?」
肩を大きく上下させ、息も絶え絶えとなっている。そんな叶子の様子からして急いでここへ来たのだという事が顕著に表れ出ていた。
勢い良く開けた彼の部屋の扉。叶子がそこで見つけたのは、普段と何ら変わらぬ様子で仕事をしているジャックの姿だった。
突然の叶子の訪問に、ジャックは目を丸くしている。だが、すぐに状況が飲み込めたのか、みるみる口角が上がり始めた。
「カナ! 本当に来てくれたんだ」
掛けていた眼鏡を取って立ち上がると、そのままの勢いでキツク抱きしめられる。だが、叶子はすぐに彼の腕を掴んで二人の間に少しの距離を取った。
緩みきったジャックの表情に、叶子は首を傾げている。
「倒れたんじゃないの? 仕事して大丈夫なの?」
「うん、さっき医者が来てね。ただの貧血だって。今日一日ゆっくりしてれば良くなるだろうだってさ」
「……そっか、――良かった」
「──。」
ホッと胸を撫で下ろしている叶子の顔をジャックが覗き込んだ。、
「心配してくれたんだ?」
「……っ」
そう言いながら叶子の頬に手の甲を滑らせると、叶子の睫毛がピクリと震える。ゆっくり顔を上げると、大きな目を細めて彼が微笑んでいた。
顔の角度を変えて次第に近づいてくるの感じる。それにつられて閉じられようとしていた叶子の瞼は次の瞬間、大きく見開かれると共にジャックの腕の中から慌てて抜け出した。
「ル、ルール違反しちゃだめです!」
「……はーい」
数日前、彼の家に行った時に決めた二人のルール。それは、彼の家にいる間は彼女に手を触れてはいけないと言う内容のものだった。彼にとってはとても辛いルールのようだが、そのルールを作る事で叶子が家に来てくれるならと、ジャックは渋々その条件を呑んだ。
両手を顔の横に持っていき、『あなたにはこれ以上触れませんよ』とアピールしながらむくれた顔で部屋に備え付けてあるバーカウンターへと向かう。ケトルを探し当てるとお湯を沸かす準備を始めた。
「ごめんね、仕事休ませちゃって」
「いえ、いいんです。――どうせしばらく休みになったんで」
腑に落ちないと言った表情で、叶子はソファーにボスッと座った。
「しばらく休み?」
「――なんだか貴方と私の事が会社にバレちゃったみたいで」
「バレた? 恋人同士だっていうのが?」
何の臆面もなくそう言われてしまい、頬を赤らめながら叶子は小さく頷いた。
「バレたからってなんで会社が休みになるの?」
叶子の表情の変化に気付かないまま、ジャックは意味が判らないと言った面持ちでティーポットに紅茶の葉を入れようとした。
「──私、今回の仕事外されたんです」
「……はぁっ!?」
一瞬の間の後、ジャックの頭のてっぺんから聞こえて来たのかと思えるほどの驚きの声が部屋中に響いた。