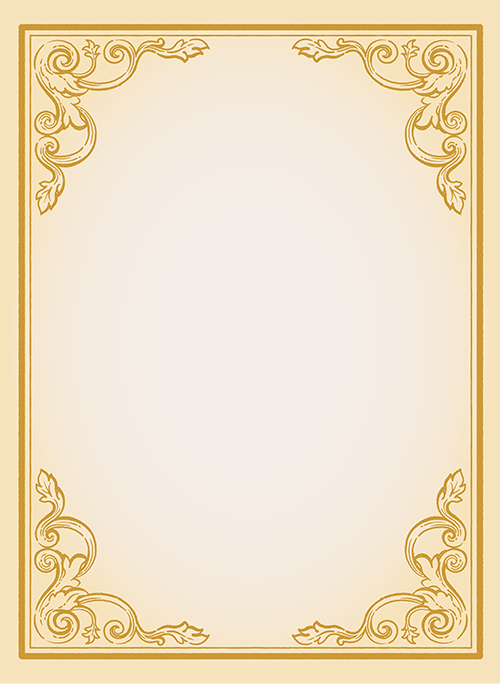いつもの様に彼が支払を済ませている間、叶子はお店の外で彼が出て来るのを待っていた。外はまだ寒く、あっという間に手が冷たくなる。その場しのぎではあるが、はぁっと息を吐き、何度も手を擦りあわせて自分の手を暖めてはこの後にある幸せの瞬間に備えていた。
「お待たせ」
そう言って彼は駆け寄ってくると、すぐに叶子の手を捕まえる。
二人が‟ビジネス”の関係から‟恋人”に切り替わるこの瞬間が、叶子はとても好きだった。
駐車場まで続く道を二人手を繋ぎながら歩いていると、彼が急に叶子の腰に両手を回し、向かい合う様にして立ち止まった。どうしたのかと叶子が目を丸くする。次の瞬間、瞼を伏せた彼が首を傾けながら距離を狭め、あっという間に口唇が塞がれた。
「……んっ…、ち、ちょっと」
両手で彼の胸をおさえて口唇を離すが、腰に回された彼の手はまだ叶子を解放しようとはしない。
「どうしたの?」
「『どうしたの?』じゃないですよ。こんな所で突然……」
「だってキス。したかったんでしょ?」
彼は悪戯っぽく微笑みながら首を傾げた。
『え? 違うの?』ととぼけているのが誰にでもわかりそうな、明らかに確信犯的な意地悪な微笑みだった。
「だ、だから、誰がそんな事言いました?」
「顔に書いてあったよ」
本当に書いているわけではないとわかってはいるが、つい両手で頬をこすった。
そんな叶子を見て彼がクスリと笑う。右手を彼女の頬に添えると親指を使い、そのぷっくりとした叶子の口唇をなぞった。
「僕の口唇が欲しくてたまらない、って顔。してたよ?」
「……。」
うっとりとした目で射抜かれる。男性とは思えぬその色香に心がざわつき始めた。
確かにあの時の自分は彼の口唇をじっと見つめていた。あの薄い口唇に触れたくて仕方が無いと心のどこかで思っていたのも、こうやって彼に見つめられてしまっては認めざるを得ない。
ただ、見つめられているだけだと言うのに、叶子の心臓は早鐘を打ち始め、そして思考はあっさりと停止した。
いくら辺りに人の気配が無いとは言え、いつ何時人が通るのかも判らない。過去の恋人とは野外でキスは愚か、手を繋ぐことすら恥ずかしくて嫌だったのに、ただ、彼に見つめられるだけで、僅かに残っていた羞恥心などいつの間にかどこかへ消え去っていた。
――そして、気付けば彼に吸い込まれるようにして自分から顔を寄せていった。
ふんわりと柔らかくて薄い唇が焦れるように触れる。一度顔を離して彼が微笑むと、再び目を細めて更に続きを強請る。
少しづつ侵入を始める彼の舌に躊躇して自身の舌を喉の奥に引っ込めると、すぐに顔の角度を変えて彼が更に深い所に入り込もうとする。
「…っ、…ん…」
突然、奥まで到達したその舌に、彼の胸元に置いていた手がピクリと跳ねた。呼吸がままならなくなると自然と眉間にも皺が刻まれ、意識せずとも悩まし気な声が漏れ出してしまう。
奥で縮こまっていた叶子の舌を彼の舌が追い詰め、あっさりと絡め取ると前へと引き出させる。最初は戸惑いがちに突き出していた舌が、彼のリードによって徐々に様になっていった。
ゆったりと繰り広げられる彼の焦れたキスが、あっという間に彼女を蕩けさせてしまう。ただ、口唇を合わせ、舌をもつれさせているだけなのに、身体のずっと奥の方が徐々に熱を持ち始める。
自身に起きている身体の変化によって、彼はキスが上手なのだと言う事を知った。
(や、ヤダ……。頭がボーっとしちゃう)
最初の方こそ恥ずかしくて嫌がっていた叶子だったが、いつの間にか彼のペースにのせられて受け入れていた。
長い戯れの後、名残惜しむように彼がやっとのことで口唇を解放する。口唇が離れたと言ってもすぐに身体を離すわけではなく、そのままぎゅっと叶子を抱き寄せた。
「あんまり煽らないでよ、理性が保てなくなる」
「…あ、煽ってなんか」
キツク巻きつけた腕を少し緩み、叶子の頭のてっぺんにチュッとキスを落とす。彼の頬が頭の上に添えられると、小さく溜息を吐いた。
「君が欲しいよ」
いつにも増して熱のこもった艶のある声でポツリと呟いた。
彼の家での一件があってから、二人の関係はキス止まり。先程の様な情熱的な口づけはあの時以来だったのもありその事が余程嬉しかったのか、押さえが利かずについ本音が漏れてしまった様だった。
「……っ」
急に現実の世界に引き戻されたかのように、火照っていた体から熱が失われていく。このまま身体を密着させていると彼がまた暴走するのでは、と、ジャックの腕からするりとすり抜け彼に向って背を向けた。
「――あ」
腕の中から叶子が抜け出た途端、ぬくもりが無くなる。手持ち無沙汰になった手をそのまま組むと、ジャックは小さく溜息を吐いた。
袖を捲り時間を確認する。まだ少し時間がある事を知ると、背中を向けている叶子に向かってジャックは話しかけた。
「ねぇ、今から僕ん家来ない? 帰って少し仕事もしたいし」
優しく問いかけても、叶子は背を向けたまま黙って首を振るだけだった。頑なに拒み続けるそんな叶子の様子に、大きく肩を上下すると更に深い溜息を吐いた。
「そうやって毎回毎回拒絶されると君が家に来てくれるって言った時、僕、変に期待しちゃいそうなんだけど?」
「や、あの、その」
慌てて彼の方を振り返り、しどろもどろになった彼女がとってつけたような言い訳を始める。
男女の関係になるのが今まで経験した事がないわけでは無いが、やはりあの時の怒りに満ち溢れた彼の顔がフラッシュバックして、中々前に進む事が出来ない。彼もそれを承知しているのか、あれからと言うもの、力づくで自分のモノにしようといった態度を見せた事が無かったから、叶子も安心していた。
いつかは乗り越えなければならないその壁を、叩き壊せるまでの気持ちの準備がまだ整っていなかった。
眉尻を下げ、明らかに返答に困っている叶子にふわっと温かいぬくもりが包み込む。先ほどとは違って優しく抱き締められて、自然と彼の胸の中で瞼を閉じた。
「いいよ、僕待つから」
彼の優しさがじんと心に伝わってくる。いつまでも逃げていてはいかない、自分も少し譲歩しなければと言う気持ちが自然と沸いて出た
「あの、何も――しないって約束できるなら、行ってもいいですけど」
「え?」
叶子のその言葉を聞くと、ガバッと抱き締めていた体を離し彼女の両肩に手を置いた。
「今、なんて?」
「こんな事、何度も言えません」
顔を背けて頬を赤らめている叶子に、聞き間違いではない事を確信した。みるみる笑顔になったジャックは叶子の気が変わらないうちにとでも思ったのか、おもむろに叶子の手を掬いあげ、善は急げと言わんばかりに歩き始めた。
「約束ですよ?」
念を押した彼女に彼は満面の笑みで返す。
「うん! 行こう」
そう言ってジャックは急に走り出した。足が縺れそうになりながらも、引っ張られるようについて行く。
「ちょっ、待って! 何も走らなくても」
「急いで! 時間がもったいないよ」
走りながら後ろを振り返る無邪気な彼の姿を見て、つい叶子の頬も緩んだ。
「お待たせ」
そう言って彼は駆け寄ってくると、すぐに叶子の手を捕まえる。
二人が‟ビジネス”の関係から‟恋人”に切り替わるこの瞬間が、叶子はとても好きだった。
駐車場まで続く道を二人手を繋ぎながら歩いていると、彼が急に叶子の腰に両手を回し、向かい合う様にして立ち止まった。どうしたのかと叶子が目を丸くする。次の瞬間、瞼を伏せた彼が首を傾けながら距離を狭め、あっという間に口唇が塞がれた。
「……んっ…、ち、ちょっと」
両手で彼の胸をおさえて口唇を離すが、腰に回された彼の手はまだ叶子を解放しようとはしない。
「どうしたの?」
「『どうしたの?』じゃないですよ。こんな所で突然……」
「だってキス。したかったんでしょ?」
彼は悪戯っぽく微笑みながら首を傾げた。
『え? 違うの?』ととぼけているのが誰にでもわかりそうな、明らかに確信犯的な意地悪な微笑みだった。
「だ、だから、誰がそんな事言いました?」
「顔に書いてあったよ」
本当に書いているわけではないとわかってはいるが、つい両手で頬をこすった。
そんな叶子を見て彼がクスリと笑う。右手を彼女の頬に添えると親指を使い、そのぷっくりとした叶子の口唇をなぞった。
「僕の口唇が欲しくてたまらない、って顔。してたよ?」
「……。」
うっとりとした目で射抜かれる。男性とは思えぬその色香に心がざわつき始めた。
確かにあの時の自分は彼の口唇をじっと見つめていた。あの薄い口唇に触れたくて仕方が無いと心のどこかで思っていたのも、こうやって彼に見つめられてしまっては認めざるを得ない。
ただ、見つめられているだけだと言うのに、叶子の心臓は早鐘を打ち始め、そして思考はあっさりと停止した。
いくら辺りに人の気配が無いとは言え、いつ何時人が通るのかも判らない。過去の恋人とは野外でキスは愚か、手を繋ぐことすら恥ずかしくて嫌だったのに、ただ、彼に見つめられるだけで、僅かに残っていた羞恥心などいつの間にかどこかへ消え去っていた。
――そして、気付けば彼に吸い込まれるようにして自分から顔を寄せていった。
ふんわりと柔らかくて薄い唇が焦れるように触れる。一度顔を離して彼が微笑むと、再び目を細めて更に続きを強請る。
少しづつ侵入を始める彼の舌に躊躇して自身の舌を喉の奥に引っ込めると、すぐに顔の角度を変えて彼が更に深い所に入り込もうとする。
「…っ、…ん…」
突然、奥まで到達したその舌に、彼の胸元に置いていた手がピクリと跳ねた。呼吸がままならなくなると自然と眉間にも皺が刻まれ、意識せずとも悩まし気な声が漏れ出してしまう。
奥で縮こまっていた叶子の舌を彼の舌が追い詰め、あっさりと絡め取ると前へと引き出させる。最初は戸惑いがちに突き出していた舌が、彼のリードによって徐々に様になっていった。
ゆったりと繰り広げられる彼の焦れたキスが、あっという間に彼女を蕩けさせてしまう。ただ、口唇を合わせ、舌をもつれさせているだけなのに、身体のずっと奥の方が徐々に熱を持ち始める。
自身に起きている身体の変化によって、彼はキスが上手なのだと言う事を知った。
(や、ヤダ……。頭がボーっとしちゃう)
最初の方こそ恥ずかしくて嫌がっていた叶子だったが、いつの間にか彼のペースにのせられて受け入れていた。
長い戯れの後、名残惜しむように彼がやっとのことで口唇を解放する。口唇が離れたと言ってもすぐに身体を離すわけではなく、そのままぎゅっと叶子を抱き寄せた。
「あんまり煽らないでよ、理性が保てなくなる」
「…あ、煽ってなんか」
キツク巻きつけた腕を少し緩み、叶子の頭のてっぺんにチュッとキスを落とす。彼の頬が頭の上に添えられると、小さく溜息を吐いた。
「君が欲しいよ」
いつにも増して熱のこもった艶のある声でポツリと呟いた。
彼の家での一件があってから、二人の関係はキス止まり。先程の様な情熱的な口づけはあの時以来だったのもありその事が余程嬉しかったのか、押さえが利かずについ本音が漏れてしまった様だった。
「……っ」
急に現実の世界に引き戻されたかのように、火照っていた体から熱が失われていく。このまま身体を密着させていると彼がまた暴走するのでは、と、ジャックの腕からするりとすり抜け彼に向って背を向けた。
「――あ」
腕の中から叶子が抜け出た途端、ぬくもりが無くなる。手持ち無沙汰になった手をそのまま組むと、ジャックは小さく溜息を吐いた。
袖を捲り時間を確認する。まだ少し時間がある事を知ると、背中を向けている叶子に向かってジャックは話しかけた。
「ねぇ、今から僕ん家来ない? 帰って少し仕事もしたいし」
優しく問いかけても、叶子は背を向けたまま黙って首を振るだけだった。頑なに拒み続けるそんな叶子の様子に、大きく肩を上下すると更に深い溜息を吐いた。
「そうやって毎回毎回拒絶されると君が家に来てくれるって言った時、僕、変に期待しちゃいそうなんだけど?」
「や、あの、その」
慌てて彼の方を振り返り、しどろもどろになった彼女がとってつけたような言い訳を始める。
男女の関係になるのが今まで経験した事がないわけでは無いが、やはりあの時の怒りに満ち溢れた彼の顔がフラッシュバックして、中々前に進む事が出来ない。彼もそれを承知しているのか、あれからと言うもの、力づくで自分のモノにしようといった態度を見せた事が無かったから、叶子も安心していた。
いつかは乗り越えなければならないその壁を、叩き壊せるまでの気持ちの準備がまだ整っていなかった。
眉尻を下げ、明らかに返答に困っている叶子にふわっと温かいぬくもりが包み込む。先ほどとは違って優しく抱き締められて、自然と彼の胸の中で瞼を閉じた。
「いいよ、僕待つから」
彼の優しさがじんと心に伝わってくる。いつまでも逃げていてはいかない、自分も少し譲歩しなければと言う気持ちが自然と沸いて出た
「あの、何も――しないって約束できるなら、行ってもいいですけど」
「え?」
叶子のその言葉を聞くと、ガバッと抱き締めていた体を離し彼女の両肩に手を置いた。
「今、なんて?」
「こんな事、何度も言えません」
顔を背けて頬を赤らめている叶子に、聞き間違いではない事を確信した。みるみる笑顔になったジャックは叶子の気が変わらないうちにとでも思ったのか、おもむろに叶子の手を掬いあげ、善は急げと言わんばかりに歩き始めた。
「約束ですよ?」
念を押した彼女に彼は満面の笑みで返す。
「うん! 行こう」
そう言ってジャックは急に走り出した。足が縺れそうになりながらも、引っ張られるようについて行く。
「ちょっ、待って! 何も走らなくても」
「急いで! 時間がもったいないよ」
走りながら後ろを振り返る無邪気な彼の姿を見て、つい叶子の頬も緩んだ。