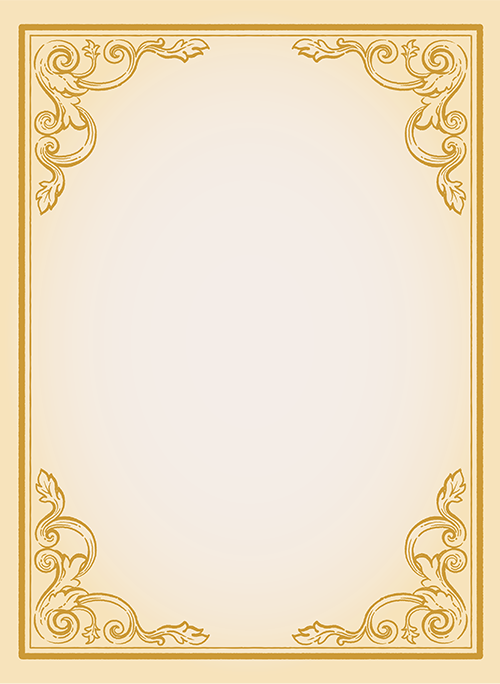少しゆるめに巻いた腕時計をくるりと回して約束の時刻が来た事を確認すると、荷物をまとめパソコンの電源を切った。
「ボス。打ち合わせ後、直帰しますね」
「はいよ! 頑張ってきてよ!」
一時はこの仕事を降りると強情をはっていた叶子だったが、この仕事は自分でないとダメなんだとジャックから説得され、仕事に私情を持ち込んでいるのは彼ではなく自分なのだという事に気付かされた。
傷つきたくない一心で彼を避けていたが、まだ心の中に彼が存在していた事に気付いた叶子は、本当の自分の気持ちに素直になった事でギクシャクしていた彼との関係もいい感じに落ち着いた。
何を言っても頑なに拒絶していたのが一変、水を得た魚の如く以前にも増してやる気に満ち溢れている叶子に対し、ボスは特に何も言わず上機嫌でいつも送り出してくれる。
そんなボスに対しニコリと微笑みを浮かべると、急いで扉から出て行った。
あれからジャックとは打ち合わせと称して度々会っていた。いつも忙しい彼はプライベートの時間を作るのはとても難しく、こういった形でなければ中々会えないのが叶子には少し不満ではあった。
叶子も仕事抜きで会いたい気持ちはあるものの、彼の立場を考えるとそれは簡単に叶うものではないと理解していた。
だが、彼に会いたい気持ちはどんどん膨らみを増す。職権乱用、はたまた公私混同だとか、後ろめたい気持ちが常に付きまとってはいたものの、仕事をしている事には違いないのだと割り切る様にしていた。
階下へ降りるエレベーターの中。前回の彼との打ち合わせを思い出していた。
彼はどうやら完璧主義なのか、叶子のデザインを気に入ったとは言え全てをそのまま受け入れるわけではなく、実に細やかな要望を伝えてくる。
ここはこの色を使って――と具体的に指示を出してくれるととても助かるのだが、『寒い冬の朝に温かいベッドから這い出そうとしている感じ』と、実にデザイナー泣かせな表現で指示を出すのだった。
どうにもこうにも理解が出来ない叶子は、もうちょっと具体的にと恥を忍んで尋ねてみた。が、返って来る返事はどれも似たり寄ったりで更に叶子の頭を悩ませる結果となった。
「そうだなぁ。冬の朝って凄く寒くてベッドから出るのって本当に嫌になるよね? でも、起きないと仕事にも行けないし学校にも行けない。新しい出会いが待っているかもしれないのに、ずっとベッドにいるんじゃあ何の変化もない。でも、それじゃあもったいないよね? だから思い切ってベッドから出ようとするんだけど、本当はまだ出たくないから指先から徐々に這い出て。で、最後の最後までベッドのぬくもりを感じていたいから足を出すのは一番最後なんだよ。――そんな感じ」
「はぁ……」
(さっぱりわかんないよ。……もしかして、これって試されてるのかな?)
余りの難題に困り果てた叶子は、自分でも気づかぬうちにグッと深く眉根を寄せていた。
そんな叶子の様子にジャックが気付くと、
「君なら大丈夫。きっといいのが描けるよ」
そう言って、柔らかく微笑んだ。
一体何を伝えたいのかといつも頭を悩ませられるのだけれども、彼によって徐々に自分が成長している様なそんな気がした。
「お待たせしました」
ビルから出て車道を見れば、いつもの様に彼が車の前で待っていてくれる。
叶子が近づくと、彼は満面の笑みで彼女を抱きしめた。
「ち、ちょっと、やめて下さい!」
長い腕の中でもがいている叶子の両肘を持つようにして距離を取ると、叶子の顔を覗き込みながら彼は不思議そうな顔で尋ねた。
「なんで? 抱きしめる位ならいつもしてるじゃない」
しれっと言ってのけたその科白に、みるみる叶子の顔が朱に染まっていった。
「ち、ちがっ、会社の前だし誰かに見られたら……」
辺りをキョロキョロと見回しながら彼に近づき小さな声でそう言うと、良く聞こえなかったのか、彼は耳を近づけてもう一度彼女の言葉を待った。
「もぅ、だから……」
彼の耳に手をかぶせ耳打ちするように話し出そうとした瞬間、不意をついた彼は叶子の頬にチュッと軽くキスを落とした。
突然の出来事に酷く驚いた叶子は、両手を彼の胸元に置くと勢いよく突き飛ばした。
「ひ、人の話聞いてます!?」
頬を手で押さえながら怒っている叶子の様子に、ジャックは身体を折るようにして笑い転げている。カンカンになっている彼女を尻目に、悪戯が成功した少年の様に喜んでいる様子だ。その笑いをこらえる事が出来ないまま、叶子を車の中へと誘導した。
車内に乗り込んだ後も両極端な態度の二人に、運転手のビルは呆れている。
「もう! 私は仕事で出てきてるんですよ? こんなトコ誰かに見られたりしたら、……ああ、そう考えただけで予想がつくのが恐ろしい」
「ククッ……気をつけないとね。――プッ」
まだキスをされた頬を押さえながらギロっと横目で睨みつけた。ジャックからすればそんな叶子が面白いのか、一旦収まりそうになったのがぶり返してしまっている様だった。
「で、でも……ハハッ、凄くスリリングだよね?」
「もぅ、バカッ!」
◇◆◇
いつもの様においしい食事を楽しみながら、仕事の話に没頭した。
目の前にいる彼は先ほどまでの少年の様な彼とは打って変わり、今となっては鋭い目つきをしたビジネスマンの顔になっている。
そんな彼の豹変ぶりに叶子はまだ慣れない様子だった。
メモを取りつつ彼の目を見ながら話を聞いているが、いつの間にやらどこか上の空になって自然とペンが止まる。彼が自分から視線を外した時を狙って、徐々に視線を落とすと視線は彼の口唇に止まった。
この人がさっき私を抱きしめて頬にキスした人。
この人が私を愛していると言ってくれる人。
でも、今、目の前にいる彼はまるで別人の様だった。
(なんか変な感じだな)
彼の口唇が動きを止めたのにも気付かず、そのまま彼の薄い口唇に見とれていた。
「……ねぇ? 聞いてる?」
口唇が動くと同時に出た彼の言葉で、慌てて視線を彼の目に戻した。
「あ、は、はい! 聞いてます」
疑いの眼差しを向けられてつい、叶子もしまったと言うような表情が顔に出る。
「さっき、ずっと僕の口元見てたよね?」
「っ! そ、そんなこ、っと、あるりません!!」
言い当てられてしまって動揺した叶子は、見事に噛んでしまった。途端、グッと眉根に皺を刻み彼の表情が険しくなる。叶子の背筋が凍る瞬間だった。
「――いいかい? 今日はビジネスで来てるんだ、ちゃんとその辺をわきまえて貰わないと困るよ」
「はい。……申し訳ありません」
「……、――プッ」
しゅんっとなり頭を項垂れた叶子を見て、彼は堪え切れず笑い出した。
「……え?」
「ほんっと、君って正直だよね……『あるりません!』だって、あははっ」
俯いていた顔を上げると、さっきまでの鋭い目つきが無くなり、いつもの彼のやさしい表情に変わっていた。当の叶子はキョトンとした顔で事の事態を把握出来ないで居る。
徐々に理解したのか、今度は叶子の眉間に皺が深く刻まれた。
「ひ、酷いっ!」
「あはは、ごめんごめん、でも――」
――『君って本当、可愛い女性(ひと)だね』
そんな風に言われてしまっては、叶子も本気で怒る事ができなかった。
「もうっ! ……?」
口先を尖らせむくれている叶子の頭に、彼の大きな掌が触れた。
「ちゃんと後であげるから。――ね?」
「っ!」
ポンポンと頭を優しく撫でながら意味深げにウィンクをすると、又、叶子の顔がみるみる赤くなり始めた。
「ボス。打ち合わせ後、直帰しますね」
「はいよ! 頑張ってきてよ!」
一時はこの仕事を降りると強情をはっていた叶子だったが、この仕事は自分でないとダメなんだとジャックから説得され、仕事に私情を持ち込んでいるのは彼ではなく自分なのだという事に気付かされた。
傷つきたくない一心で彼を避けていたが、まだ心の中に彼が存在していた事に気付いた叶子は、本当の自分の気持ちに素直になった事でギクシャクしていた彼との関係もいい感じに落ち着いた。
何を言っても頑なに拒絶していたのが一変、水を得た魚の如く以前にも増してやる気に満ち溢れている叶子に対し、ボスは特に何も言わず上機嫌でいつも送り出してくれる。
そんなボスに対しニコリと微笑みを浮かべると、急いで扉から出て行った。
あれからジャックとは打ち合わせと称して度々会っていた。いつも忙しい彼はプライベートの時間を作るのはとても難しく、こういった形でなければ中々会えないのが叶子には少し不満ではあった。
叶子も仕事抜きで会いたい気持ちはあるものの、彼の立場を考えるとそれは簡単に叶うものではないと理解していた。
だが、彼に会いたい気持ちはどんどん膨らみを増す。職権乱用、はたまた公私混同だとか、後ろめたい気持ちが常に付きまとってはいたものの、仕事をしている事には違いないのだと割り切る様にしていた。
階下へ降りるエレベーターの中。前回の彼との打ち合わせを思い出していた。
彼はどうやら完璧主義なのか、叶子のデザインを気に入ったとは言え全てをそのまま受け入れるわけではなく、実に細やかな要望を伝えてくる。
ここはこの色を使って――と具体的に指示を出してくれるととても助かるのだが、『寒い冬の朝に温かいベッドから這い出そうとしている感じ』と、実にデザイナー泣かせな表現で指示を出すのだった。
どうにもこうにも理解が出来ない叶子は、もうちょっと具体的にと恥を忍んで尋ねてみた。が、返って来る返事はどれも似たり寄ったりで更に叶子の頭を悩ませる結果となった。
「そうだなぁ。冬の朝って凄く寒くてベッドから出るのって本当に嫌になるよね? でも、起きないと仕事にも行けないし学校にも行けない。新しい出会いが待っているかもしれないのに、ずっとベッドにいるんじゃあ何の変化もない。でも、それじゃあもったいないよね? だから思い切ってベッドから出ようとするんだけど、本当はまだ出たくないから指先から徐々に這い出て。で、最後の最後までベッドのぬくもりを感じていたいから足を出すのは一番最後なんだよ。――そんな感じ」
「はぁ……」
(さっぱりわかんないよ。……もしかして、これって試されてるのかな?)
余りの難題に困り果てた叶子は、自分でも気づかぬうちにグッと深く眉根を寄せていた。
そんな叶子の様子にジャックが気付くと、
「君なら大丈夫。きっといいのが描けるよ」
そう言って、柔らかく微笑んだ。
一体何を伝えたいのかといつも頭を悩ませられるのだけれども、彼によって徐々に自分が成長している様なそんな気がした。
「お待たせしました」
ビルから出て車道を見れば、いつもの様に彼が車の前で待っていてくれる。
叶子が近づくと、彼は満面の笑みで彼女を抱きしめた。
「ち、ちょっと、やめて下さい!」
長い腕の中でもがいている叶子の両肘を持つようにして距離を取ると、叶子の顔を覗き込みながら彼は不思議そうな顔で尋ねた。
「なんで? 抱きしめる位ならいつもしてるじゃない」
しれっと言ってのけたその科白に、みるみる叶子の顔が朱に染まっていった。
「ち、ちがっ、会社の前だし誰かに見られたら……」
辺りをキョロキョロと見回しながら彼に近づき小さな声でそう言うと、良く聞こえなかったのか、彼は耳を近づけてもう一度彼女の言葉を待った。
「もぅ、だから……」
彼の耳に手をかぶせ耳打ちするように話し出そうとした瞬間、不意をついた彼は叶子の頬にチュッと軽くキスを落とした。
突然の出来事に酷く驚いた叶子は、両手を彼の胸元に置くと勢いよく突き飛ばした。
「ひ、人の話聞いてます!?」
頬を手で押さえながら怒っている叶子の様子に、ジャックは身体を折るようにして笑い転げている。カンカンになっている彼女を尻目に、悪戯が成功した少年の様に喜んでいる様子だ。その笑いをこらえる事が出来ないまま、叶子を車の中へと誘導した。
車内に乗り込んだ後も両極端な態度の二人に、運転手のビルは呆れている。
「もう! 私は仕事で出てきてるんですよ? こんなトコ誰かに見られたりしたら、……ああ、そう考えただけで予想がつくのが恐ろしい」
「ククッ……気をつけないとね。――プッ」
まだキスをされた頬を押さえながらギロっと横目で睨みつけた。ジャックからすればそんな叶子が面白いのか、一旦収まりそうになったのがぶり返してしまっている様だった。
「で、でも……ハハッ、凄くスリリングだよね?」
「もぅ、バカッ!」
◇◆◇
いつもの様においしい食事を楽しみながら、仕事の話に没頭した。
目の前にいる彼は先ほどまでの少年の様な彼とは打って変わり、今となっては鋭い目つきをしたビジネスマンの顔になっている。
そんな彼の豹変ぶりに叶子はまだ慣れない様子だった。
メモを取りつつ彼の目を見ながら話を聞いているが、いつの間にやらどこか上の空になって自然とペンが止まる。彼が自分から視線を外した時を狙って、徐々に視線を落とすと視線は彼の口唇に止まった。
この人がさっき私を抱きしめて頬にキスした人。
この人が私を愛していると言ってくれる人。
でも、今、目の前にいる彼はまるで別人の様だった。
(なんか変な感じだな)
彼の口唇が動きを止めたのにも気付かず、そのまま彼の薄い口唇に見とれていた。
「……ねぇ? 聞いてる?」
口唇が動くと同時に出た彼の言葉で、慌てて視線を彼の目に戻した。
「あ、は、はい! 聞いてます」
疑いの眼差しを向けられてつい、叶子もしまったと言うような表情が顔に出る。
「さっき、ずっと僕の口元見てたよね?」
「っ! そ、そんなこ、っと、あるりません!!」
言い当てられてしまって動揺した叶子は、見事に噛んでしまった。途端、グッと眉根に皺を刻み彼の表情が険しくなる。叶子の背筋が凍る瞬間だった。
「――いいかい? 今日はビジネスで来てるんだ、ちゃんとその辺をわきまえて貰わないと困るよ」
「はい。……申し訳ありません」
「……、――プッ」
しゅんっとなり頭を項垂れた叶子を見て、彼は堪え切れず笑い出した。
「……え?」
「ほんっと、君って正直だよね……『あるりません!』だって、あははっ」
俯いていた顔を上げると、さっきまでの鋭い目つきが無くなり、いつもの彼のやさしい表情に変わっていた。当の叶子はキョトンとした顔で事の事態を把握出来ないで居る。
徐々に理解したのか、今度は叶子の眉間に皺が深く刻まれた。
「ひ、酷いっ!」
「あはは、ごめんごめん、でも――」
――『君って本当、可愛い女性(ひと)だね』
そんな風に言われてしまっては、叶子も本気で怒る事ができなかった。
「もうっ! ……?」
口先を尖らせむくれている叶子の頭に、彼の大きな掌が触れた。
「ちゃんと後であげるから。――ね?」
「っ!」
ポンポンと頭を優しく撫でながら意味深げにウィンクをすると、又、叶子の顔がみるみる赤くなり始めた。