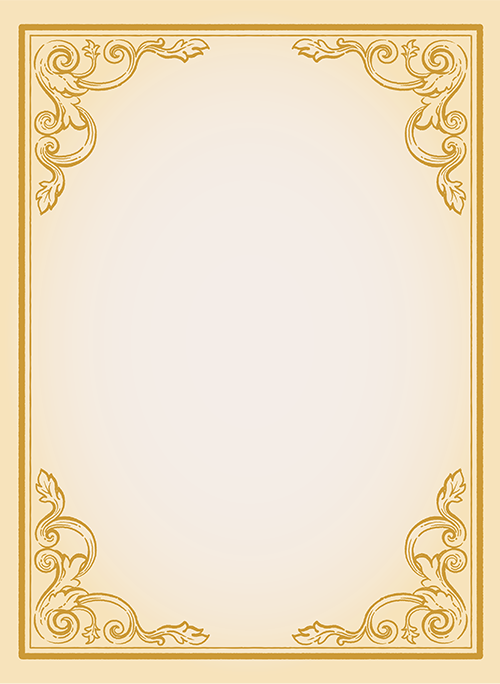キッチンの隅に置かれている椅子が二脚だけのテーブルセット。そこに座る様にと促され叶子は素直に従った。
グレースはケトルに水を入れてシュンシュンと湯気が上がるのを今か今かと待ちわびている。やがて、沸点まで熱された熱々のお湯が沸くと、ティーポットの中に入った茶葉を循環させるようにして高い位置から勢いよくティーポットに注ぎいれる。ティーコージーを被せた後、砂時計を引っくり返す。全てをシルバーのトレーの上に乗せ叶子の傍までやってくると、ようやくグレースが腰掛けた。
「少し、落ち着きなさったかな?」
「はい。有難うございます」
叶子の様子を見てニッコリと微笑んだかと思うと、次には眉間に皺を寄せた。
「しかし、女の子を泣かせるとは。坊ちゃんも酷い事をするもんだ」
「い、いえ、私が悪いんです」
思ったとおりの返事が返ってきて、グレースの目尻が下がる。
今までジャックが付き合ってきた女性は皆自己主張が激しく、ジャックと喧嘩をしても、誰一人折れるのはおろか、自分に非があるなんて言う女性は一人も居なかった。
かと言って、カナが自己主張のしないつまらない人間なのかと言われるとそうではなく、ちゃんと自分の非を認めても一緒に居る事が出来ないのだと部屋を飛び出したのだから、決して流されてしまうような人間では無いのだろうと、グレースは思った。
女性を振り回すことがあっても振り回されることが無いジャックが、珍しく女性に夢中になっている理由が判る気がした。
グレースがティーセットを広げながら、紅茶を淹れる準備を始めた。
「──坊ちゃんは正直すぎる所があるんです。時にそれが強引に感じることがありますが、慣れればとてもコントロールしやすい方ですよ」
砂が全部落ちたのを横目で確認するとティーストレーナーに手を伸ばし、紅茶を注ぎいれながら彼女に向かってウィンクをした。
淹れたての紅茶と温めたミルクを彼女に差し出しソレを飲むようにと手で促される。叶子は軽く頭を下げるとティーカップに手を伸ばし、ゴクリと一口喉に流し入れた。
「……おいしい」
思わず自然に出た言葉に、グレースはにっこりと微笑んでいる。
「……でも、カナさんに対しては随分我慢なされてる様で、正直びっくり致しました」
そう言って、グレースもカップに口をつけた。
「我慢?」
「こういう話をするのは良くないのかも知れませんが……、坊ちゃんは自分の気持ちを抑える事が苦手な方でして、いい事も悪い事も全部吐き出さないと気が済まないんです。駆け引きって言うのが出来ないタイプなんですな」
「そうなんですか?」
「ただ、カナさんに対してはかなり自分を押し殺していましたね。仕事でも恋愛でも自分についてこれる奴だけついてくればいい。っていう考えの方だったのに、自分の気持ちを隠してまであなたの側に居たかった様に感じました」
「……。」
叶子にとっては十分強引に見える彼だが、それが彼の本性でないとグレースによって知らされる。自分が彼を我慢させていたんだという事実が、彼女の胸をぎゅっと締め付けた。
「私は――。私はどうしたらいいのでしょうか」
「ほ?」
「彼の気持ちを受け入れたいとは思っているのですが、どうしても過去の事が引っかかってしまって素直に受け入れる事が出来ないんです」
「それは、……もしやカレンさんの事ですかな?」
ティーカップを見つめながら小さく頷いた。
こんな話をしてしまって本当に良いのだろうか。少なくとも自分よりカレンとの付き合いが長いグレースに、こんな話をするのはいささか不利な気がする。
しかし、彼の事を良く知っているグレースだからこそ、何か解決策が見出せるかもしれないと、彼女は藁にも縋る思いだった。
言っていいものかどうなのかと、悩んでいるような表情をしたグレースが大きな溜息を吐いた。そして、とうとうその重い口を開いた。
「確かに、あのお二人は以前近しい存在ではありました。……ですが、どちらかと言うとカレンさんの一方的な感情だったと私は思っております」
「そうでしょうか……」
二人は特別な関係だったという事実を知り、自分から相談しておきながらも落ち込んでしまった。両手で包み込むようにして持ったティーカップに視線を落とし、小さく息を吐いた。
「それに今は、カレンさんは他の方とご結婚なさってますし」
「……えっ!?」
続けられた言葉に耳を疑う。手元を見ていた視線は勢いよくグレースへと向けられた。
「あ、ご存知無かったですか?」
「は、はい」
「なんでしょう、妬いておられるのでしょうね。坊ちゃんとは長い付き合いで一時とは言え男女の仲……コホン、仲良くされておられましたし」
つい口を滑らせてしまったと笑いながら舌を出したグレースを見ていると、カレンとの仲を気にしている自分がなんだか滑稽に思えてきた。 大事なのは過去ではなく、現在(いま)なのだと、グレースに教えてもらっている様な気がした。
「坊ちゃんは意外に単純なお方ですから、貴方も直ぐに操れるようになりますよ」
そう言うと声を出して笑い出したグレースに、叶子もつられて笑ってしまう。声を出して思いっきり笑うと、くよくよしていた自分が凄くちっぽけに思えて来た。
きっとあのまま帰っていたら、もう彼に会うことは出来なかっただろう。グレースに会えて良かったと今はそう心から思えるようになった。
◇◆◇
グレースと談笑しながら玄関へと向かうと、ドアの横に置かれている椅子に頭をうなだれて座っていた彼が二人を見つけた。その彼の表情は今にも泣きそうで、そしてとても不安そうな顔をしていた。
ジャックの姿を見つけた叶子は進めていた足を一瞬止めてしまったが、グレースに背中を軽く押されゆっくりと彼の元へと歩いていった。
彼の傍まで行くと大きな手がそっと背中に回る。叶子の顔を覗き込むようにして様子を伺う彼の態度を見た叶子は強張った笑みを浮かべ、彼に支えられるようにしてドアへと向かった。
後方にいるグレースに彼が振り返ると「ありがとう」と、声を出さずに口を動かした。まるで自分の役目を終えたかのようにグレースはにっこりとほほ笑み返すと静かにその場を離れていった。
「本当に帰るの?」
頭上から、消え入りそうな彼の声が聞こえる。
「はい、明日も仕事があるので」
「そっか……」
彼が扉に手を掛けた時、叶子の足がピタリと止まった。
「──? どうしたの?」
腫れ物に触る様な態度で自分に接している彼を見て、胸がぎゅっと痛んだ。
今、目の前にいるのは本当の彼じゃない。自分の思っている事をちゃんと言えて、いつも堂々としているからこそ、魅力的な人なのだ、と自分がそんな風にさせてしまっていることがとても辛かった。
俯いていた顔を上げると、意を決して彼に告げた。
「──私、貴方が好きです。すぐには無理かもしれないけど、貴方と向き合っていきたいの」
「……。」
彼女からの突然の告白に、瞬きをするのも忘れ放心状態になっている。彼のシャツの胸元を掴むと、グイっと引き寄せ彼女の方から口づけた。
明かりの落とされた玄関の透かし戸に、呼んでおいたタクシーのヘッドライトが入り込んでいる。
タクシーが到着を知らせるクラクションが何度も鳴り響く中、そのライトの明かりに包まれながら二人の影はやがて一つになり、いつまでも固く抱き合っていた。
グレースはケトルに水を入れてシュンシュンと湯気が上がるのを今か今かと待ちわびている。やがて、沸点まで熱された熱々のお湯が沸くと、ティーポットの中に入った茶葉を循環させるようにして高い位置から勢いよくティーポットに注ぎいれる。ティーコージーを被せた後、砂時計を引っくり返す。全てをシルバーのトレーの上に乗せ叶子の傍までやってくると、ようやくグレースが腰掛けた。
「少し、落ち着きなさったかな?」
「はい。有難うございます」
叶子の様子を見てニッコリと微笑んだかと思うと、次には眉間に皺を寄せた。
「しかし、女の子を泣かせるとは。坊ちゃんも酷い事をするもんだ」
「い、いえ、私が悪いんです」
思ったとおりの返事が返ってきて、グレースの目尻が下がる。
今までジャックが付き合ってきた女性は皆自己主張が激しく、ジャックと喧嘩をしても、誰一人折れるのはおろか、自分に非があるなんて言う女性は一人も居なかった。
かと言って、カナが自己主張のしないつまらない人間なのかと言われるとそうではなく、ちゃんと自分の非を認めても一緒に居る事が出来ないのだと部屋を飛び出したのだから、決して流されてしまうような人間では無いのだろうと、グレースは思った。
女性を振り回すことがあっても振り回されることが無いジャックが、珍しく女性に夢中になっている理由が判る気がした。
グレースがティーセットを広げながら、紅茶を淹れる準備を始めた。
「──坊ちゃんは正直すぎる所があるんです。時にそれが強引に感じることがありますが、慣れればとてもコントロールしやすい方ですよ」
砂が全部落ちたのを横目で確認するとティーストレーナーに手を伸ばし、紅茶を注ぎいれながら彼女に向かってウィンクをした。
淹れたての紅茶と温めたミルクを彼女に差し出しソレを飲むようにと手で促される。叶子は軽く頭を下げるとティーカップに手を伸ばし、ゴクリと一口喉に流し入れた。
「……おいしい」
思わず自然に出た言葉に、グレースはにっこりと微笑んでいる。
「……でも、カナさんに対しては随分我慢なされてる様で、正直びっくり致しました」
そう言って、グレースもカップに口をつけた。
「我慢?」
「こういう話をするのは良くないのかも知れませんが……、坊ちゃんは自分の気持ちを抑える事が苦手な方でして、いい事も悪い事も全部吐き出さないと気が済まないんです。駆け引きって言うのが出来ないタイプなんですな」
「そうなんですか?」
「ただ、カナさんに対してはかなり自分を押し殺していましたね。仕事でも恋愛でも自分についてこれる奴だけついてくればいい。っていう考えの方だったのに、自分の気持ちを隠してまであなたの側に居たかった様に感じました」
「……。」
叶子にとっては十分強引に見える彼だが、それが彼の本性でないとグレースによって知らされる。自分が彼を我慢させていたんだという事実が、彼女の胸をぎゅっと締め付けた。
「私は――。私はどうしたらいいのでしょうか」
「ほ?」
「彼の気持ちを受け入れたいとは思っているのですが、どうしても過去の事が引っかかってしまって素直に受け入れる事が出来ないんです」
「それは、……もしやカレンさんの事ですかな?」
ティーカップを見つめながら小さく頷いた。
こんな話をしてしまって本当に良いのだろうか。少なくとも自分よりカレンとの付き合いが長いグレースに、こんな話をするのはいささか不利な気がする。
しかし、彼の事を良く知っているグレースだからこそ、何か解決策が見出せるかもしれないと、彼女は藁にも縋る思いだった。
言っていいものかどうなのかと、悩んでいるような表情をしたグレースが大きな溜息を吐いた。そして、とうとうその重い口を開いた。
「確かに、あのお二人は以前近しい存在ではありました。……ですが、どちらかと言うとカレンさんの一方的な感情だったと私は思っております」
「そうでしょうか……」
二人は特別な関係だったという事実を知り、自分から相談しておきながらも落ち込んでしまった。両手で包み込むようにして持ったティーカップに視線を落とし、小さく息を吐いた。
「それに今は、カレンさんは他の方とご結婚なさってますし」
「……えっ!?」
続けられた言葉に耳を疑う。手元を見ていた視線は勢いよくグレースへと向けられた。
「あ、ご存知無かったですか?」
「は、はい」
「なんでしょう、妬いておられるのでしょうね。坊ちゃんとは長い付き合いで一時とは言え男女の仲……コホン、仲良くされておられましたし」
つい口を滑らせてしまったと笑いながら舌を出したグレースを見ていると、カレンとの仲を気にしている自分がなんだか滑稽に思えてきた。 大事なのは過去ではなく、現在(いま)なのだと、グレースに教えてもらっている様な気がした。
「坊ちゃんは意外に単純なお方ですから、貴方も直ぐに操れるようになりますよ」
そう言うと声を出して笑い出したグレースに、叶子もつられて笑ってしまう。声を出して思いっきり笑うと、くよくよしていた自分が凄くちっぽけに思えて来た。
きっとあのまま帰っていたら、もう彼に会うことは出来なかっただろう。グレースに会えて良かったと今はそう心から思えるようになった。
◇◆◇
グレースと談笑しながら玄関へと向かうと、ドアの横に置かれている椅子に頭をうなだれて座っていた彼が二人を見つけた。その彼の表情は今にも泣きそうで、そしてとても不安そうな顔をしていた。
ジャックの姿を見つけた叶子は進めていた足を一瞬止めてしまったが、グレースに背中を軽く押されゆっくりと彼の元へと歩いていった。
彼の傍まで行くと大きな手がそっと背中に回る。叶子の顔を覗き込むようにして様子を伺う彼の態度を見た叶子は強張った笑みを浮かべ、彼に支えられるようにしてドアへと向かった。
後方にいるグレースに彼が振り返ると「ありがとう」と、声を出さずに口を動かした。まるで自分の役目を終えたかのようにグレースはにっこりとほほ笑み返すと静かにその場を離れていった。
「本当に帰るの?」
頭上から、消え入りそうな彼の声が聞こえる。
「はい、明日も仕事があるので」
「そっか……」
彼が扉に手を掛けた時、叶子の足がピタリと止まった。
「──? どうしたの?」
腫れ物に触る様な態度で自分に接している彼を見て、胸がぎゅっと痛んだ。
今、目の前にいるのは本当の彼じゃない。自分の思っている事をちゃんと言えて、いつも堂々としているからこそ、魅力的な人なのだ、と自分がそんな風にさせてしまっていることがとても辛かった。
俯いていた顔を上げると、意を決して彼に告げた。
「──私、貴方が好きです。すぐには無理かもしれないけど、貴方と向き合っていきたいの」
「……。」
彼女からの突然の告白に、瞬きをするのも忘れ放心状態になっている。彼のシャツの胸元を掴むと、グイっと引き寄せ彼女の方から口づけた。
明かりの落とされた玄関の透かし戸に、呼んでおいたタクシーのヘッドライトが入り込んでいる。
タクシーが到着を知らせるクラクションが何度も鳴り響く中、そのライトの明かりに包まれながら二人の影はやがて一つになり、いつまでも固く抱き合っていた。