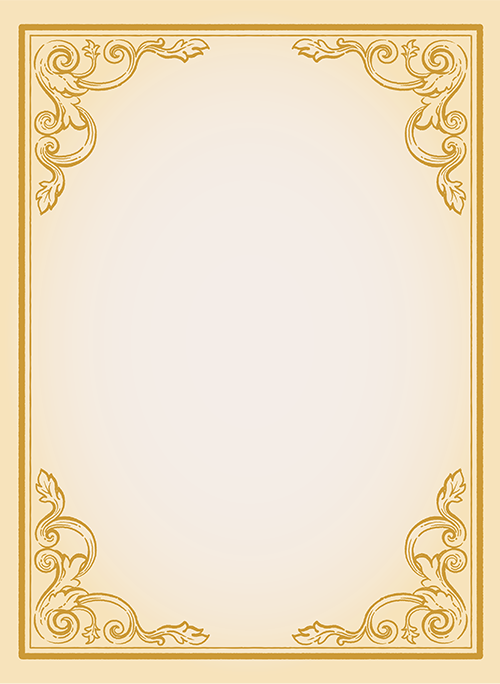その時の彼女の顔を見た途端、手の動きは勿論、思考までもがピタリと停止した。顔を背け歯を食いしばり、目を硬く閉じている。よく見ると身体が小刻みに震えているのも判った。
何の抵抗も示さなくなった彼女に、ちょっと強引ではあったけれど、やっと自分の事を理解して己を解放する事に同意したのだとジャックは思っていた。
「どうして?」
ジャックが問うと、彼女の目から一筋の涙が頬を伝った。
「どうして抵抗するのを止めたの? ……本当は嫌なんじゃないの?」
再び問いかけると、ゆっくりと目を開け彼の方へと視線を向けた。噛みすぎた口唇が痛々しく真っ赤になっている。
「私が悪いから。私が軽率すぎたの、が」
「そうだよ、君は男というものを全く判っていない。……でも、だからって無理矢理抱かれて……、カナはそれで平気なの?」
「わ、からない……けど、――怖くて」
「怖い?」
小刻みに震えながら首を小さく縦に振って恐怖におののく彼女を見た時、一気に後悔の念に駆られる。
「……。」
ジャックは捲れ上がった彼女のシャツを下ろすと、そのまま彼女の横に倒れこんだ。
彼女の言葉に愕然とした。何もかもを彼女一人のせいにして、己の感情だけを優先した自分に腹が立つ。
彼女を守りたい気持ちで居たはずの自分が、彼女の脅威となってしまっている。
どうしても空回りしてしまう自分がいる。
どうすれば判り合えるのだろう。
彼女の事を想う速度にどうやら彼女はついて来れず、振り返るとずっと遠いところに彼女はまだ立っているかの様だ。そんな状態で半ば強引に身体を重ねようとしても温度差があって当たり前なのに、一体自分は何を焦っているのかと溜息を吐いた。
勿論、彼女の身体が目的ではなく、ジャックはただ‟繋がり”が欲しかった。しかし、彼女とはまだ心すら繋がっていないのだと気付かされ、情けない思いで一杯になった。
◇◆◇
「おやすみ、グレース」
「はい、おやすみ」
部屋の明かりをパチンと消し、大きな音を立ててしまわないようにゆっくりと扉を閉めた。
「さて、私もそろそろ寝るとしましょうか」
今日も一日終わったと、少し曲がった腰をトントンと叩きながらグレースはひとりごちた。
二階から手すりを掴みゆっくりと階段を下り始めると、階下のリビングの扉が勢いよく開く音が耳に入り、手摺越しにグレースが階下を見下ろした。コートを手にした女性がリビングから飛び出したかと思うと、まるで何かから逃げる様に玄関の方向へと駆けていくのが見える。
(はて? あのお方は確か……)
その女性の姿に見覚えがあると思ったグレースは眼鏡の縁を持ち上げ、ほんの少し身を乗り出した。
「カナ! 待って!」
彼女のすぐ後をジャックが追って飛び出してきた。
「おやまぁ、あんなに逃げ腰になっていたのが、嘘みたいですな」
今の二人の状況が飲み込めたグレースは、優しい眼差しで二人に向かってほほ笑んだ。
◇◆◇
ベッドの上での耐え難い羞恥から解放された叶子は、いてもたってもいられなくなった。再び上体を起こすと滑り落ちる様にしてベッドから降り、髪と服の乱れを手早く直しながらソファーの方へと早足で向かう。テーブルの横に置いていた自分のコートとバッグを手に取ると、彼に背中を向けながらピタリと動きを止めた。
ベッドの上で上体を起こした彼が、そんな叶子の様子をじっと見つめている。
「──カナ?」
「わ、私帰ります!」
彼の顔も見ることが出来ず、慌てて部屋から飛び出していった。
◇◆◇
彼が後を追い、長い廊下の途中で叶子の腕を捕まえた。
「カナ! こんな時間に一人でどうやって帰るの!?」
「大丈夫です、タクシーでも捕まえるから」
「こんな所でタクシーなんか捕まんないよ!」
確かに彼の家は人里離れた山の中に建っていて、周りは人の気配どころか店一軒すら建っていない。そんな場所で、しかもこんなに夜も更けた後では、流しのタクシーなんて当然走っているはずも無いだろう。だからといって、このまま彼と同じ空間にいるのは居心地が悪く、どうにかしてココから逃げ出そうと後先考えずに部屋を飛び出してしまった。
「で、電話で呼ぶから!」
掴まれた腕を振り解き再び長い廊下を進む。でもまたすぐに彼に捕まってしまい、振り返らされた瞬間、今度は両腕を掴まれた。
「じゃあ、タクシーが来るまでここにいるんだ」
叶子の表情を窺うようにして、彼が下から覗き込んでくる。
「だ、大丈夫です、子供じゃあるまいし。離して下さい」
ぷいと顔を背けると、頭上から語気鋭く彼が言い放った。
「子供じゃないから心配してるんじゃないか!」
「──っ」
突然の大声に慄き、ビクッと肩を竦める。両腕を掴まれているから逃れることは出来ないが、反射的に身体が反り返る。
「大体、子供だったらこんな時間に一人で外へ出るなんて事しないよ! 大人だから、……僕の大事な女性(ひと)だから余計に心配なんだよ! それ位わかれよ!」
言いながら、まるで聞き分けの無い子供に諭すように何度も身体を揺すられる。
彼の自分に対する想いを聞かされ、また胸の奥がチクンと傷む。耐え切れず、叶子の目から大粒の涙がポロポロと零れ始めた。涙を見せる事でまた彼を困らせてしまうのだと感じながらも、一度決壊を破ってしまったものはすぐに収める事が出来ない。無駄な事だと自覚しながらも、泣いていると気付かれないように更に後方へと顔を背けた。
又、彼を怒らせてしまった。
何をやっても空回りして、結局彼の怒りに触れてしまう。
「ごめ、んなさい」
「……。」
結局、溢れる涙を抑えきれず、両手で顔を塞いだ。
そんな叶子の姿を目の当たりにし、ジャックの眉根がぐっと寄せられる。掴んでいた彼女の両腕を開放し、自分が傷つけてしまったせいで泣いている彼女を直視する事が出来ず、ジャックは叶子に背を向けた。
明かりの落とされた廊下の窓から、月の明かりが差し込でいる。
お互い声を掛けることが出来ず二人とも押し黙っていると、暗闇の奥から聞き覚えのある声が聞こえた。
「あら、いらしてたんですね」
事の事態を把握しているのかしていないのか、グレースの呑気な声がした。二人は驚くと共に、暗闇の中の声のする方へ視線を向けた。
暗闇の中、普段通りニコニコと笑みを浮かべて立っているグレースは、
「丁度いいお茶が手に入ったんですよ。よろしければ召し上がって行きませんか?」
と、叶子を誘う。
その口振りが、自分たちに気を使ってそんな事を言っているのだろうと、ジャックと叶子も気付いていた。
「あの、でも私そろそろ」
「まあまあ、いいじゃありませんか。ささっ、どうぞこちらへ」
叶子の側まで来ると、乾燥したしわくちゃの手が彼女の手を取る。涙を一杯溜めた目で彼へと視線を向けると、コクンと小さく頷いてジャックはその場を後にした。
「──。」
グレースが彼女を連れて行ったことで、ジャックが自分の部屋に戻ろうと踵を返す。両手をズボンのポケットに突っ込みながら、グレースが彼女を引き止めてくれたことにホッと安堵の表情を浮かべていた。
今の自分だと何かしようとする度に余計に彼女を追い詰めてしまっている。グレースがどういうつもりで彼女を連れて行ったのかは正直判らなかったが、長年自分の事を見てくれていたグレースの事だから、自分の不器用な所を上手く彼女に伝えてくれるのでは。と、他人任せではあるが、そうあって欲しいとジャックは願った。
◇◆◇
叶子の手を引いてグレースはキッチンへと向かう。さすがにグレースの手を振り解く事が出来なず、指先で涙を拭きながらグレースの後をただ黙ってついて歩いた。
そんな叶子の前に、すっとハンカチが差し出される。
「えぇと、カナさん? でしたかな。もう夜も更けましたから、今晩は泊まっていかれなさい」
「……ありがとう、ございます」
ニッコリと微笑むグレースの手からハンカチを受け取ると、温かいその言葉に又涙が滲む。
懐かしい匂いのするハンカチを目に押し当てると、緊迫していた気持ちが次第にゆるゆると解れていった。
何の抵抗も示さなくなった彼女に、ちょっと強引ではあったけれど、やっと自分の事を理解して己を解放する事に同意したのだとジャックは思っていた。
「どうして?」
ジャックが問うと、彼女の目から一筋の涙が頬を伝った。
「どうして抵抗するのを止めたの? ……本当は嫌なんじゃないの?」
再び問いかけると、ゆっくりと目を開け彼の方へと視線を向けた。噛みすぎた口唇が痛々しく真っ赤になっている。
「私が悪いから。私が軽率すぎたの、が」
「そうだよ、君は男というものを全く判っていない。……でも、だからって無理矢理抱かれて……、カナはそれで平気なの?」
「わ、からない……けど、――怖くて」
「怖い?」
小刻みに震えながら首を小さく縦に振って恐怖におののく彼女を見た時、一気に後悔の念に駆られる。
「……。」
ジャックは捲れ上がった彼女のシャツを下ろすと、そのまま彼女の横に倒れこんだ。
彼女の言葉に愕然とした。何もかもを彼女一人のせいにして、己の感情だけを優先した自分に腹が立つ。
彼女を守りたい気持ちで居たはずの自分が、彼女の脅威となってしまっている。
どうしても空回りしてしまう自分がいる。
どうすれば判り合えるのだろう。
彼女の事を想う速度にどうやら彼女はついて来れず、振り返るとずっと遠いところに彼女はまだ立っているかの様だ。そんな状態で半ば強引に身体を重ねようとしても温度差があって当たり前なのに、一体自分は何を焦っているのかと溜息を吐いた。
勿論、彼女の身体が目的ではなく、ジャックはただ‟繋がり”が欲しかった。しかし、彼女とはまだ心すら繋がっていないのだと気付かされ、情けない思いで一杯になった。
◇◆◇
「おやすみ、グレース」
「はい、おやすみ」
部屋の明かりをパチンと消し、大きな音を立ててしまわないようにゆっくりと扉を閉めた。
「さて、私もそろそろ寝るとしましょうか」
今日も一日終わったと、少し曲がった腰をトントンと叩きながらグレースはひとりごちた。
二階から手すりを掴みゆっくりと階段を下り始めると、階下のリビングの扉が勢いよく開く音が耳に入り、手摺越しにグレースが階下を見下ろした。コートを手にした女性がリビングから飛び出したかと思うと、まるで何かから逃げる様に玄関の方向へと駆けていくのが見える。
(はて? あのお方は確か……)
その女性の姿に見覚えがあると思ったグレースは眼鏡の縁を持ち上げ、ほんの少し身を乗り出した。
「カナ! 待って!」
彼女のすぐ後をジャックが追って飛び出してきた。
「おやまぁ、あんなに逃げ腰になっていたのが、嘘みたいですな」
今の二人の状況が飲み込めたグレースは、優しい眼差しで二人に向かってほほ笑んだ。
◇◆◇
ベッドの上での耐え難い羞恥から解放された叶子は、いてもたってもいられなくなった。再び上体を起こすと滑り落ちる様にしてベッドから降り、髪と服の乱れを手早く直しながらソファーの方へと早足で向かう。テーブルの横に置いていた自分のコートとバッグを手に取ると、彼に背中を向けながらピタリと動きを止めた。
ベッドの上で上体を起こした彼が、そんな叶子の様子をじっと見つめている。
「──カナ?」
「わ、私帰ります!」
彼の顔も見ることが出来ず、慌てて部屋から飛び出していった。
◇◆◇
彼が後を追い、長い廊下の途中で叶子の腕を捕まえた。
「カナ! こんな時間に一人でどうやって帰るの!?」
「大丈夫です、タクシーでも捕まえるから」
「こんな所でタクシーなんか捕まんないよ!」
確かに彼の家は人里離れた山の中に建っていて、周りは人の気配どころか店一軒すら建っていない。そんな場所で、しかもこんなに夜も更けた後では、流しのタクシーなんて当然走っているはずも無いだろう。だからといって、このまま彼と同じ空間にいるのは居心地が悪く、どうにかしてココから逃げ出そうと後先考えずに部屋を飛び出してしまった。
「で、電話で呼ぶから!」
掴まれた腕を振り解き再び長い廊下を進む。でもまたすぐに彼に捕まってしまい、振り返らされた瞬間、今度は両腕を掴まれた。
「じゃあ、タクシーが来るまでここにいるんだ」
叶子の表情を窺うようにして、彼が下から覗き込んでくる。
「だ、大丈夫です、子供じゃあるまいし。離して下さい」
ぷいと顔を背けると、頭上から語気鋭く彼が言い放った。
「子供じゃないから心配してるんじゃないか!」
「──っ」
突然の大声に慄き、ビクッと肩を竦める。両腕を掴まれているから逃れることは出来ないが、反射的に身体が反り返る。
「大体、子供だったらこんな時間に一人で外へ出るなんて事しないよ! 大人だから、……僕の大事な女性(ひと)だから余計に心配なんだよ! それ位わかれよ!」
言いながら、まるで聞き分けの無い子供に諭すように何度も身体を揺すられる。
彼の自分に対する想いを聞かされ、また胸の奥がチクンと傷む。耐え切れず、叶子の目から大粒の涙がポロポロと零れ始めた。涙を見せる事でまた彼を困らせてしまうのだと感じながらも、一度決壊を破ってしまったものはすぐに収める事が出来ない。無駄な事だと自覚しながらも、泣いていると気付かれないように更に後方へと顔を背けた。
又、彼を怒らせてしまった。
何をやっても空回りして、結局彼の怒りに触れてしまう。
「ごめ、んなさい」
「……。」
結局、溢れる涙を抑えきれず、両手で顔を塞いだ。
そんな叶子の姿を目の当たりにし、ジャックの眉根がぐっと寄せられる。掴んでいた彼女の両腕を開放し、自分が傷つけてしまったせいで泣いている彼女を直視する事が出来ず、ジャックは叶子に背を向けた。
明かりの落とされた廊下の窓から、月の明かりが差し込でいる。
お互い声を掛けることが出来ず二人とも押し黙っていると、暗闇の奥から聞き覚えのある声が聞こえた。
「あら、いらしてたんですね」
事の事態を把握しているのかしていないのか、グレースの呑気な声がした。二人は驚くと共に、暗闇の中の声のする方へ視線を向けた。
暗闇の中、普段通りニコニコと笑みを浮かべて立っているグレースは、
「丁度いいお茶が手に入ったんですよ。よろしければ召し上がって行きませんか?」
と、叶子を誘う。
その口振りが、自分たちに気を使ってそんな事を言っているのだろうと、ジャックと叶子も気付いていた。
「あの、でも私そろそろ」
「まあまあ、いいじゃありませんか。ささっ、どうぞこちらへ」
叶子の側まで来ると、乾燥したしわくちゃの手が彼女の手を取る。涙を一杯溜めた目で彼へと視線を向けると、コクンと小さく頷いてジャックはその場を後にした。
「──。」
グレースが彼女を連れて行ったことで、ジャックが自分の部屋に戻ろうと踵を返す。両手をズボンのポケットに突っ込みながら、グレースが彼女を引き止めてくれたことにホッと安堵の表情を浮かべていた。
今の自分だと何かしようとする度に余計に彼女を追い詰めてしまっている。グレースがどういうつもりで彼女を連れて行ったのかは正直判らなかったが、長年自分の事を見てくれていたグレースの事だから、自分の不器用な所を上手く彼女に伝えてくれるのでは。と、他人任せではあるが、そうあって欲しいとジャックは願った。
◇◆◇
叶子の手を引いてグレースはキッチンへと向かう。さすがにグレースの手を振り解く事が出来なず、指先で涙を拭きながらグレースの後をただ黙ってついて歩いた。
そんな叶子の前に、すっとハンカチが差し出される。
「えぇと、カナさん? でしたかな。もう夜も更けましたから、今晩は泊まっていかれなさい」
「……ありがとう、ございます」
ニッコリと微笑むグレースの手からハンカチを受け取ると、温かいその言葉に又涙が滲む。
懐かしい匂いのするハンカチを目に押し当てると、緊迫していた気持ちが次第にゆるゆると解れていった。