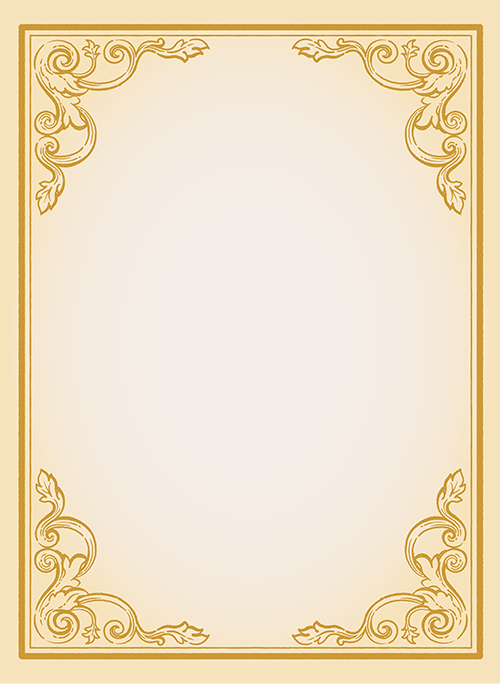そもそも、叶子が家に来ると聞いた時点で、心の何処かで疚(やま)しい気持ちがあったのかもしれない。どんなに紳士を気取ってみても、内にある欲望を抑えきることは難しい。人気の多い外で会うならまだ理性も働くのだろうが、普段自分が寝起きしているこの部屋で手を伸ばせばすぐにでも抱き締められる距離に彼女が居て、何もせず我慢できる男などこの世に存在するのだろうか。
これからする自分の行動は雄が雌を求めるのと同じで自然の摂理なのだと、まるで自分に言い訳をしているかのようだった。
「あの……」
見つめていた口唇がゆっくりと開き、蕩けるような彼女の甘い声がそこから零れ落ちた。
ジャックはチョコが入っている小さな箱を置くと、タネを仕込む手を止める。
「うん?」
子供を扱う様な優しい声音で彼女の言葉を受け入れる。先程迄とは違った低音の落ち着きのある声。
「どうして私にチョコを?」
まだ手品のタネを仕込んでいると思っている叶子は、目を閉じたままでそのチョコには何か意味があるのかをジャックに訊ねた。
「僕の育った国ではね、バレンタインデーは男性から愛する女性にチョコを贈るんだよ。ロマンティックなディナーを楽しんだりしてね」
「へー、そうなんですね」
さらっと言った『愛する女性にチョコを贈る』というジャックの言葉の意味を、叶子は気付いていないのか『国が違えばイベントの習慣でさえも変わるんですね』と感心している。
察しの悪い彼女にもどかしくなったジャックはとうとう理性を失い、行動に出てしまった。
彼女の口唇にふわんと柔らかい何かが触れる。
「――? ……、――っ!?」
ゆっくりと目を開けてみれば目と鼻の先にジャックの顔があった事に驚き、肘をついた状態で後ろに倒れこむ様にして仰け反った。
完全にパニック状態になっている彼女を余所に、彼女をじっと見つめるジャックの目は先ほどまでの拗ねた子供の様な表情とは全く違い、トロンとしたその目は妙な艶っぽさがあった。
大きな目で何度も瞬きを繰り返す叶子に、ジャックがクスリと笑う。
「ちゃんと言ってなかったね」
「――え? 何、を?」
「僕は君を愛しているって事を。――心の底からね」
「――。」
『愛している』その言葉の持つ意味の重さがズシンと心に響き渡る。
そんな言葉を言われた事は今だかつて一度も無ければ、『好きだ』と言う言葉でさえもさほどない。過去に付き合った事のある数少ない男性達からは、付き合い始める時に一度聞いた切りで、叶子にとっては聞き慣れていないワードの一つだった。
『好き』と言う言葉すら耐性が無いというのに、『愛している』と彼が言う。初めて聞かされたその言葉は彼女に安らぎを与え、同時に彼への想いを加速させていった。
彼に対する気持ちが大きく膨らみはじめていたのを確かに自覚してはいたが、かといって何と答えればいいのか返す言葉が見つからない。叶子はただじっと彼の目を見つめ返す事しか出来なかった。
そうこうしている内にソファーが沈み、彼が手を前について更に彼女に近づいて来ようとしているのが判った。
彼の手が叶子の顔にかかった髪をかき上げる。その手をそのまま首の後ろに回し、肘をつき姿勢が苦しそうな叶子の肩をそっと支えながら二人は口唇を重ね合い、そのままゆっくりとソファーに沈んで行った。
「……っ、……」
幾度も口唇を啄ばんでは笑顔を見せ、彼は短い口付けをもったいぶるかの様に楽しんでいる。
叶子はほんの少しの抵抗を見せてはいるが、繰り返し浴びせられる甘い口づけに完全に虜になってしまっていた。離れた時に魅せる彼女の潤んだ瞳を見ると、今した所なのにすぐにもう一度触れたくなるのか又口唇を寄せてしまう。そんなループをただひたすら繰り返していた。
叶子の下口唇を軽く食みながら少し距離を取った時、寸分の狂いも無い眼差しが叶子に向けられる。
そして、まるで叶子に言い聞かせるように、
「愛しているよ」
と、もう一度そう告げると、より彼女の深い所に潜り込む為に、顔の角度を変えながら貪る様な甘い口づけを交わした。
「……んっ……」
啄ばむ様なキスを繰り返した後にやって来た官能的な刺激に耐え切れず、思わず声が漏れる。角度を変えて彼が距離を狭め優しく叶子の口唇に触れた時、彼の舌が叶子の歯列をなぞりあげた。その事に驚いて僅かに口を開けた瞬間、ここぞとばかりに彼の舌がぬるりと口腔内に侵入を遂げた。
「……あっ、……んっ……」
ソファーに押し倒された格好の叶子の上に彼が覆いかぶさっている。彼の腕を掴み少しの抵抗見せていたその手はいつしか、離れたくないと言わんばかりに彼のシャツを握りしめていた。
(――愛している? 彼が? 私を?)
彼の舌に惑わされながら、先ほどの彼の言葉を反芻していた。
長い手足、大きくてスッとした目元に薄い唇。色素を感じられない程の白い肌が彼を中性的に魅せていて、その容姿は人並み以上、いや人並み外れている。そんな誰もが目を引く容姿もさることながら仕事も出来る彼が女性の扱いも手馴れたものだという事は、ほんの数回会っただけではあったが自ずとわかるものであった。
黙っていても女性が放っておかないであろうそんな人に、突然好きだと言われた事がにわかに信じ難い。
好意をもたれているのではとほんの少し自覚してはいたものの、きっと大勢いる中の一人なのだと思ってきた。誰が見ても超がつくほどのハイスペックな彼が、よりにもよって超がつくほどの凡人である自分を好きになるとは到底思えない。
「カナ、――好きだよ」
「……っ……」
それでも目の前にいる彼が真面目な顔で自分を好きだと何度も告げる。そして、優しく触れられるだけで、もしかすると本当なのかもと錯覚しそうになってしまう。
こんな事は駄目だと思う反面、心のどこかで彼とこうなりたい願望があるのか、彼に抗えない。
幾度となく舌を絡め合う度耳に届く水音で、かあっと叶子の頬が染まった。
彼の指先が頬に触れる。その指先はそのまま髪を梳くようにして流れ、彼の大きな掌は叶子の後頭部を抱え込んだ。その手はやがてうなじへと下降を進めた後、次には顎のラインをツーッとなぞる。貪る様なキスとは逆に触れるか触れないかの距離を保つその指先が、まるで飴と鞭を同時に与えられて焦らされているかの様だった。
「……っ」
顎を伝っていた指先がやがて首筋を辿り始める。ゆっくりと鎖骨に沿う様にして襟を割り、温かい彼の手が左の肩に直に触れた。
柔らかくて温かい、包み込むような彼の大きな手が優しく触れる度に、焦れったい感情が生まれて来る。今、彼に触れられている場所全てが熱を帯び始め、彼だけで無く叶子も又、彼を求めているのだと気付かされた。
ソフトな手の動きとは違い、口腔内を縦横無尽に動き回っている彼の舌を確かに感じる。
角度を変える度に口の隙間から漏れ出す水音と、呼吸を抑えようとする自分のくぐもった声が聴覚を刺激し、もっと、もっとと、高みの方へ連れて行く。
深く甘い口づけを交わす二人には何も阻むものはなかった。
もう彼には振り回されない、そう決めたのにも関わらず目の前の彼に溺れて行った。
これからする自分の行動は雄が雌を求めるのと同じで自然の摂理なのだと、まるで自分に言い訳をしているかのようだった。
「あの……」
見つめていた口唇がゆっくりと開き、蕩けるような彼女の甘い声がそこから零れ落ちた。
ジャックはチョコが入っている小さな箱を置くと、タネを仕込む手を止める。
「うん?」
子供を扱う様な優しい声音で彼女の言葉を受け入れる。先程迄とは違った低音の落ち着きのある声。
「どうして私にチョコを?」
まだ手品のタネを仕込んでいると思っている叶子は、目を閉じたままでそのチョコには何か意味があるのかをジャックに訊ねた。
「僕の育った国ではね、バレンタインデーは男性から愛する女性にチョコを贈るんだよ。ロマンティックなディナーを楽しんだりしてね」
「へー、そうなんですね」
さらっと言った『愛する女性にチョコを贈る』というジャックの言葉の意味を、叶子は気付いていないのか『国が違えばイベントの習慣でさえも変わるんですね』と感心している。
察しの悪い彼女にもどかしくなったジャックはとうとう理性を失い、行動に出てしまった。
彼女の口唇にふわんと柔らかい何かが触れる。
「――? ……、――っ!?」
ゆっくりと目を開けてみれば目と鼻の先にジャックの顔があった事に驚き、肘をついた状態で後ろに倒れこむ様にして仰け反った。
完全にパニック状態になっている彼女を余所に、彼女をじっと見つめるジャックの目は先ほどまでの拗ねた子供の様な表情とは全く違い、トロンとしたその目は妙な艶っぽさがあった。
大きな目で何度も瞬きを繰り返す叶子に、ジャックがクスリと笑う。
「ちゃんと言ってなかったね」
「――え? 何、を?」
「僕は君を愛しているって事を。――心の底からね」
「――。」
『愛している』その言葉の持つ意味の重さがズシンと心に響き渡る。
そんな言葉を言われた事は今だかつて一度も無ければ、『好きだ』と言う言葉でさえもさほどない。過去に付き合った事のある数少ない男性達からは、付き合い始める時に一度聞いた切りで、叶子にとっては聞き慣れていないワードの一つだった。
『好き』と言う言葉すら耐性が無いというのに、『愛している』と彼が言う。初めて聞かされたその言葉は彼女に安らぎを与え、同時に彼への想いを加速させていった。
彼に対する気持ちが大きく膨らみはじめていたのを確かに自覚してはいたが、かといって何と答えればいいのか返す言葉が見つからない。叶子はただじっと彼の目を見つめ返す事しか出来なかった。
そうこうしている内にソファーが沈み、彼が手を前について更に彼女に近づいて来ようとしているのが判った。
彼の手が叶子の顔にかかった髪をかき上げる。その手をそのまま首の後ろに回し、肘をつき姿勢が苦しそうな叶子の肩をそっと支えながら二人は口唇を重ね合い、そのままゆっくりとソファーに沈んで行った。
「……っ、……」
幾度も口唇を啄ばんでは笑顔を見せ、彼は短い口付けをもったいぶるかの様に楽しんでいる。
叶子はほんの少しの抵抗を見せてはいるが、繰り返し浴びせられる甘い口づけに完全に虜になってしまっていた。離れた時に魅せる彼女の潤んだ瞳を見ると、今した所なのにすぐにもう一度触れたくなるのか又口唇を寄せてしまう。そんなループをただひたすら繰り返していた。
叶子の下口唇を軽く食みながら少し距離を取った時、寸分の狂いも無い眼差しが叶子に向けられる。
そして、まるで叶子に言い聞かせるように、
「愛しているよ」
と、もう一度そう告げると、より彼女の深い所に潜り込む為に、顔の角度を変えながら貪る様な甘い口づけを交わした。
「……んっ……」
啄ばむ様なキスを繰り返した後にやって来た官能的な刺激に耐え切れず、思わず声が漏れる。角度を変えて彼が距離を狭め優しく叶子の口唇に触れた時、彼の舌が叶子の歯列をなぞりあげた。その事に驚いて僅かに口を開けた瞬間、ここぞとばかりに彼の舌がぬるりと口腔内に侵入を遂げた。
「……あっ、……んっ……」
ソファーに押し倒された格好の叶子の上に彼が覆いかぶさっている。彼の腕を掴み少しの抵抗見せていたその手はいつしか、離れたくないと言わんばかりに彼のシャツを握りしめていた。
(――愛している? 彼が? 私を?)
彼の舌に惑わされながら、先ほどの彼の言葉を反芻していた。
長い手足、大きくてスッとした目元に薄い唇。色素を感じられない程の白い肌が彼を中性的に魅せていて、その容姿は人並み以上、いや人並み外れている。そんな誰もが目を引く容姿もさることながら仕事も出来る彼が女性の扱いも手馴れたものだという事は、ほんの数回会っただけではあったが自ずとわかるものであった。
黙っていても女性が放っておかないであろうそんな人に、突然好きだと言われた事がにわかに信じ難い。
好意をもたれているのではとほんの少し自覚してはいたものの、きっと大勢いる中の一人なのだと思ってきた。誰が見ても超がつくほどのハイスペックな彼が、よりにもよって超がつくほどの凡人である自分を好きになるとは到底思えない。
「カナ、――好きだよ」
「……っ……」
それでも目の前にいる彼が真面目な顔で自分を好きだと何度も告げる。そして、優しく触れられるだけで、もしかすると本当なのかもと錯覚しそうになってしまう。
こんな事は駄目だと思う反面、心のどこかで彼とこうなりたい願望があるのか、彼に抗えない。
幾度となく舌を絡め合う度耳に届く水音で、かあっと叶子の頬が染まった。
彼の指先が頬に触れる。その指先はそのまま髪を梳くようにして流れ、彼の大きな掌は叶子の後頭部を抱え込んだ。その手はやがてうなじへと下降を進めた後、次には顎のラインをツーッとなぞる。貪る様なキスとは逆に触れるか触れないかの距離を保つその指先が、まるで飴と鞭を同時に与えられて焦らされているかの様だった。
「……っ」
顎を伝っていた指先がやがて首筋を辿り始める。ゆっくりと鎖骨に沿う様にして襟を割り、温かい彼の手が左の肩に直に触れた。
柔らかくて温かい、包み込むような彼の大きな手が優しく触れる度に、焦れったい感情が生まれて来る。今、彼に触れられている場所全てが熱を帯び始め、彼だけで無く叶子も又、彼を求めているのだと気付かされた。
ソフトな手の動きとは違い、口腔内を縦横無尽に動き回っている彼の舌を確かに感じる。
角度を変える度に口の隙間から漏れ出す水音と、呼吸を抑えようとする自分のくぐもった声が聴覚を刺激し、もっと、もっとと、高みの方へ連れて行く。
深く甘い口づけを交わす二人には何も阻むものはなかった。
もう彼には振り回されない、そう決めたのにも関わらず目の前の彼に溺れて行った。