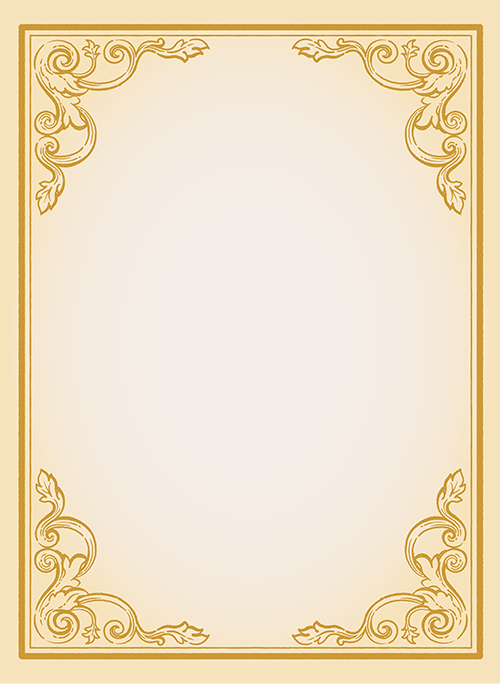カーテンの隙間から柔らかな陽が差し込み、鳥のさえずりが聞こえた事が朝が訪れたのだと告げていた。
けたたましく鳴り響く目覚まし時計に不満をぶつけるかのように、目覚ましを思い切り叩いた。昨夜見た夢を思い出してしまった叶子は上体を起こし、両手で頭を抱え髪をかき乱した。
(今日、……か)
温かいベッドから這い出ると、部屋中のカーテンを開けて腕をぐんと伸ばす。今夜彼に会うまで彼の事は極力考えないようにしよう。そう心に決めると伸ばした腕をパタンと下ろした。
「さ、仕事行くかな」
睡眠不足な頭をリセットさせる為に、無理矢理気持ちを切り替えた。
新調した服、履き慣れないピンヒールに傘とCD。
あの夢と全く同じスタイルだが、彼女は構わず出かけた。
◇◆◇
「社長」
『社長』と呼ばれたその人は、デスクでペンを走らせていた手をピタリと止めると、大きなため息をつきながら俯いていた頭をあげた。
「もう、その呼び方やめてよ」
「でも」
そこは譲れない! とでも言いたげな秘書のジュディスを見て、ジャックは諦めて両手を広げ肩をすくめた。
「で? 今日の予定を教えてくれるかな?」
見晴らしのいいガラス張りのオフィス。座り心地のよさそうな黒革の椅子に深く腰掛け、ジャックは足を組んでいる。窓の方に椅子を回転させ聳(そび)え立つビル群を見つめながら、ため息混じりにそう言った。
「あ、はい。今日は10時から社内ミーティング、12時にリッチホテルにてミスターエマーソンと会食。その後は――」
いつもの朝のお決まりの儀式だが、相変わらずびっしりと組まれているスケジュールに目眩を覚えた。
こんなに毎日働き詰めだとその内、過労死するんじゃないだろうか。肘掛に付いた手で額を覆い大きな溜息を吐いた。
「それが済みましたら、18時に社に戻り本日の業務は終了となります」
「……え? それ以降は?」
いつもは21時頃までびっしりと予定が組み込まれていて、それらのスケジュールをこなしたあと書類に目を通したりしているとあっと言う間に時は過ぎ、帰宅時間は夜中の0時を過ぎるといった毎日なのに、ジュディスの言い方だと18時にはもう帰っていいのだと言っているようにも取れる。
あまりにも理想的なスケジュールにジャックは思わず振り返り、不思議そうに首を傾げた。
まるで先程考えていた事がいつの間にか口に出ていて、気を遣ったジュディスがスケジュールを変更したのかと思ったが、この秘書に限ってそんな温情を見せる筈が無いとジャックは思い改める。
「今日は誰かの誕生日だったっけ?」
「? いいえ?」
訝しげに眉間を寄せた秘書から返された言葉は意外なものだった。
「19時に約束がおありとの事でしたので、スケジューリングしておりませんが?」
「……」
「では、失礼します」
まだ状況が飲み込めていない様子の彼をそのままに、バタンと扉を閉め秘書が退出した。彼は瞬きを忘れ、広いデスクの上に肘をつき手を組みながら考え込む。
(約束……? ───っ!!)
やっとの事で思い出し、彼は勢い良くその場で立ち上がった。
(ああ、そうだ、今日だった……。どうしよう? 何も考えてなかったよ)
落ち着かない彼は顎に手を置き部屋の中を何度も往復した。コートハンガーの横にある鏡に自分が映りこむのが見え、慌てて近づいて何処かおかしい所が無いか全身くまなくチェックしている。
(服は……、これでいいか)
又、部屋の中をウロウロしだすと、今度は突然大きな声を上げた。
「……っ! あーっ! どうしよう! 場所は決めたのにレストラン予約してなかった!!」
慌てて部屋を飛び出し、すぐ側に居る筈の秘書の名前を呼んだ。
「ジュディス! 今日の19時ウェリントンのフレンチ2名で予約して!」
「は、はい、社長」
呼ばれたく無い名称を言われた事に、ジャックの眉根に深く皺が出来る。秘書をじろっと睨んでいる彼を他所に、ジュディスは顔をひきつらせながらその事に触れないように話を進めた。
「あ、えーっと……、お連れ様はお煙草は?」
「あー、……吸わないね」
「かしこまりました。すぐ予約入れておきます」
「宜しく」
ホッと安心したジャックは部屋に戻り、大きなソファーにボスッと腰下ろした。彼のデスクの上にある電話が目に入り、初めて会ったあの日の事やあの後くれた電話での会話を思い出していた。
(初対面であんなに話せた人って初めてだなぁ)
叶子だけでなく彼も又彼女との再会を楽しみにしていて、その事が彼の顔を自然と笑顔にさせた。
「し、社長……?」
ハッとして声がする方を見ると、秘書が変わったものを見るような目で彼を見つめている。思わず彼は両手で顔をこすりながら、ほころんだ顔をどうにか抑えようとした。
「ちょっ、入る時はノック位してよっ!」
「何度もしましたがお返事が無かったので……」
顔を真っ赤にした彼は窓際へと向かい、ジュディスに背を向けて窓の外を見る振りをした。
「で!? 何!?」
「あっ、はい。ウェリントンのフレンチ、19時に2名、禁煙席でお取り出来ました」
「あ、ありがとうっ!」
いつもと違う社長の様子が気になりつつも、ジュディスは扉に手を掛けるとその場を後にした。
そろりと振り返りジュディスが出て行ったのを確認する。フーッと小さく息を吐くと窓ガラスに手を置き、もう一方の手をポケットに突っ込みながら、大きく深呼吸して心を落ち着かせようとした。
遠くの空を眺めると澄み渡る綺麗な青空が広がっていて、まるで今の彼の気持ちを表して居るかのようだ。
――もうすぐ会えるんだ
そんな気持ちが、この同じ空の下(もと)にいる、彼女にもあればいいのに。と、彼は切に願うのだった。
けたたましく鳴り響く目覚まし時計に不満をぶつけるかのように、目覚ましを思い切り叩いた。昨夜見た夢を思い出してしまった叶子は上体を起こし、両手で頭を抱え髪をかき乱した。
(今日、……か)
温かいベッドから這い出ると、部屋中のカーテンを開けて腕をぐんと伸ばす。今夜彼に会うまで彼の事は極力考えないようにしよう。そう心に決めると伸ばした腕をパタンと下ろした。
「さ、仕事行くかな」
睡眠不足な頭をリセットさせる為に、無理矢理気持ちを切り替えた。
新調した服、履き慣れないピンヒールに傘とCD。
あの夢と全く同じスタイルだが、彼女は構わず出かけた。
◇◆◇
「社長」
『社長』と呼ばれたその人は、デスクでペンを走らせていた手をピタリと止めると、大きなため息をつきながら俯いていた頭をあげた。
「もう、その呼び方やめてよ」
「でも」
そこは譲れない! とでも言いたげな秘書のジュディスを見て、ジャックは諦めて両手を広げ肩をすくめた。
「で? 今日の予定を教えてくれるかな?」
見晴らしのいいガラス張りのオフィス。座り心地のよさそうな黒革の椅子に深く腰掛け、ジャックは足を組んでいる。窓の方に椅子を回転させ聳(そび)え立つビル群を見つめながら、ため息混じりにそう言った。
「あ、はい。今日は10時から社内ミーティング、12時にリッチホテルにてミスターエマーソンと会食。その後は――」
いつもの朝のお決まりの儀式だが、相変わらずびっしりと組まれているスケジュールに目眩を覚えた。
こんなに毎日働き詰めだとその内、過労死するんじゃないだろうか。肘掛に付いた手で額を覆い大きな溜息を吐いた。
「それが済みましたら、18時に社に戻り本日の業務は終了となります」
「……え? それ以降は?」
いつもは21時頃までびっしりと予定が組み込まれていて、それらのスケジュールをこなしたあと書類に目を通したりしているとあっと言う間に時は過ぎ、帰宅時間は夜中の0時を過ぎるといった毎日なのに、ジュディスの言い方だと18時にはもう帰っていいのだと言っているようにも取れる。
あまりにも理想的なスケジュールにジャックは思わず振り返り、不思議そうに首を傾げた。
まるで先程考えていた事がいつの間にか口に出ていて、気を遣ったジュディスがスケジュールを変更したのかと思ったが、この秘書に限ってそんな温情を見せる筈が無いとジャックは思い改める。
「今日は誰かの誕生日だったっけ?」
「? いいえ?」
訝しげに眉間を寄せた秘書から返された言葉は意外なものだった。
「19時に約束がおありとの事でしたので、スケジューリングしておりませんが?」
「……」
「では、失礼します」
まだ状況が飲み込めていない様子の彼をそのままに、バタンと扉を閉め秘書が退出した。彼は瞬きを忘れ、広いデスクの上に肘をつき手を組みながら考え込む。
(約束……? ───っ!!)
やっとの事で思い出し、彼は勢い良くその場で立ち上がった。
(ああ、そうだ、今日だった……。どうしよう? 何も考えてなかったよ)
落ち着かない彼は顎に手を置き部屋の中を何度も往復した。コートハンガーの横にある鏡に自分が映りこむのが見え、慌てて近づいて何処かおかしい所が無いか全身くまなくチェックしている。
(服は……、これでいいか)
又、部屋の中をウロウロしだすと、今度は突然大きな声を上げた。
「……っ! あーっ! どうしよう! 場所は決めたのにレストラン予約してなかった!!」
慌てて部屋を飛び出し、すぐ側に居る筈の秘書の名前を呼んだ。
「ジュディス! 今日の19時ウェリントンのフレンチ2名で予約して!」
「は、はい、社長」
呼ばれたく無い名称を言われた事に、ジャックの眉根に深く皺が出来る。秘書をじろっと睨んでいる彼を他所に、ジュディスは顔をひきつらせながらその事に触れないように話を進めた。
「あ、えーっと……、お連れ様はお煙草は?」
「あー、……吸わないね」
「かしこまりました。すぐ予約入れておきます」
「宜しく」
ホッと安心したジャックは部屋に戻り、大きなソファーにボスッと腰下ろした。彼のデスクの上にある電話が目に入り、初めて会ったあの日の事やあの後くれた電話での会話を思い出していた。
(初対面であんなに話せた人って初めてだなぁ)
叶子だけでなく彼も又彼女との再会を楽しみにしていて、その事が彼の顔を自然と笑顔にさせた。
「し、社長……?」
ハッとして声がする方を見ると、秘書が変わったものを見るような目で彼を見つめている。思わず彼は両手で顔をこすりながら、ほころんだ顔をどうにか抑えようとした。
「ちょっ、入る時はノック位してよっ!」
「何度もしましたがお返事が無かったので……」
顔を真っ赤にした彼は窓際へと向かい、ジュディスに背を向けて窓の外を見る振りをした。
「で!? 何!?」
「あっ、はい。ウェリントンのフレンチ、19時に2名、禁煙席でお取り出来ました」
「あ、ありがとうっ!」
いつもと違う社長の様子が気になりつつも、ジュディスは扉に手を掛けるとその場を後にした。
そろりと振り返りジュディスが出て行ったのを確認する。フーッと小さく息を吐くと窓ガラスに手を置き、もう一方の手をポケットに突っ込みながら、大きく深呼吸して心を落ち着かせようとした。
遠くの空を眺めると澄み渡る綺麗な青空が広がっていて、まるで今の彼の気持ちを表して居るかのようだ。
――もうすぐ会えるんだ
そんな気持ちが、この同じ空の下(もと)にいる、彼女にもあればいいのに。と、彼は切に願うのだった。