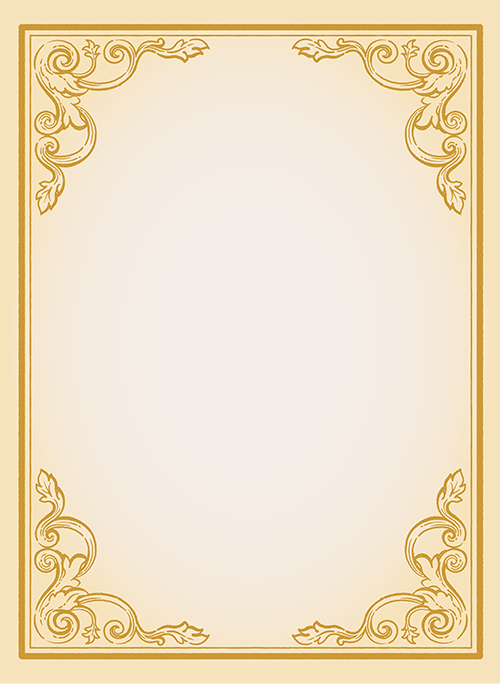大画面で見る映画の迫力にいつしか飲み込まれ、彼が横に居る事も、今彼の部屋に居るという事も忘れ、映画の世界に入り込んでしまっていた。
エンドロールが終わってその事に気付くと、映画の余韻に浸ったまま隣に座るジャックに目を向ける。
「……?」
彼女の目の高さまで上げられた彼の両手は、何かを掬うような形を作って掌を上に向けている。
キョトンとしている叶子にどこか嬉しそうな表情をしたジャックは、叶子が自分の手に注目しているのを確認し、広げた手の平をもう一方の手でくるりと覆うと再度両方の手の平を上に向けるようにして見せた。すると、先ほどまでは何もなかった彼のその大きな手の上に、金色のリボンがかかった小さな黒い箱が突如現れ出た。
「……わあ! 凄い!」
みるみる明るくなる叶子の表情に、ジャックはとても満足している様子であった。
「どうやったの?」
突然見せられた手品に興奮したのか、ジャックに対していつもは敬語で話していたのが思わずタメ口になっているのにも気付いていない。彼の手を上から見たり下を覗き込んだりと、どうやってやったのか必死で暴こうとしていた。すると、頭上から『はぁーっ』と大きな溜息と共に、切なそうな声が聞こえてきた。
「そこなの?」
「え?」
肩透かしをくらったと言わんばかりの表情でそう言った。一体、何故そんな風に言うのかを叶子は落ち着いて考えてみた。
「……あ、コレ?」
掌に乗った小さな箱を指差した。
「そ」
「コレ、さっき隣の部屋にあったチョコじゃないんですか?」
「違うよ」
「え? じゃあ??」
何が言いたいのかさっぱりわからず、首を傾げながらジャックを見た。そんな叶子の様子に業を煮やしたのか、ジャックは彼女の手を取るとその小さな箱を手の上に置いた。
まだ事の自体を把握してない叶子に、『開けて見て』と促した。
「え? あ? 私に??」
幾分拍子抜けしたような彼の様子が見てとれる。コクコクと彼が頷いて初めて、自分へのプレゼントなのだということに気が付いた。
何が入ってるんだろうかとドキドキしながら言われた通りに金色のリボンをスルスルと解き始める。
「――ん? やっぱりチョコ??」
「うん」
箱の中身は形がバラバラなチョコレートが4つ。
彼は少し照れているのか、瞬きの回数が格段に増えているのが判った。
食べろという仕草をジャックがするので、叶子はその歪(いびつ)な形のチョコを一個口に放り込んだ。
途端、片頬を膨らませながら眉間にしわを寄せた叶子の顔からして、お世辞にも美味しいものを食べている時にする表情ではない事は、誰が見ても一目瞭然だった。
「あ、おいしくない?」
「か、かたひ」
「あ、やっぱり?」
「形もなんだか変わってるし、これ一体どこで買ったんですか?」
「……。」
「??」
一瞬、むっとした顔になったかと思うと、何も言わず残りのチョコを叶子の手から取り上げ、背中の後ろに隠してしまった。
「あっ」
自分は何も用意していなかったのだから、偉そうに批評できる立場では無いはず。例え不味かったとしても顔に出す事は愚か、口に出すなんてもってのほかだ。
せっかく自分の為に用意してくれたというのに、調子に乗って口を滑らせ気を悪くさせてしまった。気遣いの感じられない無い自分の言動に激しく後悔した。
いつもおいしい食事をチョイスするジャックだったから何か理由でもあるのかという思いもあり、そんな言葉を口走ってしまった。
とにかく、何とか臍を曲げてしまったジャックのご機嫌を取ろうと、思った事を率直に言うことにした。
「あ、味はおいしいですよ!」
「……又、嘘吐いてる」
「嘘じゃないですって!」
「そりゃぁ、――材料自体はグレースが選んだいいものを使ってるから、下手でもそれなりにおいしいかもしれないけどね」
ジャックが何故ここまで拗ねているのかと考えあぐねる。部屋が暗くて少し判りにくいものの、ジャックの顔が心なしか赤くなっている様な気がした。
『グレースが用意した材料』『下手でもそれなり』先ほど、彼の言ったセリフをもう一度じっくり考えてみる。
「……、――っ!? ま、まさかコレ、貴方が作ったとか??」
「……。」
背中に箱を隠しながら顔を背け口を尖らせている彼の態度を見ると、やはりこれは彼が作ったのだと確信した。
(うぇ~!! 嘘!? か、彼がチョコを……! 四十六歳のバリバリ働くやり手社長が、キッチンでテンパリングとかしちゃったの!? ……エ、エプロンとかするのかなっ? ああっ、でもなんだか私より良く似合ってそうで嫉妬する!)
確信した後、頭の中が一気に騒がしくなった。慌てふためいてまともな思考が出来なくなっている。
妄想を一通り終えた後、それよりも何よりも何かいい言い訳をしなければと考えたがいい言葉が浮かばない。もし、自分が人にチョコを作ってあげて、あんな微妙な事言われたら傷つきすぎてきっと立ち直れない。
「あ、あのー。もう1個食べたいなぁー?」
何て言えばこの場を切り抜けられるかと足りない頭で必死で考えたものの、こんな台詞しか思い浮かばなかった。上目遣いで彼にお願いするが、完全に拗ねてしまった彼は顔をフンッと逸らしたまま、箱を渡す気配は全く無いようだ。
もう、こうなったら実力行使に出るしかないと、叶子は賭けに出た。
「……あっ! あのCD、私も持ってるかもー?」
ジャックの後ろにあるデスクを指差し、彼の気を逸らそうとした。完全な棒読みだったと言うのに、彼はそれに釣られて後ろを振り返る。
「ん? どれ? ……、――あ! こら!」
身体を捻った事で後ろ手に持ったチョコレートの箱の姿が見えた。油断しているその隙を狙って、そーっとジャックの手にある箱を奪おうと試みるが、すぐにそれもばれてしまった。ジャックは腕のリーチの長さを生かし、上に上げたり後方にぐんと離したりと、決して叶子に取られまいと抵抗した。
「もう! ダメだってば!」
「いいじゃない! それ私にくれたものでしょ?」
ジャックと叶子は、まるで小さな子供が無邪気にじゃれあっているかの様にソファーの上でその小さな箱の争奪戦を始めた。
そして、気付かぬうちにどんどん二人の距離が狭まって行った。
「もう、わかった! わかったから!」
とうとうジャックは観念し、後ろに隠した小さな箱を差し出した。勝ち誇った様な顔で叶子はその箱を受け取り一粒口に放り込むと、すぐにもう一つ手に取って彼の顔の前にそれを近づけた。
「はい、あーん」
「――。」
目の前に出されたチョコを見て、そのまま指伝いにその先にいる叶子に視線を向けた。嬉しそうにしてほほ笑む顔を見ると思わず口元が緩む。
仕方なく開けた口に叶子がチョコを放り込む。ジャックの口唇にほんの少しだけ彼女の指が触れた。それに気付いているのかどうなのかは判らないが、満足気に笑みを浮かべ自身の指についたチョコを彼の目を見つめながらペロリと舐めた。
その仕草に、叶子に対して今までに無い色気を感じ、ドキッと胸が一段と大きな音を立てた。
……が、そんな気分に浸る間もなく、すぐにジャックの眉間にも皺が刻まれることとなった。
「ほんとだ、かたっ」
「でしょ? でも、おいしいですよね」
「うん、味は……まともかな」
「生クリーム足すとかしたら柔らかくなっていいですよ」
「へーそうなの? 良く知ってるね」
「まぁ、こんな私でもチョコレート位作った事はありますから」
「ふぅ、ん」
その言葉を聞いてチクンと胸の奥が痛んだ。たったこれしきの事で、自分の知らない彼女の過去の相手に嫉妬しているのだと気付く。
彼女にだって過去に恋愛の一つや二つくらいあるだろう。相手を想うがあまり眠れない夜を過ごしたこともきっと――。自分にもそんな過去があるのと同じく彼女にもあったのだろうと無論判ってはいたが、持って行き場の無い思いがぐるぐると感情の渦を巻いた。
「あ、さっきの手品。もう一回やって下さい」
きっと、話の流れで何気なく言っただけであろう。ジャックの今の思いに全く気付いていない様子だった。きょろきょろと周囲を見回しテーブルの上にあったリモコンに手を伸ばすと、ジャックの手を取りそれを乗せた。
「さすがにこれは大きすぎて無理だよ。掌に隠れる位の大きさで無いと」
まるで子供の様な彼女に、ジャックは苦笑いを浮かべている。眉間に皺を寄せた叶子は仕方なく、もう一度チョコの入った箱をジャックの手の上に乗せた。
ワクワクした顔で彼の手にグッと近づき至近距離でその魔法を見破ろうとしている。こんな事で喜んでくれた事にジャックは驚き、そして嬉しかった。
「仕込んでからでないとできないよ」
「そうなんですか?」
「そりゃそうさ、ちゃんとタネがあるんだから。ほら、目を瞑って」
「はーい」
膝の上にちょこんと両手を揃えて置くと、言われた通りに目を瞑りながらニコニコとあどけない表情をしている叶子がいとおしくてたまらない。彼女が居るだけで自然と笑顔になれる、そんな気がした。
「まだだよ。ちゃんと目、瞑ってる? 薄目したらもうやらないよ?」
「大丈夫、ちゃんと瞑ってますよー」
「……。」
タネを仕込みながら目を瞑っているのをいい事に、無防備な彼女をじっと見つめた。
長い睫に小ぶりな鼻、ぷっくりとした口唇に、笑うとキュッと細くなる顎。細くて白い首筋やはっきりと浮き出た鎖骨には、細いチェーンのネックレスが引っかかっている。いつかそこに顔を埋めたいと思わず心の中で本音が漏れる。
「――まだですか?」
「う、うん。まだだよ」
急に声を発したのに驚いて、ジャックの声が思わず裏返った。
明るい声で話す彼女に対してなんて卑猥な事を考えてるんだと、後ろめたさで一杯になる。それでも視線を逸らす事が出来ない。逸らすどころか、その視線を徐々に下げていった。
着ているシャツに明らかに余裕のある二の腕と、その割りに窮屈そうにしている胸元に初めて気付き、思わず喉を鳴らしてしまう。キュッとくびれた腰にぶら下がったものは、腰の細さとは反比例して女性らしい丸みを帯びていて何とも扇情的な気分にさせられる。膝まであるタイトなスカートから伸びた足はスラッとしていて、程よい筋肉で引き締まっているのが伺えた。
二十代だと見紛うほどの童顔な顔立ちからは想像出来ない、三十三歳の大人の女性の身体をしている彼女に、まるで脳天を打ち抜かれた様な気持ちにさせられた。
「――。」
先ほど繰り広げられた争奪戦により、二人の距離はぐっと近くなっている。
少し腕を伸ばせばいとも簡単に抱き締められる距離に彼女が居る事に、今更ながら緊張感が走った。腕の中に閉じ込めてしまいたいという本音と、そんな事をしてしまえばせっかくここまで打ち解けてくれたのに、全てが水の泡になると言う理性とが激しくぶつかり合う。二つの感情で葛藤し、頭が混乱した。
(もう、無理……、かもしれない)
徐々に理性を失いつつあるジャックは、とうとう目の前にいる彼女を自分のものにしたいという願望に打ち勝つ事が出来なくなった。
エンドロールが終わってその事に気付くと、映画の余韻に浸ったまま隣に座るジャックに目を向ける。
「……?」
彼女の目の高さまで上げられた彼の両手は、何かを掬うような形を作って掌を上に向けている。
キョトンとしている叶子にどこか嬉しそうな表情をしたジャックは、叶子が自分の手に注目しているのを確認し、広げた手の平をもう一方の手でくるりと覆うと再度両方の手の平を上に向けるようにして見せた。すると、先ほどまでは何もなかった彼のその大きな手の上に、金色のリボンがかかった小さな黒い箱が突如現れ出た。
「……わあ! 凄い!」
みるみる明るくなる叶子の表情に、ジャックはとても満足している様子であった。
「どうやったの?」
突然見せられた手品に興奮したのか、ジャックに対していつもは敬語で話していたのが思わずタメ口になっているのにも気付いていない。彼の手を上から見たり下を覗き込んだりと、どうやってやったのか必死で暴こうとしていた。すると、頭上から『はぁーっ』と大きな溜息と共に、切なそうな声が聞こえてきた。
「そこなの?」
「え?」
肩透かしをくらったと言わんばかりの表情でそう言った。一体、何故そんな風に言うのかを叶子は落ち着いて考えてみた。
「……あ、コレ?」
掌に乗った小さな箱を指差した。
「そ」
「コレ、さっき隣の部屋にあったチョコじゃないんですか?」
「違うよ」
「え? じゃあ??」
何が言いたいのかさっぱりわからず、首を傾げながらジャックを見た。そんな叶子の様子に業を煮やしたのか、ジャックは彼女の手を取るとその小さな箱を手の上に置いた。
まだ事の自体を把握してない叶子に、『開けて見て』と促した。
「え? あ? 私に??」
幾分拍子抜けしたような彼の様子が見てとれる。コクコクと彼が頷いて初めて、自分へのプレゼントなのだということに気が付いた。
何が入ってるんだろうかとドキドキしながら言われた通りに金色のリボンをスルスルと解き始める。
「――ん? やっぱりチョコ??」
「うん」
箱の中身は形がバラバラなチョコレートが4つ。
彼は少し照れているのか、瞬きの回数が格段に増えているのが判った。
食べろという仕草をジャックがするので、叶子はその歪(いびつ)な形のチョコを一個口に放り込んだ。
途端、片頬を膨らませながら眉間にしわを寄せた叶子の顔からして、お世辞にも美味しいものを食べている時にする表情ではない事は、誰が見ても一目瞭然だった。
「あ、おいしくない?」
「か、かたひ」
「あ、やっぱり?」
「形もなんだか変わってるし、これ一体どこで買ったんですか?」
「……。」
「??」
一瞬、むっとした顔になったかと思うと、何も言わず残りのチョコを叶子の手から取り上げ、背中の後ろに隠してしまった。
「あっ」
自分は何も用意していなかったのだから、偉そうに批評できる立場では無いはず。例え不味かったとしても顔に出す事は愚か、口に出すなんてもってのほかだ。
せっかく自分の為に用意してくれたというのに、調子に乗って口を滑らせ気を悪くさせてしまった。気遣いの感じられない無い自分の言動に激しく後悔した。
いつもおいしい食事をチョイスするジャックだったから何か理由でもあるのかという思いもあり、そんな言葉を口走ってしまった。
とにかく、何とか臍を曲げてしまったジャックのご機嫌を取ろうと、思った事を率直に言うことにした。
「あ、味はおいしいですよ!」
「……又、嘘吐いてる」
「嘘じゃないですって!」
「そりゃぁ、――材料自体はグレースが選んだいいものを使ってるから、下手でもそれなりにおいしいかもしれないけどね」
ジャックが何故ここまで拗ねているのかと考えあぐねる。部屋が暗くて少し判りにくいものの、ジャックの顔が心なしか赤くなっている様な気がした。
『グレースが用意した材料』『下手でもそれなり』先ほど、彼の言ったセリフをもう一度じっくり考えてみる。
「……、――っ!? ま、まさかコレ、貴方が作ったとか??」
「……。」
背中に箱を隠しながら顔を背け口を尖らせている彼の態度を見ると、やはりこれは彼が作ったのだと確信した。
(うぇ~!! 嘘!? か、彼がチョコを……! 四十六歳のバリバリ働くやり手社長が、キッチンでテンパリングとかしちゃったの!? ……エ、エプロンとかするのかなっ? ああっ、でもなんだか私より良く似合ってそうで嫉妬する!)
確信した後、頭の中が一気に騒がしくなった。慌てふためいてまともな思考が出来なくなっている。
妄想を一通り終えた後、それよりも何よりも何かいい言い訳をしなければと考えたがいい言葉が浮かばない。もし、自分が人にチョコを作ってあげて、あんな微妙な事言われたら傷つきすぎてきっと立ち直れない。
「あ、あのー。もう1個食べたいなぁー?」
何て言えばこの場を切り抜けられるかと足りない頭で必死で考えたものの、こんな台詞しか思い浮かばなかった。上目遣いで彼にお願いするが、完全に拗ねてしまった彼は顔をフンッと逸らしたまま、箱を渡す気配は全く無いようだ。
もう、こうなったら実力行使に出るしかないと、叶子は賭けに出た。
「……あっ! あのCD、私も持ってるかもー?」
ジャックの後ろにあるデスクを指差し、彼の気を逸らそうとした。完全な棒読みだったと言うのに、彼はそれに釣られて後ろを振り返る。
「ん? どれ? ……、――あ! こら!」
身体を捻った事で後ろ手に持ったチョコレートの箱の姿が見えた。油断しているその隙を狙って、そーっとジャックの手にある箱を奪おうと試みるが、すぐにそれもばれてしまった。ジャックは腕のリーチの長さを生かし、上に上げたり後方にぐんと離したりと、決して叶子に取られまいと抵抗した。
「もう! ダメだってば!」
「いいじゃない! それ私にくれたものでしょ?」
ジャックと叶子は、まるで小さな子供が無邪気にじゃれあっているかの様にソファーの上でその小さな箱の争奪戦を始めた。
そして、気付かぬうちにどんどん二人の距離が狭まって行った。
「もう、わかった! わかったから!」
とうとうジャックは観念し、後ろに隠した小さな箱を差し出した。勝ち誇った様な顔で叶子はその箱を受け取り一粒口に放り込むと、すぐにもう一つ手に取って彼の顔の前にそれを近づけた。
「はい、あーん」
「――。」
目の前に出されたチョコを見て、そのまま指伝いにその先にいる叶子に視線を向けた。嬉しそうにしてほほ笑む顔を見ると思わず口元が緩む。
仕方なく開けた口に叶子がチョコを放り込む。ジャックの口唇にほんの少しだけ彼女の指が触れた。それに気付いているのかどうなのかは判らないが、満足気に笑みを浮かべ自身の指についたチョコを彼の目を見つめながらペロリと舐めた。
その仕草に、叶子に対して今までに無い色気を感じ、ドキッと胸が一段と大きな音を立てた。
……が、そんな気分に浸る間もなく、すぐにジャックの眉間にも皺が刻まれることとなった。
「ほんとだ、かたっ」
「でしょ? でも、おいしいですよね」
「うん、味は……まともかな」
「生クリーム足すとかしたら柔らかくなっていいですよ」
「へーそうなの? 良く知ってるね」
「まぁ、こんな私でもチョコレート位作った事はありますから」
「ふぅ、ん」
その言葉を聞いてチクンと胸の奥が痛んだ。たったこれしきの事で、自分の知らない彼女の過去の相手に嫉妬しているのだと気付く。
彼女にだって過去に恋愛の一つや二つくらいあるだろう。相手を想うがあまり眠れない夜を過ごしたこともきっと――。自分にもそんな過去があるのと同じく彼女にもあったのだろうと無論判ってはいたが、持って行き場の無い思いがぐるぐると感情の渦を巻いた。
「あ、さっきの手品。もう一回やって下さい」
きっと、話の流れで何気なく言っただけであろう。ジャックの今の思いに全く気付いていない様子だった。きょろきょろと周囲を見回しテーブルの上にあったリモコンに手を伸ばすと、ジャックの手を取りそれを乗せた。
「さすがにこれは大きすぎて無理だよ。掌に隠れる位の大きさで無いと」
まるで子供の様な彼女に、ジャックは苦笑いを浮かべている。眉間に皺を寄せた叶子は仕方なく、もう一度チョコの入った箱をジャックの手の上に乗せた。
ワクワクした顔で彼の手にグッと近づき至近距離でその魔法を見破ろうとしている。こんな事で喜んでくれた事にジャックは驚き、そして嬉しかった。
「仕込んでからでないとできないよ」
「そうなんですか?」
「そりゃそうさ、ちゃんとタネがあるんだから。ほら、目を瞑って」
「はーい」
膝の上にちょこんと両手を揃えて置くと、言われた通りに目を瞑りながらニコニコとあどけない表情をしている叶子がいとおしくてたまらない。彼女が居るだけで自然と笑顔になれる、そんな気がした。
「まだだよ。ちゃんと目、瞑ってる? 薄目したらもうやらないよ?」
「大丈夫、ちゃんと瞑ってますよー」
「……。」
タネを仕込みながら目を瞑っているのをいい事に、無防備な彼女をじっと見つめた。
長い睫に小ぶりな鼻、ぷっくりとした口唇に、笑うとキュッと細くなる顎。細くて白い首筋やはっきりと浮き出た鎖骨には、細いチェーンのネックレスが引っかかっている。いつかそこに顔を埋めたいと思わず心の中で本音が漏れる。
「――まだですか?」
「う、うん。まだだよ」
急に声を発したのに驚いて、ジャックの声が思わず裏返った。
明るい声で話す彼女に対してなんて卑猥な事を考えてるんだと、後ろめたさで一杯になる。それでも視線を逸らす事が出来ない。逸らすどころか、その視線を徐々に下げていった。
着ているシャツに明らかに余裕のある二の腕と、その割りに窮屈そうにしている胸元に初めて気付き、思わず喉を鳴らしてしまう。キュッとくびれた腰にぶら下がったものは、腰の細さとは反比例して女性らしい丸みを帯びていて何とも扇情的な気分にさせられる。膝まであるタイトなスカートから伸びた足はスラッとしていて、程よい筋肉で引き締まっているのが伺えた。
二十代だと見紛うほどの童顔な顔立ちからは想像出来ない、三十三歳の大人の女性の身体をしている彼女に、まるで脳天を打ち抜かれた様な気持ちにさせられた。
「――。」
先ほど繰り広げられた争奪戦により、二人の距離はぐっと近くなっている。
少し腕を伸ばせばいとも簡単に抱き締められる距離に彼女が居る事に、今更ながら緊張感が走った。腕の中に閉じ込めてしまいたいという本音と、そんな事をしてしまえばせっかくここまで打ち解けてくれたのに、全てが水の泡になると言う理性とが激しくぶつかり合う。二つの感情で葛藤し、頭が混乱した。
(もう、無理……、かもしれない)
徐々に理性を失いつつあるジャックは、とうとう目の前にいる彼女を自分のものにしたいという願望に打ち勝つ事が出来なくなった。