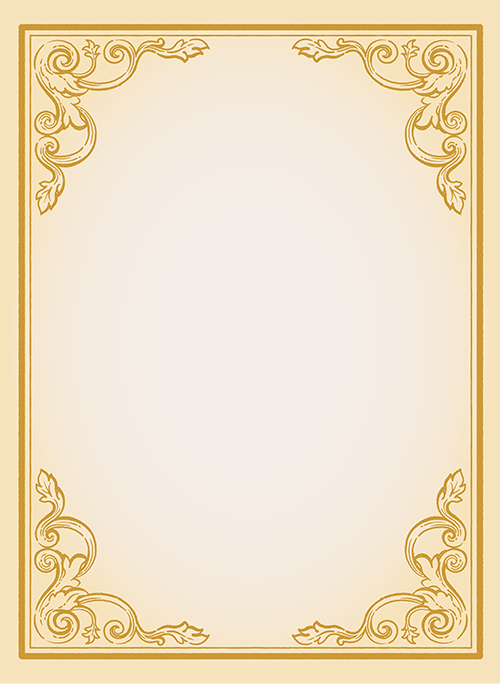「それでね」
リビングの扉を開ける直前、彼が叶子の方を振り返りながら開け放たれた扉の向こうに見えた光景に思わず絶句する。叶子のその顔を見た彼はドアに手を掛けたまま、リビングに視線を戻せば、テーブルやソファーは勿論。部屋の至る所に、大小さまざまなプレゼントらしき物が所狭しと置いてあって、ジャックも彼女と同じように目を丸くした。
「凄い! もしかしてこれ全部チョコですか?」
「ん、ああ、多分……そう」
タイミングの悪さにがっくりしているのか、彼は頭を掻きながら『はぁ~っ』と特大の溜息を吐いた。
「もう、これじゃあ話をする所かゆっくり座れもしない」
家に仕えるスタッフからは勿論、仕事関係の女性からも沢山届けられていたようで、その数は年々増えている。
座る所を確保しようとソファーの上に置いてある物から片付け始めるが、数が多すぎて拉致があかなかった。
「ダメだ、隣の部屋に移ろう」
そう言って、彼が親指で指し示した方を見ると、以前来た時には気付かなかったがリビングの奥に1枚の扉があった。言われるがまま、彼の後について隣の部屋に入ると、どうやらそこは彼のプライベートスペースのようだった。
プライベートスペースと言ってもとても広いその部屋は変な緊張感が生み出されそうな感じは一切なく、大きな本棚に囲まれたデスク。小さなバーカウンターと、大人の男性が一人寝そべっても、足がはみ出る事がなさそうな黒い革張りのソファー。そして、その前には大きなテレビが物凄い存在感をかもし出していた。
部屋の隅に目をやると、そこにはブラインドの奥に大きなベッドがチラリと顔を出しているのが見える。
「座って。ちょっと散らかってるけど」
相変わらずのスケールの大きさに呆気に取られ、思わずキョロキョロと部屋の中を見回していると、彼がネクタイを緩めながらちょんちょんとソファーを指差した。
ジャケットを脱いでそれをデスクの椅子に雑に放り投げる。あちらこちらに乱雑に積み重ねてあるCDを拾い上げては、デスクの後ろのラックに片付けだした。
ソファーの中央に彼女が腰を降ろし、それを見た彼が遠くからリモコンを操作してテレビの電源が入れられた。突然大きな音量で映画が映し出され、体が一瞬浮いてしまうほどビクッとした。
「ああ、ごめん音量下げるの忘れてた」
CDの束を片手で何枚も掴みながら、急いで音量を下げていく。
「い、いつもこんな大きな音で聞いてるんですか?」
「うん、迫力あるからね」
「ああ、確かにこんなおっきなテレビで見ると気持ちいいでしょうね。これって一体何インチですか?」
「え~っと、確かこれは103インチだったかな?」
「すごっ……」
「このテレビで出来上がったばっかりのミュージックビデオとか見ると、粗が良く判ってチェックするのに丁度いいんだ」
「なるほど……」
“仕事で使ってるんだ”と、この会話でも彼の仕事に対する情熱を感じさせられた。
「奥のベッドルームのはプロジェクターだけどもうちょっと大きくて、120インチ位あったはず」
「へー! まるで映画館じゃないですか!」
「めったにないけど休みの前の夜にベッドで寝転びながら映画を見ると凄く幸せになれるんだよ」
『そんな事で幸せを感じてしまえる僕は、本当に幸せな人間なのかもね』CDのジャケットの表と裏を返しながら、彼はそう言って眉を下げた。
「ちょっと片付けてる間これでも見てて」
リモコンを彼女に渡すついでにソファーの前のテーブルに散乱している書類を引っ掴むと、又デスクへと戻って行った。
画面に映し出されていたものは、彼が何日か前に途中まで見た映画だそうだ。内心、途中から見るのもどうかと思い、最初から見るためにリモコンに手を伸ばした手をすぐに引っ込めた。
きっとリモコンを渡されたイコール好きに見ていいよ、って事なんだろうが、既に途中まで見てしまっている彼に申し訳なく思い、純粋に映画を楽しむ事は諦めそのまま途中から見る事にした。
しかしその大画面の迫力たるや否や本当に凄まじく、途中から見ているというのにあっさりと映画の世界に引きずり込まれてしまった。
「――。」
画面に釘付けになっている叶子を横目で見るとジャックはクスリと微笑んだ。
◇◆◇
しばらくするとソファーが沈むのを感じた。どうやら片付けを終えたのか、叶子の方に体を向ける様にしてソファーの端に座っていた。
首にしていたネクタイも既に無く、シャツのボタンも2、3個外されている。その隙間から男らしい喉仏が垣間見え、トクンと心臓が跳ねても気付かない振りをした。
そしていつの間に淹れたのか、マグに入ったミルクティーを手渡される。言わずとも望みのものを与えてくれる彼に、おのずと安心感が生まれてくるのが判った。
「ありがとうございます」
そう言うと又、すぐに視線を画面に戻し再び映画に集中し始めた。
カチッと何か音がしたかと思うと、突然オレンジ色の光が現われた。その光がテーブルに置いてあるキャンドルに火を点し彼が部屋の電気を消した。
「?」
「この方がもっと楽しめるよ」
急に部屋が暗くなった事で、天井を見上げている叶子にそう言った。叶子は『なんだか映画館に来たみたい!』とはしゃいでいる。確かに、こうした方がより映画を楽しめるからと思ってやった事には違いないが、薄暗い方が微妙な表情の変化がわかりにくく、自分にとってその方が都合がいいというのもあった。
成り行きでそうなったとは言え、自分の部屋に彼女がいる。
そう思うだけで、勝手に顔が紅潮していくのが自分でもよく判った。
彼女は両手でマグを握り締めながら楽しい場面では笑顔になり、悲しい場面では目に一杯涙を浮かべている。ジャックは一緒に映画を見る振りをして彼女の横顔を盗み見し、コロコロ変わる叶子の表情を見ては心が自然に癒される様な気分にさせられた。
映画が終わりエンドロールが流れ始めても、叶子はまだ画面に釘付けになっている。
映画が終わった時、叶子がジャックの方を向けばそれを合図にある事を実行しようと考えていた事があった。
いつもより少し早く音を立てる胸の音が、否が応にも彼を煽り立てている。
緊張が最高潮にまで登りつめた時、薄暗かった部屋がより一層暗くなった。画面が真っ暗になった事がエンドロールも終った事を表している。そして、とうとうその時はやって来た。
リビングの扉を開ける直前、彼が叶子の方を振り返りながら開け放たれた扉の向こうに見えた光景に思わず絶句する。叶子のその顔を見た彼はドアに手を掛けたまま、リビングに視線を戻せば、テーブルやソファーは勿論。部屋の至る所に、大小さまざまなプレゼントらしき物が所狭しと置いてあって、ジャックも彼女と同じように目を丸くした。
「凄い! もしかしてこれ全部チョコですか?」
「ん、ああ、多分……そう」
タイミングの悪さにがっくりしているのか、彼は頭を掻きながら『はぁ~っ』と特大の溜息を吐いた。
「もう、これじゃあ話をする所かゆっくり座れもしない」
家に仕えるスタッフからは勿論、仕事関係の女性からも沢山届けられていたようで、その数は年々増えている。
座る所を確保しようとソファーの上に置いてある物から片付け始めるが、数が多すぎて拉致があかなかった。
「ダメだ、隣の部屋に移ろう」
そう言って、彼が親指で指し示した方を見ると、以前来た時には気付かなかったがリビングの奥に1枚の扉があった。言われるがまま、彼の後について隣の部屋に入ると、どうやらそこは彼のプライベートスペースのようだった。
プライベートスペースと言ってもとても広いその部屋は変な緊張感が生み出されそうな感じは一切なく、大きな本棚に囲まれたデスク。小さなバーカウンターと、大人の男性が一人寝そべっても、足がはみ出る事がなさそうな黒い革張りのソファー。そして、その前には大きなテレビが物凄い存在感をかもし出していた。
部屋の隅に目をやると、そこにはブラインドの奥に大きなベッドがチラリと顔を出しているのが見える。
「座って。ちょっと散らかってるけど」
相変わらずのスケールの大きさに呆気に取られ、思わずキョロキョロと部屋の中を見回していると、彼がネクタイを緩めながらちょんちょんとソファーを指差した。
ジャケットを脱いでそれをデスクの椅子に雑に放り投げる。あちらこちらに乱雑に積み重ねてあるCDを拾い上げては、デスクの後ろのラックに片付けだした。
ソファーの中央に彼女が腰を降ろし、それを見た彼が遠くからリモコンを操作してテレビの電源が入れられた。突然大きな音量で映画が映し出され、体が一瞬浮いてしまうほどビクッとした。
「ああ、ごめん音量下げるの忘れてた」
CDの束を片手で何枚も掴みながら、急いで音量を下げていく。
「い、いつもこんな大きな音で聞いてるんですか?」
「うん、迫力あるからね」
「ああ、確かにこんなおっきなテレビで見ると気持ちいいでしょうね。これって一体何インチですか?」
「え~っと、確かこれは103インチだったかな?」
「すごっ……」
「このテレビで出来上がったばっかりのミュージックビデオとか見ると、粗が良く判ってチェックするのに丁度いいんだ」
「なるほど……」
“仕事で使ってるんだ”と、この会話でも彼の仕事に対する情熱を感じさせられた。
「奥のベッドルームのはプロジェクターだけどもうちょっと大きくて、120インチ位あったはず」
「へー! まるで映画館じゃないですか!」
「めったにないけど休みの前の夜にベッドで寝転びながら映画を見ると凄く幸せになれるんだよ」
『そんな事で幸せを感じてしまえる僕は、本当に幸せな人間なのかもね』CDのジャケットの表と裏を返しながら、彼はそう言って眉を下げた。
「ちょっと片付けてる間これでも見てて」
リモコンを彼女に渡すついでにソファーの前のテーブルに散乱している書類を引っ掴むと、又デスクへと戻って行った。
画面に映し出されていたものは、彼が何日か前に途中まで見た映画だそうだ。内心、途中から見るのもどうかと思い、最初から見るためにリモコンに手を伸ばした手をすぐに引っ込めた。
きっとリモコンを渡されたイコール好きに見ていいよ、って事なんだろうが、既に途中まで見てしまっている彼に申し訳なく思い、純粋に映画を楽しむ事は諦めそのまま途中から見る事にした。
しかしその大画面の迫力たるや否や本当に凄まじく、途中から見ているというのにあっさりと映画の世界に引きずり込まれてしまった。
「――。」
画面に釘付けになっている叶子を横目で見るとジャックはクスリと微笑んだ。
◇◆◇
しばらくするとソファーが沈むのを感じた。どうやら片付けを終えたのか、叶子の方に体を向ける様にしてソファーの端に座っていた。
首にしていたネクタイも既に無く、シャツのボタンも2、3個外されている。その隙間から男らしい喉仏が垣間見え、トクンと心臓が跳ねても気付かない振りをした。
そしていつの間に淹れたのか、マグに入ったミルクティーを手渡される。言わずとも望みのものを与えてくれる彼に、おのずと安心感が生まれてくるのが判った。
「ありがとうございます」
そう言うと又、すぐに視線を画面に戻し再び映画に集中し始めた。
カチッと何か音がしたかと思うと、突然オレンジ色の光が現われた。その光がテーブルに置いてあるキャンドルに火を点し彼が部屋の電気を消した。
「?」
「この方がもっと楽しめるよ」
急に部屋が暗くなった事で、天井を見上げている叶子にそう言った。叶子は『なんだか映画館に来たみたい!』とはしゃいでいる。確かに、こうした方がより映画を楽しめるからと思ってやった事には違いないが、薄暗い方が微妙な表情の変化がわかりにくく、自分にとってその方が都合がいいというのもあった。
成り行きでそうなったとは言え、自分の部屋に彼女がいる。
そう思うだけで、勝手に顔が紅潮していくのが自分でもよく判った。
彼女は両手でマグを握り締めながら楽しい場面では笑顔になり、悲しい場面では目に一杯涙を浮かべている。ジャックは一緒に映画を見る振りをして彼女の横顔を盗み見し、コロコロ変わる叶子の表情を見ては心が自然に癒される様な気分にさせられた。
映画が終わりエンドロールが流れ始めても、叶子はまだ画面に釘付けになっている。
映画が終わった時、叶子がジャックの方を向けばそれを合図にある事を実行しようと考えていた事があった。
いつもより少し早く音を立てる胸の音が、否が応にも彼を煽り立てている。
緊張が最高潮にまで登りつめた時、薄暗かった部屋がより一層暗くなった。画面が真っ暗になった事がエンドロールも終った事を表している。そして、とうとうその時はやって来た。