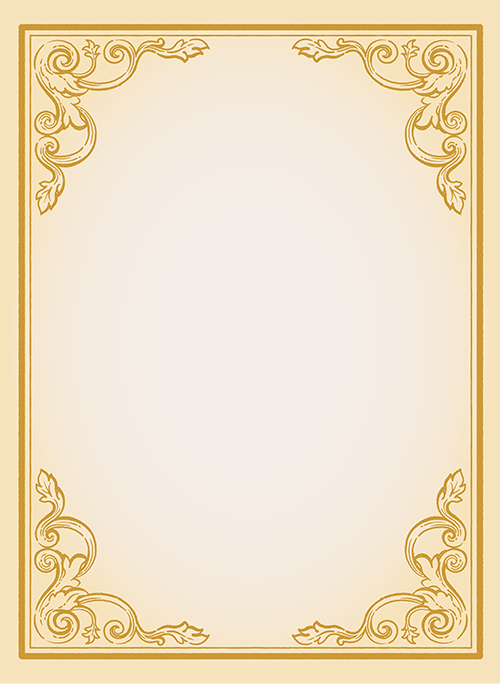彼女の手を引く様にして、駐車場まで続く石畳の上を歩く。ところどころに飾られたイルミネーションと手を振りほどかれる様子が微塵も感じられない事が、ジャックにとって幻想の世界にいるかの様な錯覚を覚えさせた。
彼が握った手を彼女が握り返してくれたのを感じると、自然とジャックの顔がほころんでいく。
───このまま時が止まってしまえばいいのに。と、心の奥底で願っていた。
車に近づくと、運転席に座ったビルがテレビに目を向けながら退屈そうに主の帰りを待っていた。
「ビル、お待たせ」
「おかえり。その様子だと楽しんだようだね」
チラッと視線を落とした後、ビルがそう言った。
きっと仲良く手を繋いでいるのを見ての発言であろう。察した叶子は繋がれた手に視線を落とすと顔を赤らめた。
「あ、いえ、そんな……」
何て言い訳をしようかと困惑している彼女と相反して、ジャックは全くその事実を否定することなかった。
「ああ、お陰で凄く楽しかったよ。ありがとう」
さらっと言ってのけた。
繋いだ手を離すきっかけを無くした二人は、車内でも繋がれたまま。彼女の小さく華奢な手はジャックの大きな手によってすっぽりと包み込まれ、互いの温もりを感じていた。
「さて、じゃあ次は何処へ行こうか?」
「あージャック、悪いんだけど……」
この後も既に約束を取り付けてあるジャックは、叶子の顔を覗き込んでそう言うと、申し訳なさそうにビルがルームミラー越しに二人の間に割って入った。
「ああ、そうか。ビルも今日は早く帰らないとね」
「そうなんだ、カミさんがうるさくてね」
時計に目をやると時刻はまだ21:30。せっかく彼女と楽しいひと時を過ごせると思ったのに、ビルを帰さなければいけない。
ジャックは既にアルコールを摂取してしまっている為に運転する事は出来ないし、かと言ってタクシーに乗るのもあまり好きではない。
さて、どうしたものか。ジャックが決め兼ねていると、信じられない言葉が彼の耳に入ってきた。
「……貴方のお家は?」
上目使いでジャックを見上げる彼女の表情は、こんな事を言ったら彼はどんな顔をするのだろう。と、まるでジャックの反応を楽しむように僅かに口の端があがっていた。
ジャックの事を拒絶していたのはまるで全部芝居だったんじゃないのかと、自分の都合のいい様に勘違いしてしまいそうになる。トロンとした彼女の目つきからして、きっと酔った勢いでそんな事を言ってるのだと必死で自分に言い聞かせた。
本音を言うと二つ返事で“YES”と言いたい所だったが、又変な風に誤解されて距離を作られても困ると思い直し、意を決して彼女の提案を断ろうとした。
「いや、それは……」
「あー、それがいい! そうしよう!」
ジャックの言葉を遮るようにビルがそう言うと、彼女の気が変わらないうちにと、さっさと彼の自宅へと車を走らせた。
「ビ、ビル!?」
口元に手をあててクスクスと笑っている彼女を見ると、やはり冗談で言ったのでは無かったのだろうかとも思えて来る。何とも突然の展開にジャックの方は困った顔をした。
「……いいの?」
「え? いいんじゃないですか? 何か問題でも?」
ジャックが彼女を子供扱いし過ぎていたのか、しばらく合わないうちに彼女が大人びたのか。それとも無理に自分と合わせようとしているのか皆目検討もつかない。
何はともあれ、彼女が自分の家に来るからと言って、『ここで調子に乗って砕けてしまわないように、努めて冷静に振舞わなければ。せっかく彼女の気持ちが和らいできているのに、ここに来て焦ってはいけないんだ』と、自宅に到着するまで何度も自分に言い聞かせていた。
◇◆◇
「今日はありがとう。おやすみ」
「おやすみジャック。いい夜を」
「ありがとうございます、ビルさん」
二人は玄関の前で車から降り、ビルとおやすみの挨拶を交わす。ビルは叶子にウィンクをするとすぐに車を走らせ、隣接する建物に車を止めた。
「?」
不思議そうに車の行方を追っている彼女に近寄ると、腰に手をおき家の中へと誘導しながら説明した。
「あそこはスタッフハウスだよ。僕の周りで働く極近しいスタッフだけあそこに住んでるんだ」
「……カレンさんも?」
「あ、ああ」
その名前を聞いた途端、あの日の夜のが頭の中に蘇り、明らかにジャックの動揺が顕著に表れ出た。
リビングに続く長い廊下を、二人とも無言で歩き始める。さっきまでいい雰囲気だったのが、さっきの彼女の一言で一気に崩れ去ってしまった。
こんな時こそ、彼女の手を握り締めていたい。言葉には出せなくともそうする事で自分には彼女しか見えていないんだという事を示したかった。
車から降りる際に手を離してしまった事を今とても後悔していた。
親指をズボンのポケットに引っ掛けて手持ち無沙汰にしていたジャックは、その手にぬくもりを感じた。視線を落とすと少したどたどしく彼女の手がジャックの手を捕えようとしているのがわかった。そんな彼女の行動に驚きながらもすぐにその手を捕まえる。しっかりと握られた手に安心したのか彼女はニコリと笑って見せた。
「――。」
さっきの車の中での発言にしろ、自分から手を繋いできたことにしろ、なんだか以前に比べて随分大人びて見える。自分が勝手に叶子のイメージを作り上げていただけなのかと、少し疑問に思った。
「あの、少し質問していい?」
「はい、どうぞ?」
「女性にこんな事聞くのは良くないんだろうけど、――君って今何歳?」
ポカンと口が開いたかと思うと、プッと笑い出した。
「あ、何か変な事言った?」
「い、いえ……。えと、33歳です」
「ええ!? 33? 見えないね! もっと若いのかと思ってたよ」
「――思ったより歳とってて悪かったですね!」
口を尖らせて拗ねた顔をしてはいるが、その表情はなんだか嬉しそうにも見える。
「あっ、ごめんごめん。そういう意味じゃ無いんだよ」
「貴方はおいくつなんですか?」
「僕は46」
「!?!?」
「?」
「てっきり40歳前後かと」
「わ、悪かったね! おじさんで!」
二人は思わず顔を見合わせて大笑いした。
お互いいい年をして何をやってるんだろうと、この時の会話によって先程まで感じていた変な緊張がするするとほぐれていくのがわかった。
彼が握った手を彼女が握り返してくれたのを感じると、自然とジャックの顔がほころんでいく。
───このまま時が止まってしまえばいいのに。と、心の奥底で願っていた。
車に近づくと、運転席に座ったビルがテレビに目を向けながら退屈そうに主の帰りを待っていた。
「ビル、お待たせ」
「おかえり。その様子だと楽しんだようだね」
チラッと視線を落とした後、ビルがそう言った。
きっと仲良く手を繋いでいるのを見ての発言であろう。察した叶子は繋がれた手に視線を落とすと顔を赤らめた。
「あ、いえ、そんな……」
何て言い訳をしようかと困惑している彼女と相反して、ジャックは全くその事実を否定することなかった。
「ああ、お陰で凄く楽しかったよ。ありがとう」
さらっと言ってのけた。
繋いだ手を離すきっかけを無くした二人は、車内でも繋がれたまま。彼女の小さく華奢な手はジャックの大きな手によってすっぽりと包み込まれ、互いの温もりを感じていた。
「さて、じゃあ次は何処へ行こうか?」
「あージャック、悪いんだけど……」
この後も既に約束を取り付けてあるジャックは、叶子の顔を覗き込んでそう言うと、申し訳なさそうにビルがルームミラー越しに二人の間に割って入った。
「ああ、そうか。ビルも今日は早く帰らないとね」
「そうなんだ、カミさんがうるさくてね」
時計に目をやると時刻はまだ21:30。せっかく彼女と楽しいひと時を過ごせると思ったのに、ビルを帰さなければいけない。
ジャックは既にアルコールを摂取してしまっている為に運転する事は出来ないし、かと言ってタクシーに乗るのもあまり好きではない。
さて、どうしたものか。ジャックが決め兼ねていると、信じられない言葉が彼の耳に入ってきた。
「……貴方のお家は?」
上目使いでジャックを見上げる彼女の表情は、こんな事を言ったら彼はどんな顔をするのだろう。と、まるでジャックの反応を楽しむように僅かに口の端があがっていた。
ジャックの事を拒絶していたのはまるで全部芝居だったんじゃないのかと、自分の都合のいい様に勘違いしてしまいそうになる。トロンとした彼女の目つきからして、きっと酔った勢いでそんな事を言ってるのだと必死で自分に言い聞かせた。
本音を言うと二つ返事で“YES”と言いたい所だったが、又変な風に誤解されて距離を作られても困ると思い直し、意を決して彼女の提案を断ろうとした。
「いや、それは……」
「あー、それがいい! そうしよう!」
ジャックの言葉を遮るようにビルがそう言うと、彼女の気が変わらないうちにと、さっさと彼の自宅へと車を走らせた。
「ビ、ビル!?」
口元に手をあててクスクスと笑っている彼女を見ると、やはり冗談で言ったのでは無かったのだろうかとも思えて来る。何とも突然の展開にジャックの方は困った顔をした。
「……いいの?」
「え? いいんじゃないですか? 何か問題でも?」
ジャックが彼女を子供扱いし過ぎていたのか、しばらく合わないうちに彼女が大人びたのか。それとも無理に自分と合わせようとしているのか皆目検討もつかない。
何はともあれ、彼女が自分の家に来るからと言って、『ここで調子に乗って砕けてしまわないように、努めて冷静に振舞わなければ。せっかく彼女の気持ちが和らいできているのに、ここに来て焦ってはいけないんだ』と、自宅に到着するまで何度も自分に言い聞かせていた。
◇◆◇
「今日はありがとう。おやすみ」
「おやすみジャック。いい夜を」
「ありがとうございます、ビルさん」
二人は玄関の前で車から降り、ビルとおやすみの挨拶を交わす。ビルは叶子にウィンクをするとすぐに車を走らせ、隣接する建物に車を止めた。
「?」
不思議そうに車の行方を追っている彼女に近寄ると、腰に手をおき家の中へと誘導しながら説明した。
「あそこはスタッフハウスだよ。僕の周りで働く極近しいスタッフだけあそこに住んでるんだ」
「……カレンさんも?」
「あ、ああ」
その名前を聞いた途端、あの日の夜のが頭の中に蘇り、明らかにジャックの動揺が顕著に表れ出た。
リビングに続く長い廊下を、二人とも無言で歩き始める。さっきまでいい雰囲気だったのが、さっきの彼女の一言で一気に崩れ去ってしまった。
こんな時こそ、彼女の手を握り締めていたい。言葉には出せなくともそうする事で自分には彼女しか見えていないんだという事を示したかった。
車から降りる際に手を離してしまった事を今とても後悔していた。
親指をズボンのポケットに引っ掛けて手持ち無沙汰にしていたジャックは、その手にぬくもりを感じた。視線を落とすと少したどたどしく彼女の手がジャックの手を捕えようとしているのがわかった。そんな彼女の行動に驚きながらもすぐにその手を捕まえる。しっかりと握られた手に安心したのか彼女はニコリと笑って見せた。
「――。」
さっきの車の中での発言にしろ、自分から手を繋いできたことにしろ、なんだか以前に比べて随分大人びて見える。自分が勝手に叶子のイメージを作り上げていただけなのかと、少し疑問に思った。
「あの、少し質問していい?」
「はい、どうぞ?」
「女性にこんな事聞くのは良くないんだろうけど、――君って今何歳?」
ポカンと口が開いたかと思うと、プッと笑い出した。
「あ、何か変な事言った?」
「い、いえ……。えと、33歳です」
「ええ!? 33? 見えないね! もっと若いのかと思ってたよ」
「――思ったより歳とってて悪かったですね!」
口を尖らせて拗ねた顔をしてはいるが、その表情はなんだか嬉しそうにも見える。
「あっ、ごめんごめん。そういう意味じゃ無いんだよ」
「貴方はおいくつなんですか?」
「僕は46」
「!?!?」
「?」
「てっきり40歳前後かと」
「わ、悪かったね! おじさんで!」
二人は思わず顔を見合わせて大笑いした。
お互いいい年をして何をやってるんだろうと、この時の会話によって先程まで感じていた変な緊張がするするとほぐれていくのがわかった。