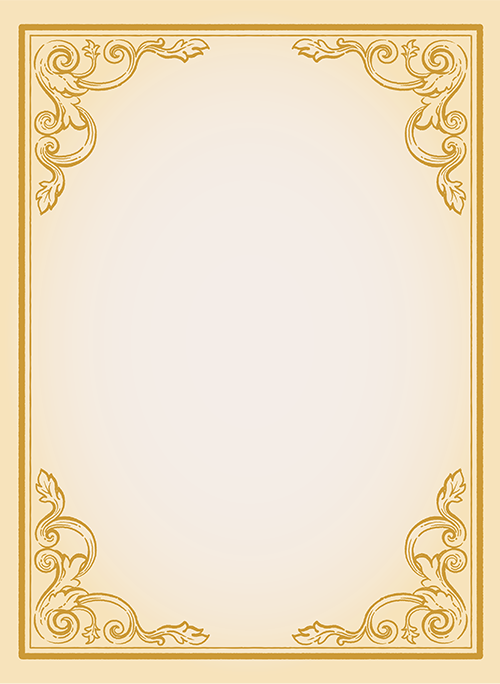もう会えないと諦めかけていた彼女に、一筋の光が差し込んだ。
結局、なんだかんだと1時間も話しこんでしまい、彼のランチタイムは無情にも終わりを告げる。
正直、会ったばかりの人とこんなに会話が弾むとは思っても見なかったが、まるで包み込まれて居るような彼の優しい話し方にすっかり夢中になってしまっていた彼女は、“CDを返す”と言う肝心な話をするのも忘れていた。
「──あっと、もうこんな時間か。……もっと話して居たいけど、そろそろ仕事に戻らないと」
「あっ、ごめんなさい! お昼食べてないんじゃ」
「ああ、平気。こんな事はしょっちゅうだからね」
「そう、ですか」
彼の事を気遣いながらも、心の片隅ではまだ話していたい気持ちが湧いている事に動揺した。
何故、こんなに心が揺れるのだろう?
何故、こんなに気持ちが落ち着かないのだろう?
何故、こんなに彼に――会いたいのかな?
本当は判っているはずなのに、叶子はその自分の気持ちをまだ受け入れる事ができないでいる。
まだ一度しか会った事のない人。しかも、その一度だってほんの少し言葉を交わしただけで、そんな気持ちになるなんてありえない。と理性が彼女の邪魔をする。そんな事、生まれてこのかた一度も経験した事がなかった叶子は、それを認めてしまうと今まで生きてきた人生を否定するような、そんな気がした。
「とりあえず、そうだな……19時にウェリントンホテルのロビーで」
「あ、はい! わかりました」
それでも又彼と会えると思うと、自然と笑顔になるのを止める事が出来なかった。
◇◆◇
待ち合わせ場所はホテルのロビー。さすがに普段着では行けそうに無い、いやホテルでなくても、だ。
彼女は今日というこの日の為に、新しい服を新調した。
履き慣れないピンヒールを履き、雨も降っていないのに大事そうに紳士物の傘とCDを持って街を歩く姿は、周りからはどんな風に映っているだろう?
紳士物の傘がなぜだか誇らしげに思えた。
約束通りの時間にホテルのロビーにつくと、辺りをキョロキョロと見回しては、彼がまだ到着していない事を確認する。ドキドキする気持ちを落ち着かせるように胸の前で両手を組むと、何処からか甘い香りがふわっと漂った。
(この香りは……)
そう思った瞬間、肩をトントンと叩かれた。叶子は笑顔で振り返ると、そこにはあの日のあの彼があの日と同じ笑顔で立っていた。
「お待たせ」
やはり綺麗な人だ。
彼女は見惚れてしまって声が出せず、ただ首を左右に振った。
「じゃあ、行こうか」
彼女の胸の前で組まれた手を彼がおもむろに掴むと、後ろに居る彼女に振り返りもせず、どんどん歩いて行く。彼の歩くスピードについていけない叶子は、少し小走りになるほどだった。
あの日触れた暖かい彼の手はソコには無く、冷たい感触だけが彼女の手の甲に伝わって来る。ただ、それだけなのに、あの時感じた彼とは全く違う印象を受けてしまった。
「ど、何処へ?」
問いかけても彼は振り向きもせず、黙々と足を進めている。
エレベーターホールで彼がボタンを押すと、箱が到着するのをまるでせかしているかのように、指をパチンパチンと何度も鳴らしていた。
(な、何だろう? 前会った時と随分印象が違う様な……)
この時によぎった彼女の不安は的中した───
エレベーターは最上階で止まり、通い慣れてるかのように彼はどんどん進んでいく。大きな2枚扉の前にたどり着くとカードキーを差込み、その重そうな扉をいとも簡単に片手で開けて見せた。
部屋に入って彼女の手を解放するとすぐに扉を閉め、まるで何者かに追われているかの様に、ドアスコープから廊下の様子をチェックしている。何も異常が無いことを確認すると、ドアを厳重にロックして彼女の方を振り返った。
その時に見せた冷たい表情に身体がパキンッと硬直する。長い前髪の隙間から覗く生気が感じられない目は、まるで小動物を捕食しようと様子を伺っている肉食動物の様にも見えた。
腕を組み片手を顎にやりながら、叶子の頭のてっぺんからつま先までを舐める様に見ていた。
「な、何ですか?」
向けられた視線に耐えられなくなり、胸元を隠すように右手で反対の腕をさする。
「――なにボーっとつったってんの?」
「え? ……」
「僕とってもお腹がすいてるんだよ」
「は、はぁ……?」
「──ねぇ、……君を味見させてよ」
「っ!」
ジャケットを脱ぎ捨てながら、ゆっくりと彼女に向かって近づいてくる。首もとのネクタイを片手で緩めると、男らしい喉元が顔を出した。
舌なめずりしながら距離を縮めてくる彼に身の危険を感じながらも、まるで蛇に睨まれた蛙の様に彼女は動けなくなっていた。手足はガタガタと震えだし、だんだん近づいてくる恐怖で声も出ない。
(や、やだ、そんな人だと思わなかった、……のに)
やがて彼女の目の前で彼が足を止めた。
「──両手を出して」
断ると何をされるか判らない。そんな雰囲気がそこはかとなく漂い、叶子は言われるがまま小刻みに震える手を差し出した。
彼はそんな怯えた彼女を見ると、大きな両手で彼女の手を包み込み、
「かわいそうに、こんなに震えて」
そっとその手の甲に口づけた。チュッチュッと何度も何度も少しずつ位置をずらしては口づけを落としていく。手のひら、指の腹、指の背まで余す事無く彼の唇が触れていく。
「あ、あの……や、やめてくださ、───っ!!」
恥ずかしさのあまり下を向きながらその行為を耐え忍んでいると、叶子の指の先にチロリと生暖かいものが触れたのが判り一気に息を吸い込んだ。驚きで顔を上げると、自分の人差し指の先を、彼の赤い舌が艶かしく蠢(うごめ)いている現実を直視し、卒倒しそうになる。その赤い舌を辿って彼の顔を見てみれば、叶子の指先を味わいながらも視線は彼女に向けている欲望に満ち溢れた彼と目が合った。
それはまるで叶子の表情の変化を愉しんで居るかのようだった。
手を引き戻そうとしてもびくともしない。中性的なルックスをしていてもやはり男だ。どんなにあがいても、男の力には敵わないのだと、もがけばもがくほど自分に知らしめる事となり、更なる恐怖を生むだけだった。
「……やっ! や、止めて!!」
と、彼女が叫ぶとその舌はそれ以上進むことは無くなった。ホッとしたのも束の間、手にしていたネクタイをおもむろに彼女の両手首に巻きつけていく。
「なっ?! ……にを、」
「大丈夫。怖がらなくていいからね」
彼の口元に舌が這う。
ゾクリ──。自分が今目にしている光景に身体の力が抜け、手にしていたCDがカシャンと床に落ちた。次の瞬間、彼が視界から消えたかと思うと叶子の体がフッと宙に浮く。片方の肩にかつがれながらそのまま奥の部屋へと突き進んでいった。
パキンッとCDを踏みつける軽い音が響き、これから行われようとしている事を察した彼女の目から、涙がポトリ、ポトリと零れ落ち、それが絨毯の上に染みを作る。片手で彼女のピンヒールを一足づつ脱がせては放り投げ、ドサッと乱暴にベッドへ下ろされたと同時に彼が襲い掛かって来た
「や、めっ……!」
激しく抵抗すると彼女の肩を両手で掴み、彼が挑発的な顔をする。
「何言ってるの? こうなるって君も望んでたからホイホイついてきたんじゃないの?」
「そんなっ! 私はただ……」
「ただ、何?」
「……ただ、あなたにもう一度会いたくて」
彼女の言葉に一瞬彼の表情がハッとなったが、すぐに元の冷たい表情に戻った。
「──クククッ」
「!?」
「もっと素直になりなよ。顔にはちゃんと書いてあるよ? 僕が欲しくてたまらないってね」
「っ! そんなことっ!」
「いいさ、君がそうやって意地張るんなら、───僕が解き放してあげるからっ!」
そう吐き捨てると同時に、叶子の服に手を掛けた。
ビリビリビリッ……新調した服を勢い良く破りだし、現れた白い肌に荒々しく唇を這わせる。彼の大きな掌で膝元から太ももまでをゆっくりと撫で回された。その内、直に肌に触れられている感触に気付き、その事がストッキングが破かれてしまったという事を示していた。
顔の下で蠢(うごめ)く彼の頭。次第に大きくなる彼の息遣いに、叶子は恐怖のあまり声が出ない。
(――誰か! 助けてっ!!)
脳内で何度助けを呼んでみても、当然助けがやってくるはずもない。このまま彼のなすがままにされるしかないのだろうか。第一印象が良かった為に何の疑いも持たずに信用し、誘われるがままついて来てしまった彼女に課せられたこれは罰なのであろうか?
口唇を噛み締めたせいで、口内に鉄の味が広がる。どうにかして逃れる方法は無いかと視線を横に移した時、ベッドサイドに大きな花瓶を見つけた。彼に気付かれない様にそっと花瓶に手を伸ばし、縛られた両手でしっかりとそれを握ると次の瞬間、目を瞑りながらおもいっきり彼の頭めがけて花瓶を振り下ろした。
「やめてーーーっ!!!」
「……、」
すると、胸元と太ももに感じていた嫌な感触はピタッと無くなり、叶子は恐る恐る瞼を開いた。
目の前にあるのは、いつもの見慣れた天井。カーテンの隙間から差し込む光は、もうすぐ夜が明けるのを知らせている。全身びっしょりと汗だくになった彼女は体を起こし、自分の体に異常がないかを確かめる。
「ゆ、夢……?」
ほっとしたと同時になんて夢をみてしまったんだと、恥ずかしくなり両手で顔を覆い、
「へ、変な夢見てごめんなさいっ!」
思わず声に出して、彼に詫びた。
結局、なんだかんだと1時間も話しこんでしまい、彼のランチタイムは無情にも終わりを告げる。
正直、会ったばかりの人とこんなに会話が弾むとは思っても見なかったが、まるで包み込まれて居るような彼の優しい話し方にすっかり夢中になってしまっていた彼女は、“CDを返す”と言う肝心な話をするのも忘れていた。
「──あっと、もうこんな時間か。……もっと話して居たいけど、そろそろ仕事に戻らないと」
「あっ、ごめんなさい! お昼食べてないんじゃ」
「ああ、平気。こんな事はしょっちゅうだからね」
「そう、ですか」
彼の事を気遣いながらも、心の片隅ではまだ話していたい気持ちが湧いている事に動揺した。
何故、こんなに心が揺れるのだろう?
何故、こんなに気持ちが落ち着かないのだろう?
何故、こんなに彼に――会いたいのかな?
本当は判っているはずなのに、叶子はその自分の気持ちをまだ受け入れる事ができないでいる。
まだ一度しか会った事のない人。しかも、その一度だってほんの少し言葉を交わしただけで、そんな気持ちになるなんてありえない。と理性が彼女の邪魔をする。そんな事、生まれてこのかた一度も経験した事がなかった叶子は、それを認めてしまうと今まで生きてきた人生を否定するような、そんな気がした。
「とりあえず、そうだな……19時にウェリントンホテルのロビーで」
「あ、はい! わかりました」
それでも又彼と会えると思うと、自然と笑顔になるのを止める事が出来なかった。
◇◆◇
待ち合わせ場所はホテルのロビー。さすがに普段着では行けそうに無い、いやホテルでなくても、だ。
彼女は今日というこの日の為に、新しい服を新調した。
履き慣れないピンヒールを履き、雨も降っていないのに大事そうに紳士物の傘とCDを持って街を歩く姿は、周りからはどんな風に映っているだろう?
紳士物の傘がなぜだか誇らしげに思えた。
約束通りの時間にホテルのロビーにつくと、辺りをキョロキョロと見回しては、彼がまだ到着していない事を確認する。ドキドキする気持ちを落ち着かせるように胸の前で両手を組むと、何処からか甘い香りがふわっと漂った。
(この香りは……)
そう思った瞬間、肩をトントンと叩かれた。叶子は笑顔で振り返ると、そこにはあの日のあの彼があの日と同じ笑顔で立っていた。
「お待たせ」
やはり綺麗な人だ。
彼女は見惚れてしまって声が出せず、ただ首を左右に振った。
「じゃあ、行こうか」
彼女の胸の前で組まれた手を彼がおもむろに掴むと、後ろに居る彼女に振り返りもせず、どんどん歩いて行く。彼の歩くスピードについていけない叶子は、少し小走りになるほどだった。
あの日触れた暖かい彼の手はソコには無く、冷たい感触だけが彼女の手の甲に伝わって来る。ただ、それだけなのに、あの時感じた彼とは全く違う印象を受けてしまった。
「ど、何処へ?」
問いかけても彼は振り向きもせず、黙々と足を進めている。
エレベーターホールで彼がボタンを押すと、箱が到着するのをまるでせかしているかのように、指をパチンパチンと何度も鳴らしていた。
(な、何だろう? 前会った時と随分印象が違う様な……)
この時によぎった彼女の不安は的中した───
エレベーターは最上階で止まり、通い慣れてるかのように彼はどんどん進んでいく。大きな2枚扉の前にたどり着くとカードキーを差込み、その重そうな扉をいとも簡単に片手で開けて見せた。
部屋に入って彼女の手を解放するとすぐに扉を閉め、まるで何者かに追われているかの様に、ドアスコープから廊下の様子をチェックしている。何も異常が無いことを確認すると、ドアを厳重にロックして彼女の方を振り返った。
その時に見せた冷たい表情に身体がパキンッと硬直する。長い前髪の隙間から覗く生気が感じられない目は、まるで小動物を捕食しようと様子を伺っている肉食動物の様にも見えた。
腕を組み片手を顎にやりながら、叶子の頭のてっぺんからつま先までを舐める様に見ていた。
「な、何ですか?」
向けられた視線に耐えられなくなり、胸元を隠すように右手で反対の腕をさする。
「――なにボーっとつったってんの?」
「え? ……」
「僕とってもお腹がすいてるんだよ」
「は、はぁ……?」
「──ねぇ、……君を味見させてよ」
「っ!」
ジャケットを脱ぎ捨てながら、ゆっくりと彼女に向かって近づいてくる。首もとのネクタイを片手で緩めると、男らしい喉元が顔を出した。
舌なめずりしながら距離を縮めてくる彼に身の危険を感じながらも、まるで蛇に睨まれた蛙の様に彼女は動けなくなっていた。手足はガタガタと震えだし、だんだん近づいてくる恐怖で声も出ない。
(や、やだ、そんな人だと思わなかった、……のに)
やがて彼女の目の前で彼が足を止めた。
「──両手を出して」
断ると何をされるか判らない。そんな雰囲気がそこはかとなく漂い、叶子は言われるがまま小刻みに震える手を差し出した。
彼はそんな怯えた彼女を見ると、大きな両手で彼女の手を包み込み、
「かわいそうに、こんなに震えて」
そっとその手の甲に口づけた。チュッチュッと何度も何度も少しずつ位置をずらしては口づけを落としていく。手のひら、指の腹、指の背まで余す事無く彼の唇が触れていく。
「あ、あの……や、やめてくださ、───っ!!」
恥ずかしさのあまり下を向きながらその行為を耐え忍んでいると、叶子の指の先にチロリと生暖かいものが触れたのが判り一気に息を吸い込んだ。驚きで顔を上げると、自分の人差し指の先を、彼の赤い舌が艶かしく蠢(うごめ)いている現実を直視し、卒倒しそうになる。その赤い舌を辿って彼の顔を見てみれば、叶子の指先を味わいながらも視線は彼女に向けている欲望に満ち溢れた彼と目が合った。
それはまるで叶子の表情の変化を愉しんで居るかのようだった。
手を引き戻そうとしてもびくともしない。中性的なルックスをしていてもやはり男だ。どんなにあがいても、男の力には敵わないのだと、もがけばもがくほど自分に知らしめる事となり、更なる恐怖を生むだけだった。
「……やっ! や、止めて!!」
と、彼女が叫ぶとその舌はそれ以上進むことは無くなった。ホッとしたのも束の間、手にしていたネクタイをおもむろに彼女の両手首に巻きつけていく。
「なっ?! ……にを、」
「大丈夫。怖がらなくていいからね」
彼の口元に舌が這う。
ゾクリ──。自分が今目にしている光景に身体の力が抜け、手にしていたCDがカシャンと床に落ちた。次の瞬間、彼が視界から消えたかと思うと叶子の体がフッと宙に浮く。片方の肩にかつがれながらそのまま奥の部屋へと突き進んでいった。
パキンッとCDを踏みつける軽い音が響き、これから行われようとしている事を察した彼女の目から、涙がポトリ、ポトリと零れ落ち、それが絨毯の上に染みを作る。片手で彼女のピンヒールを一足づつ脱がせては放り投げ、ドサッと乱暴にベッドへ下ろされたと同時に彼が襲い掛かって来た
「や、めっ……!」
激しく抵抗すると彼女の肩を両手で掴み、彼が挑発的な顔をする。
「何言ってるの? こうなるって君も望んでたからホイホイついてきたんじゃないの?」
「そんなっ! 私はただ……」
「ただ、何?」
「……ただ、あなたにもう一度会いたくて」
彼女の言葉に一瞬彼の表情がハッとなったが、すぐに元の冷たい表情に戻った。
「──クククッ」
「!?」
「もっと素直になりなよ。顔にはちゃんと書いてあるよ? 僕が欲しくてたまらないってね」
「っ! そんなことっ!」
「いいさ、君がそうやって意地張るんなら、───僕が解き放してあげるからっ!」
そう吐き捨てると同時に、叶子の服に手を掛けた。
ビリビリビリッ……新調した服を勢い良く破りだし、現れた白い肌に荒々しく唇を這わせる。彼の大きな掌で膝元から太ももまでをゆっくりと撫で回された。その内、直に肌に触れられている感触に気付き、その事がストッキングが破かれてしまったという事を示していた。
顔の下で蠢(うごめ)く彼の頭。次第に大きくなる彼の息遣いに、叶子は恐怖のあまり声が出ない。
(――誰か! 助けてっ!!)
脳内で何度助けを呼んでみても、当然助けがやってくるはずもない。このまま彼のなすがままにされるしかないのだろうか。第一印象が良かった為に何の疑いも持たずに信用し、誘われるがままついて来てしまった彼女に課せられたこれは罰なのであろうか?
口唇を噛み締めたせいで、口内に鉄の味が広がる。どうにかして逃れる方法は無いかと視線を横に移した時、ベッドサイドに大きな花瓶を見つけた。彼に気付かれない様にそっと花瓶に手を伸ばし、縛られた両手でしっかりとそれを握ると次の瞬間、目を瞑りながらおもいっきり彼の頭めがけて花瓶を振り下ろした。
「やめてーーーっ!!!」
「……、」
すると、胸元と太ももに感じていた嫌な感触はピタッと無くなり、叶子は恐る恐る瞼を開いた。
目の前にあるのは、いつもの見慣れた天井。カーテンの隙間から差し込む光は、もうすぐ夜が明けるのを知らせている。全身びっしょりと汗だくになった彼女は体を起こし、自分の体に異常がないかを確かめる。
「ゆ、夢……?」
ほっとしたと同時になんて夢をみてしまったんだと、恥ずかしくなり両手で顔を覆い、
「へ、変な夢見てごめんなさいっ!」
思わず声に出して、彼に詫びた。