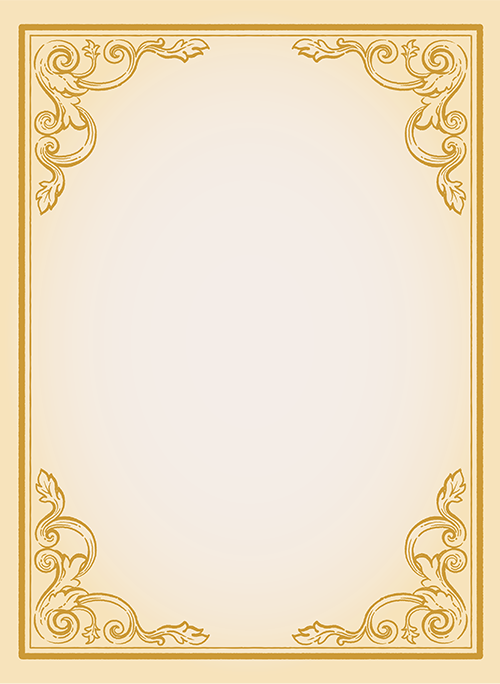良く晴れた日曜日の朝、ベランダのプランターに水を上げながら、叶子はあの日の事を思い出していた。
誰も一緒に過ごす人がいない彼女に、突如降って沸いたプレゼント。あの時、一瞬触れた彼のぬくもりがまだ手の甲に残っているように感じる。部屋から流れ出るあの時のCDを聞きながらベランダに置かれた木目調の椅子に腰掛け、温かいミルクティーに手を伸ばした。
両手でそのぬくもりを感じながら、あの日起こった出来事を、何度も、何度も思い返す。
あの日から既に2週間ほど経っていた。
このCDは明らかに“借りている”ものなのだから、そろそろ返さなくては……そう思いつつ、何度も部屋の中を振り返っては電話へと視線を向けていた。
マグをテーブルに置き部屋の中へと入ると、電話の横に置いてある名刺を手に取った。小田桐(おだぎり) 聖人(せいと)と書かれた彼であろうその名前に、思わず笑みが零れ落ちる。
「聖人……かぁ。なんか名前とピッタリな人だなぁ」
初めて会ったのは奇しくもクリスマスの夜で、成り行きとはいえ見ず知らずの自分に対し、雨の中わざわざ追いかけてきてまでクリスマスプレゼントを渡してくれたのを思い出すと、お腹の底から温かいものが湧き出てくるような感覚がした。
名前の右下に書いてある電話番号を見て見れば、メールアドレスが記載されている事に気付いた。
(今日は日曜日だし、職場に電話してもきっといないよね? 万が一居たとしても、お仕事の邪魔になるといけないから、メールにした方がいいのかな。それともこの住所に送り返す方が……)
そんな事を考えながら、しばらく電話の前をウロウロと行ったり来たりしている。見ず知らずの人から物を借りるなど叶子にとっては初めての経験だっただけに、どうしたらいいものかわからず頭を悩ませていた。
ただ、一つ言える事は、“彼にもう一度会いたい”と強く願っている自分が居ること。
会ってどうなるわけでもないとは思っているが、その気持ちが日に日に彼女の中で大きくなっていたのは確かであった。
受話器に手を伸ばしては離すを繰り返す。いつになっても決心がつかず、拉致があかない。
(12時になったら電話してみよう! で、もし電話に出なかったら……、郵送しよう)
12時までまだ少し時間がある。
そう決断してみれば、先程まで落ち着かなかった気持ちがすっと軽くなるのがわかった。
ベランダに戻り、すっかり冷え切ったミルクティーを手に取った。部屋の中へと戻り、緊張を解きほぐす為に残っていた仕事を片付けようとPCの電源を入れてみたが、どうしても時計が気になってしょうがない。
予定の時刻に時計の針はおかまいなく進んでいく。
もういっその事、メールして郵送してしまおうか。何度もそう思った。
10分前にもなると緊張は最高潮まで達し、耐え切れず部屋の中をウロウロと歩き回りだす。
(き、今日は日曜日だしきっといないよね)
会いたいはずなのに、矛盾にも彼が電話に出ない事を願っていた。
とうとう時間が来て、叶子は覚悟を決め受話器を手にする。震える自分の指先を見てしまうとそれが余計に心臓の音を早くさせる。叶子はその事に気付かない振りをして、大きく深呼吸してからダイアルした。
しかし、最後の番号を押そうとするとどうしても押すことが出来なくて、慌てて受話器を下ろしてしまう。
「ああー、どうしよう……緊張するよー」
そんな事を幾度と無く繰り返した後、時計に目をやると長い針は既に“2”を指し示していた。
「もし、彼が仕事だったとしても、もうこの時間ならランチに出ちゃってるか。……って、ああ、私一体何がしたいんだろう!」
今度こそ! という気持ちで受話器を取り、最後のボタンまでぐっと押し込んだ。
「お、お、押しちゃった……」
呼び出し音が聞こえてくると、伸ばしていた手を慌てて胸元へと置く。手が跳ね返ってきそうなほどドクドクと大きく脈打つ鼓動が、彼女の緊張を更に高めていった。
──ガチャッ
(つ、繋がった……!)
「あ、あのっ、もしもし?」
上擦った声で発した言葉も機械的な音声が流れ出した事で溜息へと変わった。
「ああ、やっぱりお休みか……」
彼はやはり不在だと言う事を確信すると緊張の糸がプツリと切れ、大きく肩で息を吐いた。
あれほど“電話に出たらどうしよう!”と思っていたのが、いざいないとわかると一気に落胆する。勝手な自分に半ば呆れつつ、あきらめて受話器を耳から遠ざけようとしたその時、機械的な音声が途中でかき消されあの時の柔らかい声が受話器の向こうから聞こえだした。
「もしもし」
「ぅあっ! あ、あの、すいません」
「──……、はい?」
一度諦めていたから緊張はほぐれていたが、何て話せばいいのかを全く考えていなかった叶子はうろたえた。あの時、自分の名前を言ったわけでもなければ、大勢の人ごみの中に紛れてしまえばなんなく溶け込める自信があるほど、平々凡々特徴ある容姿なわけでもない。
「あ、えっと、その……」
「……。」
何処から切り出せばいいのかと悩んでいるうちに、無言の時はお構いなく経過する。いたずら電話だと思われているんじゃないだろうか。そんな事を想像する余裕はあるのに、肝心の言葉が全く思い浮かばなかった。
震えた手で前髪をくしゃっと握り締め、目を固く閉じながら必死で言葉を捜した。
「私、あの、その、CDを……」
「あー! もしかしてあの時の?」
覚えていてくれていた。そう確信すると、彼女の口からするすると言葉が溢れ出した。
「あの、ごめんなさい。お仕事中に電話してしまって」
「ううん、大丈夫だよ。電話くれてありがとう」
「その、お礼が遅くなってすいません。CDありがとうございます。そろそろお返ししなければと思って」
「──返す?」
「え? ええ。頂いた名刺に“飽きたら返して”って」
「ああ~、あれは冗談だよ。そのCDは君が持ってていいよ?」
「冗談?」
「うん」
「あ、でも傘も……」
「それも別に返さなくていいよ。傘なんていくらでも持ってるから」
「そんな、見ず知らずの人にそこまでしてもらうのは」
「あれは僕からのクリスマスプレゼントだよ?」
「はぁ」
彼とはもう会えないんだ。その気持ちが叶子の中で大きくなってきた。
あの日から、今の今までわくわくしていた気持ちはやはり自分だけだったのだと痛感する。
「じゃぁ、お言葉に甘えさせて頂きます。……ありがとうございました」
「いえいえ」
「──では、……。」
一気に脱力感に襲われた。そのまま受話器をおろそうとした時、慌てた彼の声が聞こえ、急いで受話器を戻した。
「──あ! ちょっと待って!」
「は、はい??」
「あ……、そう。うん、やっぱり返してもらおうかな?」
「え? あ、……はいっ!」
明らかに彼女の声のトーンが上がる。天にも昇るような気持ちとはこの事かと思える瞬間だった。
「僕あの後ね、自分のプライベートフォンの番号を書くの忘れちゃったなぁと思って急いで引き返したんだけど、もう君の姿は当然見当たらなくなってて。職場の電話番号しか書いてなかったから、きっともう電話もらえないと思ってたんだ。――だから電話もらえて嬉しいよ」
彼と又、会えるかもしれない。
そう思うと、勇気を振り絞って電話した甲斐があったと、自分を褒めてやりたくなった。
誰も一緒に過ごす人がいない彼女に、突如降って沸いたプレゼント。あの時、一瞬触れた彼のぬくもりがまだ手の甲に残っているように感じる。部屋から流れ出るあの時のCDを聞きながらベランダに置かれた木目調の椅子に腰掛け、温かいミルクティーに手を伸ばした。
両手でそのぬくもりを感じながら、あの日起こった出来事を、何度も、何度も思い返す。
あの日から既に2週間ほど経っていた。
このCDは明らかに“借りている”ものなのだから、そろそろ返さなくては……そう思いつつ、何度も部屋の中を振り返っては電話へと視線を向けていた。
マグをテーブルに置き部屋の中へと入ると、電話の横に置いてある名刺を手に取った。小田桐(おだぎり) 聖人(せいと)と書かれた彼であろうその名前に、思わず笑みが零れ落ちる。
「聖人……かぁ。なんか名前とピッタリな人だなぁ」
初めて会ったのは奇しくもクリスマスの夜で、成り行きとはいえ見ず知らずの自分に対し、雨の中わざわざ追いかけてきてまでクリスマスプレゼントを渡してくれたのを思い出すと、お腹の底から温かいものが湧き出てくるような感覚がした。
名前の右下に書いてある電話番号を見て見れば、メールアドレスが記載されている事に気付いた。
(今日は日曜日だし、職場に電話してもきっといないよね? 万が一居たとしても、お仕事の邪魔になるといけないから、メールにした方がいいのかな。それともこの住所に送り返す方が……)
そんな事を考えながら、しばらく電話の前をウロウロと行ったり来たりしている。見ず知らずの人から物を借りるなど叶子にとっては初めての経験だっただけに、どうしたらいいものかわからず頭を悩ませていた。
ただ、一つ言える事は、“彼にもう一度会いたい”と強く願っている自分が居ること。
会ってどうなるわけでもないとは思っているが、その気持ちが日に日に彼女の中で大きくなっていたのは確かであった。
受話器に手を伸ばしては離すを繰り返す。いつになっても決心がつかず、拉致があかない。
(12時になったら電話してみよう! で、もし電話に出なかったら……、郵送しよう)
12時までまだ少し時間がある。
そう決断してみれば、先程まで落ち着かなかった気持ちがすっと軽くなるのがわかった。
ベランダに戻り、すっかり冷え切ったミルクティーを手に取った。部屋の中へと戻り、緊張を解きほぐす為に残っていた仕事を片付けようとPCの電源を入れてみたが、どうしても時計が気になってしょうがない。
予定の時刻に時計の針はおかまいなく進んでいく。
もういっその事、メールして郵送してしまおうか。何度もそう思った。
10分前にもなると緊張は最高潮まで達し、耐え切れず部屋の中をウロウロと歩き回りだす。
(き、今日は日曜日だしきっといないよね)
会いたいはずなのに、矛盾にも彼が電話に出ない事を願っていた。
とうとう時間が来て、叶子は覚悟を決め受話器を手にする。震える自分の指先を見てしまうとそれが余計に心臓の音を早くさせる。叶子はその事に気付かない振りをして、大きく深呼吸してからダイアルした。
しかし、最後の番号を押そうとするとどうしても押すことが出来なくて、慌てて受話器を下ろしてしまう。
「ああー、どうしよう……緊張するよー」
そんな事を幾度と無く繰り返した後、時計に目をやると長い針は既に“2”を指し示していた。
「もし、彼が仕事だったとしても、もうこの時間ならランチに出ちゃってるか。……って、ああ、私一体何がしたいんだろう!」
今度こそ! という気持ちで受話器を取り、最後のボタンまでぐっと押し込んだ。
「お、お、押しちゃった……」
呼び出し音が聞こえてくると、伸ばしていた手を慌てて胸元へと置く。手が跳ね返ってきそうなほどドクドクと大きく脈打つ鼓動が、彼女の緊張を更に高めていった。
──ガチャッ
(つ、繋がった……!)
「あ、あのっ、もしもし?」
上擦った声で発した言葉も機械的な音声が流れ出した事で溜息へと変わった。
「ああ、やっぱりお休みか……」
彼はやはり不在だと言う事を確信すると緊張の糸がプツリと切れ、大きく肩で息を吐いた。
あれほど“電話に出たらどうしよう!”と思っていたのが、いざいないとわかると一気に落胆する。勝手な自分に半ば呆れつつ、あきらめて受話器を耳から遠ざけようとしたその時、機械的な音声が途中でかき消されあの時の柔らかい声が受話器の向こうから聞こえだした。
「もしもし」
「ぅあっ! あ、あの、すいません」
「──……、はい?」
一度諦めていたから緊張はほぐれていたが、何て話せばいいのかを全く考えていなかった叶子はうろたえた。あの時、自分の名前を言ったわけでもなければ、大勢の人ごみの中に紛れてしまえばなんなく溶け込める自信があるほど、平々凡々特徴ある容姿なわけでもない。
「あ、えっと、その……」
「……。」
何処から切り出せばいいのかと悩んでいるうちに、無言の時はお構いなく経過する。いたずら電話だと思われているんじゃないだろうか。そんな事を想像する余裕はあるのに、肝心の言葉が全く思い浮かばなかった。
震えた手で前髪をくしゃっと握り締め、目を固く閉じながら必死で言葉を捜した。
「私、あの、その、CDを……」
「あー! もしかしてあの時の?」
覚えていてくれていた。そう確信すると、彼女の口からするすると言葉が溢れ出した。
「あの、ごめんなさい。お仕事中に電話してしまって」
「ううん、大丈夫だよ。電話くれてありがとう」
「その、お礼が遅くなってすいません。CDありがとうございます。そろそろお返ししなければと思って」
「──返す?」
「え? ええ。頂いた名刺に“飽きたら返して”って」
「ああ~、あれは冗談だよ。そのCDは君が持ってていいよ?」
「冗談?」
「うん」
「あ、でも傘も……」
「それも別に返さなくていいよ。傘なんていくらでも持ってるから」
「そんな、見ず知らずの人にそこまでしてもらうのは」
「あれは僕からのクリスマスプレゼントだよ?」
「はぁ」
彼とはもう会えないんだ。その気持ちが叶子の中で大きくなってきた。
あの日から、今の今までわくわくしていた気持ちはやはり自分だけだったのだと痛感する。
「じゃぁ、お言葉に甘えさせて頂きます。……ありがとうございました」
「いえいえ」
「──では、……。」
一気に脱力感に襲われた。そのまま受話器をおろそうとした時、慌てた彼の声が聞こえ、急いで受話器を戻した。
「──あ! ちょっと待って!」
「は、はい??」
「あ……、そう。うん、やっぱり返してもらおうかな?」
「え? あ、……はいっ!」
明らかに彼女の声のトーンが上がる。天にも昇るような気持ちとはこの事かと思える瞬間だった。
「僕あの後ね、自分のプライベートフォンの番号を書くの忘れちゃったなぁと思って急いで引き返したんだけど、もう君の姿は当然見当たらなくなってて。職場の電話番号しか書いてなかったから、きっともう電話もらえないと思ってたんだ。――だから電話もらえて嬉しいよ」
彼と又、会えるかもしれない。
そう思うと、勇気を振り絞って電話した甲斐があったと、自分を褒めてやりたくなった。