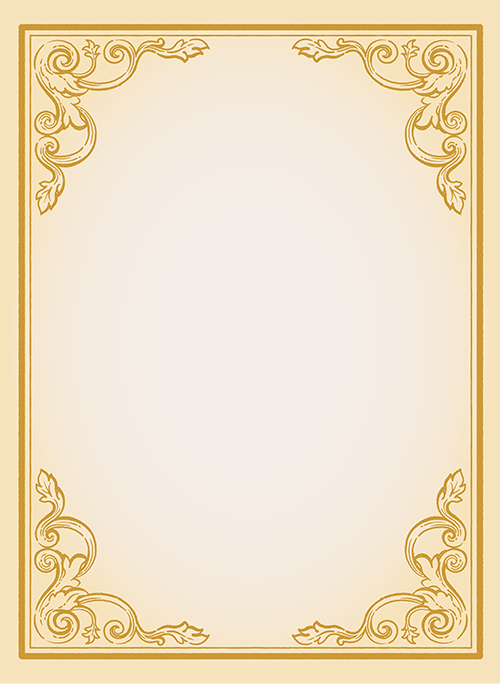「はい、これで最後ね。コレ仕上げたらもう帰っていいから」
「えぇ!? これもですか??」
ドサッとデスクの上に書類が置かれ、たちまち彼女の視界が狭くなる。書類の山から顔をひょっこり出し、不満気な声をあげた。壁にかかっている時計を横目で確認し、針が指している時刻に大きな溜息を吐く。
(毎日毎日こんなに残業ばっかじゃ、電話しようと思っても出来ないじゃない!)
自然とキーボードを叩く音が大きくなった。
「じゃ、俺は今日息子君の誕生日だから帰らせてもらうぞ? お前達もデートの一つ位したらどうだ?」
空気が読めないのか、それともあえて皆を煽る為にそんな台詞を言ったのかどうかはわからなかったが、大勢からのブーイングが飛び交う中、ボスは振り返りもせずそんな言葉を吐き捨てるとあっという間にドアの向こうへと消えていった。
一人、又一人と次々事務所を後にし、気付けば彼女一人だけが取り残されていた。
(デートの一つでもしろって……。誰のせいで毎日残業してると思ってんのよ! あぁ~もうっ! 世間の人は週末を楽しんでるはずなのに、私ときたら何でこんなに仕事ばっかりしてんだか……)
『ハァーッ』と特大のため息を吐き出した後、それを取り消すように頭を左右に振って頬を叩いた。
愚痴を言えばきりが無い。この仕事は先ほどの様な理不尽な現実を除けば、とてもやりがいがある楽しい仕事だ。手を抜こうと思えば抜く事は可能だが、そうすれば自ずとそれが結果となって返って来る。
(ちゃんとやんなきゃ!)
“ヨシッ!”っと叶子は意気込むと、スパートをかけた。
◇◆◇
「お、終わった……」
もう動けないとばかりに叶子はデスクに突っ伏した。横目でチラリと時計を見ると、もうすぐ日付が変わろうとしている。
(もう、寝ちゃってるよね)
今日も彼に電話が出来ないんだと言う事実を突きつけられたのと、仕事をやり切った感で一杯になり、一気に気が緩んで自然と瞼が閉じて行く。終いには自分の寝息が聞こえて来たのに気付き、慌てて立ち上がって帰り支度を始めた。
「しゅ、終電!!」
デスクの端でバックを広げると、机上にある荷物を片手で一気に流し込み、ポストイットやクリップと一緒にデスクの埃もバッグに仕舞い込んだ。そのままの勢いでオフィスを飛び
出し、駅へと向かう。夜の宴を楽しんだ後なのか、陽気なおじさんに声を掛けられることもあったが、叶子は振り返りもせず一心不乱に駅へとひたすら走り続けた。
◇◆◇
「……まっ、……マジで? ……、───う、嘘」
叶子の全力疾走も虚しく、最後の電車は大きな音を一つならして目の前で小さくなっていった。
「ど、どうし……よ」
予想外の出来事に混乱している頭と乱れた息を整えるため、とりあえずホームのベンチに腰掛けた。風除けがある待合室は、5人分の座席に対して1人の割合で座席が占拠されている。そこは終電に乗れなかった酔っ払い達のホテルと化していて、あの中で寒さをしのぐ事は出来ないのだと言うことは良く判った。
今更慌てても仕方が無い。すっかり諦めた叶子は真冬の風に凍えた手を温めようと、コートのポケットに両手を突っ込んだ。
「……。」
コートのポケットに入っていた携帯電話を手に取りじっと見詰めた。ある事を思い出したと同時に彼女の心臓が早く音を立て始めた。
(電話……、してみようかな)
時間も時間だし、5回コールして出なかったら切ろう。そう自分の中でルールを決めると、既に登録されている彼の電話番号を思い切って押した。
冷たい携帯電話を耳に押し当てる。呼び出し音が聞こえるまでのこのシンと静まりかえった数秒が数時間にも感じた。果たして彼は電話に出てくれるのだろうか、それとも知らない番号には出ないのだろうか。そんな事を考えながら、呼び出し音の回数を数えていた。
「はい、もしもし」
あっけなく彼が電話に出た。その声を聞き思わず笑みが零れ落ちたが、電話に出た彼は以前会った時とは違いひどく疲れている様な声に聞こえ、やはりこんな時間に電話すべきではなかったと彼女は後悔した。それでも、電話を掛けておいて無言で切る事なんて出来ない。取りあえず自分が誰なのかを告げ、又日を改めて掛け直すことを伝えようとした。
「あ、あの、こんばんは」
「……。」
「……、」
「あ! こ、こんばんは!」
急に元気になった彼の声を聞いて、少しホッとした。
「ごめんなさい、こんな時間に」
「ううん、大丈夫だよ。まだ会社だし」
「そうでしたか。お仕事お忙しそうですね」
「まぁ、いつもの事だけどね」
「すいません、特に用事があった訳じゃないので。又、……かけなおします」
「いや、もう帰るところだから大丈夫」
「や、でも、もう遅いですし――」
その時、終電が終わったというアナウンスがホームに流れだし、二人の会話も途切れてしまう。アナウンスが終わると、彼が少し驚いた様な声で話し出した。
「え? 今どこにいるの?」
「あ、私も仕事で遅くなって。今、駅にいるんです」
「駅って、――もう終電終わってるんじゃ?」
「そのようです」
叶子は笑いながらそう答えた。
ホームに駅員が巡回しだし、慌ててベンチから立ち上がる。彼の言葉を一言も逃さないよう携帯電話を耳にギュッと押し付けながら、タクシーを拾う為にホームから出ようと改札口へ向かった。
「送ってくよ」
「──え?」
思いも寄らない彼の提案に驚き、胸が大きな音を立てた。
「あのホテルの近くって言ってたよね? 君のオフィス」
「あ、いえ、だ、大丈夫! タクシーで帰りますから!」
そうは言ったものの、タクシー乗り場は既に長蛇の列が出来ている。自分の番が回ってくるのはあと何時間後だろうかと心配になった。
(ああ、どうしよう! こんなタイミングで電話したら、さも『送ってくれ』って遠まわしにアピールしてるみたいじゃない!! なんで気付かなかったんだろう?)
「や、あの、違うんですよ。そういうつもりで言ったわけじゃ……」
「だとしたらあの駅だね。えーっと10分で行くから。君は暖かくて安全な所――あ、コンビニがあるでしょ? そこに入って待ってて」
「え? いや、あっ……の? もしもし?」
どうやって言い訳をしようかと叶子が口ごもっている間に、彼はもう既に彼女の話など聞く気もないのか、さっさと待ち合わせ場所を決めると一方的に電話を切っていた。
「会える、……んだ」
あまりの急展開に少し戸惑いながらも、彼に会える嬉しさがこみ上げて来る。溜まっている日々の残業疲れも何もかも全部、この瞬間に吹っ飛んでしまいそうなほど嬉しくなる瞬間だった。
「……、ああ、でもこんな事になるんだったら、もっとましな服を着てくれば良かったなぁ」
両手を広げて自分の服を見下ろした。
◇◆◇
コンビニで暖を取っていると、両手で大切に包み込んでいた彼女の携帯電話に彼からの折り返し着信があった。
「もしもし?」
「あ、今着いたよ」
最初に電話に出た時に感じた疲れた様子の声とは明らかに違っている。前回会った時も、借りていたCDと傘を返す為だったと言うのにあえて受け取ろうとしなかった。そんな事や今の彼の様子を思うと、彼も又自分と同じ気持ちでいてくれているのでは無いかと自惚れそうになる。
淡い期待に胸を弾ませながら急いで外に出てみれば、いつもの車の横でこの寒い中コートも着ずに背中を丸めている彼が、笑顔で小さく手を振っていた。
「えぇ!? これもですか??」
ドサッとデスクの上に書類が置かれ、たちまち彼女の視界が狭くなる。書類の山から顔をひょっこり出し、不満気な声をあげた。壁にかかっている時計を横目で確認し、針が指している時刻に大きな溜息を吐く。
(毎日毎日こんなに残業ばっかじゃ、電話しようと思っても出来ないじゃない!)
自然とキーボードを叩く音が大きくなった。
「じゃ、俺は今日息子君の誕生日だから帰らせてもらうぞ? お前達もデートの一つ位したらどうだ?」
空気が読めないのか、それともあえて皆を煽る為にそんな台詞を言ったのかどうかはわからなかったが、大勢からのブーイングが飛び交う中、ボスは振り返りもせずそんな言葉を吐き捨てるとあっという間にドアの向こうへと消えていった。
一人、又一人と次々事務所を後にし、気付けば彼女一人だけが取り残されていた。
(デートの一つでもしろって……。誰のせいで毎日残業してると思ってんのよ! あぁ~もうっ! 世間の人は週末を楽しんでるはずなのに、私ときたら何でこんなに仕事ばっかりしてんだか……)
『ハァーッ』と特大のため息を吐き出した後、それを取り消すように頭を左右に振って頬を叩いた。
愚痴を言えばきりが無い。この仕事は先ほどの様な理不尽な現実を除けば、とてもやりがいがある楽しい仕事だ。手を抜こうと思えば抜く事は可能だが、そうすれば自ずとそれが結果となって返って来る。
(ちゃんとやんなきゃ!)
“ヨシッ!”っと叶子は意気込むと、スパートをかけた。
◇◆◇
「お、終わった……」
もう動けないとばかりに叶子はデスクに突っ伏した。横目でチラリと時計を見ると、もうすぐ日付が変わろうとしている。
(もう、寝ちゃってるよね)
今日も彼に電話が出来ないんだと言う事実を突きつけられたのと、仕事をやり切った感で一杯になり、一気に気が緩んで自然と瞼が閉じて行く。終いには自分の寝息が聞こえて来たのに気付き、慌てて立ち上がって帰り支度を始めた。
「しゅ、終電!!」
デスクの端でバックを広げると、机上にある荷物を片手で一気に流し込み、ポストイットやクリップと一緒にデスクの埃もバッグに仕舞い込んだ。そのままの勢いでオフィスを飛び
出し、駅へと向かう。夜の宴を楽しんだ後なのか、陽気なおじさんに声を掛けられることもあったが、叶子は振り返りもせず一心不乱に駅へとひたすら走り続けた。
◇◆◇
「……まっ、……マジで? ……、───う、嘘」
叶子の全力疾走も虚しく、最後の電車は大きな音を一つならして目の前で小さくなっていった。
「ど、どうし……よ」
予想外の出来事に混乱している頭と乱れた息を整えるため、とりあえずホームのベンチに腰掛けた。風除けがある待合室は、5人分の座席に対して1人の割合で座席が占拠されている。そこは終電に乗れなかった酔っ払い達のホテルと化していて、あの中で寒さをしのぐ事は出来ないのだと言うことは良く判った。
今更慌てても仕方が無い。すっかり諦めた叶子は真冬の風に凍えた手を温めようと、コートのポケットに両手を突っ込んだ。
「……。」
コートのポケットに入っていた携帯電話を手に取りじっと見詰めた。ある事を思い出したと同時に彼女の心臓が早く音を立て始めた。
(電話……、してみようかな)
時間も時間だし、5回コールして出なかったら切ろう。そう自分の中でルールを決めると、既に登録されている彼の電話番号を思い切って押した。
冷たい携帯電話を耳に押し当てる。呼び出し音が聞こえるまでのこのシンと静まりかえった数秒が数時間にも感じた。果たして彼は電話に出てくれるのだろうか、それとも知らない番号には出ないのだろうか。そんな事を考えながら、呼び出し音の回数を数えていた。
「はい、もしもし」
あっけなく彼が電話に出た。その声を聞き思わず笑みが零れ落ちたが、電話に出た彼は以前会った時とは違いひどく疲れている様な声に聞こえ、やはりこんな時間に電話すべきではなかったと彼女は後悔した。それでも、電話を掛けておいて無言で切る事なんて出来ない。取りあえず自分が誰なのかを告げ、又日を改めて掛け直すことを伝えようとした。
「あ、あの、こんばんは」
「……。」
「……、」
「あ! こ、こんばんは!」
急に元気になった彼の声を聞いて、少しホッとした。
「ごめんなさい、こんな時間に」
「ううん、大丈夫だよ。まだ会社だし」
「そうでしたか。お仕事お忙しそうですね」
「まぁ、いつもの事だけどね」
「すいません、特に用事があった訳じゃないので。又、……かけなおします」
「いや、もう帰るところだから大丈夫」
「や、でも、もう遅いですし――」
その時、終電が終わったというアナウンスがホームに流れだし、二人の会話も途切れてしまう。アナウンスが終わると、彼が少し驚いた様な声で話し出した。
「え? 今どこにいるの?」
「あ、私も仕事で遅くなって。今、駅にいるんです」
「駅って、――もう終電終わってるんじゃ?」
「そのようです」
叶子は笑いながらそう答えた。
ホームに駅員が巡回しだし、慌ててベンチから立ち上がる。彼の言葉を一言も逃さないよう携帯電話を耳にギュッと押し付けながら、タクシーを拾う為にホームから出ようと改札口へ向かった。
「送ってくよ」
「──え?」
思いも寄らない彼の提案に驚き、胸が大きな音を立てた。
「あのホテルの近くって言ってたよね? 君のオフィス」
「あ、いえ、だ、大丈夫! タクシーで帰りますから!」
そうは言ったものの、タクシー乗り場は既に長蛇の列が出来ている。自分の番が回ってくるのはあと何時間後だろうかと心配になった。
(ああ、どうしよう! こんなタイミングで電話したら、さも『送ってくれ』って遠まわしにアピールしてるみたいじゃない!! なんで気付かなかったんだろう?)
「や、あの、違うんですよ。そういうつもりで言ったわけじゃ……」
「だとしたらあの駅だね。えーっと10分で行くから。君は暖かくて安全な所――あ、コンビニがあるでしょ? そこに入って待ってて」
「え? いや、あっ……の? もしもし?」
どうやって言い訳をしようかと叶子が口ごもっている間に、彼はもう既に彼女の話など聞く気もないのか、さっさと待ち合わせ場所を決めると一方的に電話を切っていた。
「会える、……んだ」
あまりの急展開に少し戸惑いながらも、彼に会える嬉しさがこみ上げて来る。溜まっている日々の残業疲れも何もかも全部、この瞬間に吹っ飛んでしまいそうなほど嬉しくなる瞬間だった。
「……、ああ、でもこんな事になるんだったら、もっとましな服を着てくれば良かったなぁ」
両手を広げて自分の服を見下ろした。
◇◆◇
コンビニで暖を取っていると、両手で大切に包み込んでいた彼女の携帯電話に彼からの折り返し着信があった。
「もしもし?」
「あ、今着いたよ」
最初に電話に出た時に感じた疲れた様子の声とは明らかに違っている。前回会った時も、借りていたCDと傘を返す為だったと言うのにあえて受け取ろうとしなかった。そんな事や今の彼の様子を思うと、彼も又自分と同じ気持ちでいてくれているのでは無いかと自惚れそうになる。
淡い期待に胸を弾ませながら急いで外に出てみれば、いつもの車の横でこの寒い中コートも着ずに背中を丸めている彼が、笑顔で小さく手を振っていた。