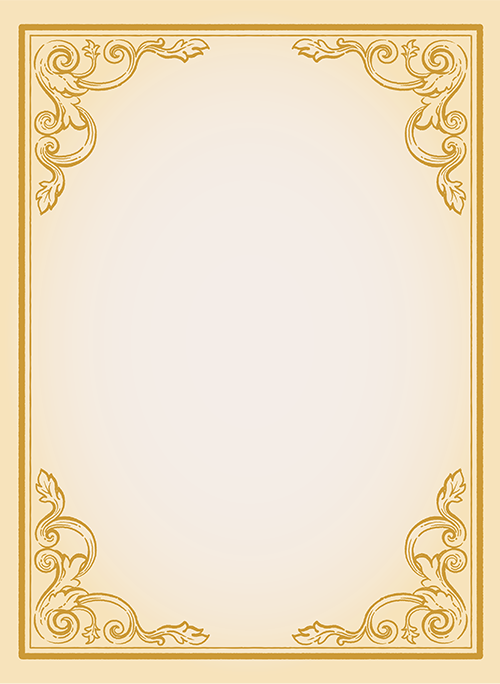「……はぁー」
急な残業で帰宅時間が思った以上に遅くなってしまった。
今日はクリスマスイブと言う事もあり深夜の繁華街はいつにも増して人通りが多く、冷静に辺りを見渡してみると仲睦まじいカップルばかりが目にはいる。
誰かが待っているわけでも無いと言うのに、現在一人身を余儀なくされている彼女にとっては今のこの現状が耐え難く、その事が自然と足を速めてしまっていた。
街中を彩るイルミネーションを横目で見ては溜息を繰り返し、背中を丸めながら野嶋 叶子(のじま かなこ)は駅までの道のりを歩いていた。
「……?」
ふと、頬に何か冷たいものを感じ反射的に空を見上げた。ポツリポツリと次第に強くなって行く雨足に目を開ける事が難しくなり、すぐに上げた顎を引き寄せる。
(雨宿りが出来るいい場所ないかな)
キョロキョロと雨宿りが出来そうな場所を探す。カフェやレストランは勿論カップルでひしめき合っていた。
(あ、あそこなら平気かも)
ひときわ明るく賑やかな店を見つけると叶子は急いでそこへ飛び込んだ。寒い冬をも忘れさせてくれる程暖かいその店内も又、多くのカップルでひしめき合っていた事に愕然とする。
雨が落ち着く迄の我慢だと自分で自分を慰めながら、沢山並んでいるCDを見つめて時間を潰そうとした。
「───、」
ふと、1枚のCDジャケットに叶子の目が留まる。
誰のCDなのかは全くわからないまま、彼女は何気なしにそのCDへと手を伸ばすと、大きな手がもう一方から伸びたのが判り、彼女は慌てて手を引っ込めた。
「あ、すいません」
相手の顔も見ずに俯きながらそういい残し、そのCDを手にする事を諦めてその場を立ち去ろうとすると、柔らかい声で呼び止められ思わず振り返ってしまった。
「──あ、待って」
庶民の集まるこの場に似つかわしくないと思えるほど気品のある物腰と、中性的な顔立ちをした男性が申し訳なさそうな顔をして自分を見つめて居た。
(わぁ……綺麗な人)
思わず見とれてしまう程、長い手足と肩まである黒髪。大きな目に長い睫毛とスッとした鼻筋が印象的で、細身の体にフィットしたダークスーツを見事に着こなしているその人は、誰もが目を引くであろう存在感を醸し出していた。
「あの、僕の方こそごめんね。コレ1枚しかないみたいだし……どうぞ?」
そう言うと、先程彼女が手を伸ばしたCDをスッと差し出した。
「あ、いえ、いいんです! ただ、ジャケットが素敵だなと思ってちょっと見てみたかっただけですので」
そう言うと彼はまるで、小さな子どもが欲しかったものをやっと手にした時の様な無垢な笑顔を覗かせた。初めて会ったと言うのにこんな表情をする彼にトクンと胸の奥が小さく跳ねる。
「僕も、……僕もそう思ったんだ! ジャケットが素敵だなって。彼にそう言っても『何処が?』って言われちゃって」
彼が親指を立て、少し離れて立っていた恰幅のいい男性を指差した。
「そうですか。……?」
ふと、周囲がざわつき始めたのを感じ辺りを見回した。流石にこのルックスだと嫌でも視線を集めてしまうのだろう。どうやらこの中性的な男性に気付いた人達が、少し距離を取りながらもチラチラと様子を伺っている事に気が付いた。そして、いつの間にか自分に好奇の目が向けられているのを感じた叶子は、急いでこの場から離れようと適当に返事をしながら愛想笑いを浮かべ、軽く会釈をして再度その場を立ち去ろうとした。が、また彼に呼び止められてしまう。
「あ!待って待って! コレ持ってって」
そう言って彼は叶子の手を取ると、そのCDを半ば強引に彼女のその小さな手にのせようとした。驚いた叶子は慌てて手を引き寄せ、二度と渡される事の無いように身体の後ろに回す。
「ほ、本当にいいんです! また買いに来たらいいだけですから」
一瞬触れた彼の手がとても暖かくソフトで、恥ずかしくなってしまって手を振り解いたと言った方がいいかもしれない。
次第に顔が熱くなるのを感じ、激しく動揺した。
そんな彼女の態度を見た彼は、顎に手を置きどうしたものかと悩んでいる様子だった。そして次の瞬間、何かいい事を思いついたような表情を浮べ、
「わかった。じゃあコレは僕が買うよ、ありがとう」
そう言って手にしたCDを軽く振りながら足早にレジへと向かう彼の背中を見送ると、周囲の目もそれに合わせて散っていった。なんだかそこに居辛くなってしまった彼女は、雨がまだ降って居るのも構わずにCDショップを後にした。
(――なんだか今日はついてないような気がする)
信号はことごとく全て赤。
雨の中、傘も持たずに信号待ちをしている彼女にはため息しかでない。
(でも素敵な人だったなぁ。あーいう人とお近づきになるには、どうすればいいんだろうな)
ふと、さっきのCDショップの彼の事を思い浮かべ、年甲斐も無く不謹慎な事を考えてしまった自分が恥ずかしくなり、煩悩をかき消すように頭を左右に振った。
しばらくして、後ろから誰かが走ってくる水音がだんだん彼女の方へと近づいてくるのが判る。その音が彼女の真後ろでピタリと止まった時、思いがけない出来事が彼女に訪れた。
「……あの!」
振り返ると、そこには先ほどのCDショップの彼が息を切らして立っていた。この寒さの中コートも着ずに追いかけてきたのか、吐く息は白く鼻の頭が赤くなっている。
「え? 何か……?」
彼は何も言わず、手にしたさっきのCDショップの袋と自分が今さしている傘を彼女に差し出した。叶子は自分が置かれている状況が把握できないでいると、彼が痺れを切らして彼女の手を取り、傘とその袋を無理矢理渡した。
呆気に取られている彼女に向かって、ニッコリと笑みを浮べ、
「メリークリスマス」
「───、……え? ……ちょっ!」
そう言うと、彼は手で雨をよけながら急いで来た道を引き返していった。
突然現れたサンタクロースに彼女はお礼を言う事も出来ず、信号が青に変わってもただ、彼の後姿を見えなくなるまで見つめていた。
「……うそ」
彼の姿が完全に見えなくなってから渡された袋の中を見てみると、神秘的な森にたたずむ小さな少女が描かれたジャケットのCDとともに、どうやら彼の名刺と思われるものが入っていた。
その名刺の裏を返すと、慌てて書き留めた風な走り書きがあることに気付く。
――聞き飽きたら返してね――
ついていない日だと思っていたのに、一気に幸せな一日に逆転する。
この時、二人の運命の針が動き出したとは当の本人は愚か、誰も気付くはずも無かった。
急な残業で帰宅時間が思った以上に遅くなってしまった。
今日はクリスマスイブと言う事もあり深夜の繁華街はいつにも増して人通りが多く、冷静に辺りを見渡してみると仲睦まじいカップルばかりが目にはいる。
誰かが待っているわけでも無いと言うのに、現在一人身を余儀なくされている彼女にとっては今のこの現状が耐え難く、その事が自然と足を速めてしまっていた。
街中を彩るイルミネーションを横目で見ては溜息を繰り返し、背中を丸めながら野嶋 叶子(のじま かなこ)は駅までの道のりを歩いていた。
「……?」
ふと、頬に何か冷たいものを感じ反射的に空を見上げた。ポツリポツリと次第に強くなって行く雨足に目を開ける事が難しくなり、すぐに上げた顎を引き寄せる。
(雨宿りが出来るいい場所ないかな)
キョロキョロと雨宿りが出来そうな場所を探す。カフェやレストランは勿論カップルでひしめき合っていた。
(あ、あそこなら平気かも)
ひときわ明るく賑やかな店を見つけると叶子は急いでそこへ飛び込んだ。寒い冬をも忘れさせてくれる程暖かいその店内も又、多くのカップルでひしめき合っていた事に愕然とする。
雨が落ち着く迄の我慢だと自分で自分を慰めながら、沢山並んでいるCDを見つめて時間を潰そうとした。
「───、」
ふと、1枚のCDジャケットに叶子の目が留まる。
誰のCDなのかは全くわからないまま、彼女は何気なしにそのCDへと手を伸ばすと、大きな手がもう一方から伸びたのが判り、彼女は慌てて手を引っ込めた。
「あ、すいません」
相手の顔も見ずに俯きながらそういい残し、そのCDを手にする事を諦めてその場を立ち去ろうとすると、柔らかい声で呼び止められ思わず振り返ってしまった。
「──あ、待って」
庶民の集まるこの場に似つかわしくないと思えるほど気品のある物腰と、中性的な顔立ちをした男性が申し訳なさそうな顔をして自分を見つめて居た。
(わぁ……綺麗な人)
思わず見とれてしまう程、長い手足と肩まである黒髪。大きな目に長い睫毛とスッとした鼻筋が印象的で、細身の体にフィットしたダークスーツを見事に着こなしているその人は、誰もが目を引くであろう存在感を醸し出していた。
「あの、僕の方こそごめんね。コレ1枚しかないみたいだし……どうぞ?」
そう言うと、先程彼女が手を伸ばしたCDをスッと差し出した。
「あ、いえ、いいんです! ただ、ジャケットが素敵だなと思ってちょっと見てみたかっただけですので」
そう言うと彼はまるで、小さな子どもが欲しかったものをやっと手にした時の様な無垢な笑顔を覗かせた。初めて会ったと言うのにこんな表情をする彼にトクンと胸の奥が小さく跳ねる。
「僕も、……僕もそう思ったんだ! ジャケットが素敵だなって。彼にそう言っても『何処が?』って言われちゃって」
彼が親指を立て、少し離れて立っていた恰幅のいい男性を指差した。
「そうですか。……?」
ふと、周囲がざわつき始めたのを感じ辺りを見回した。流石にこのルックスだと嫌でも視線を集めてしまうのだろう。どうやらこの中性的な男性に気付いた人達が、少し距離を取りながらもチラチラと様子を伺っている事に気が付いた。そして、いつの間にか自分に好奇の目が向けられているのを感じた叶子は、急いでこの場から離れようと適当に返事をしながら愛想笑いを浮かべ、軽く会釈をして再度その場を立ち去ろうとした。が、また彼に呼び止められてしまう。
「あ!待って待って! コレ持ってって」
そう言って彼は叶子の手を取ると、そのCDを半ば強引に彼女のその小さな手にのせようとした。驚いた叶子は慌てて手を引き寄せ、二度と渡される事の無いように身体の後ろに回す。
「ほ、本当にいいんです! また買いに来たらいいだけですから」
一瞬触れた彼の手がとても暖かくソフトで、恥ずかしくなってしまって手を振り解いたと言った方がいいかもしれない。
次第に顔が熱くなるのを感じ、激しく動揺した。
そんな彼女の態度を見た彼は、顎に手を置きどうしたものかと悩んでいる様子だった。そして次の瞬間、何かいい事を思いついたような表情を浮べ、
「わかった。じゃあコレは僕が買うよ、ありがとう」
そう言って手にしたCDを軽く振りながら足早にレジへと向かう彼の背中を見送ると、周囲の目もそれに合わせて散っていった。なんだかそこに居辛くなってしまった彼女は、雨がまだ降って居るのも構わずにCDショップを後にした。
(――なんだか今日はついてないような気がする)
信号はことごとく全て赤。
雨の中、傘も持たずに信号待ちをしている彼女にはため息しかでない。
(でも素敵な人だったなぁ。あーいう人とお近づきになるには、どうすればいいんだろうな)
ふと、さっきのCDショップの彼の事を思い浮かべ、年甲斐も無く不謹慎な事を考えてしまった自分が恥ずかしくなり、煩悩をかき消すように頭を左右に振った。
しばらくして、後ろから誰かが走ってくる水音がだんだん彼女の方へと近づいてくるのが判る。その音が彼女の真後ろでピタリと止まった時、思いがけない出来事が彼女に訪れた。
「……あの!」
振り返ると、そこには先ほどのCDショップの彼が息を切らして立っていた。この寒さの中コートも着ずに追いかけてきたのか、吐く息は白く鼻の頭が赤くなっている。
「え? 何か……?」
彼は何も言わず、手にしたさっきのCDショップの袋と自分が今さしている傘を彼女に差し出した。叶子は自分が置かれている状況が把握できないでいると、彼が痺れを切らして彼女の手を取り、傘とその袋を無理矢理渡した。
呆気に取られている彼女に向かって、ニッコリと笑みを浮べ、
「メリークリスマス」
「───、……え? ……ちょっ!」
そう言うと、彼は手で雨をよけながら急いで来た道を引き返していった。
突然現れたサンタクロースに彼女はお礼を言う事も出来ず、信号が青に変わってもただ、彼の後姿を見えなくなるまで見つめていた。
「……うそ」
彼の姿が完全に見えなくなってから渡された袋の中を見てみると、神秘的な森にたたずむ小さな少女が描かれたジャケットのCDとともに、どうやら彼の名刺と思われるものが入っていた。
その名刺の裏を返すと、慌てて書き留めた風な走り書きがあることに気付く。
――聞き飽きたら返してね――
ついていない日だと思っていたのに、一気に幸せな一日に逆転する。
この時、二人の運命の針が動き出したとは当の本人は愚か、誰も気付くはずも無かった。