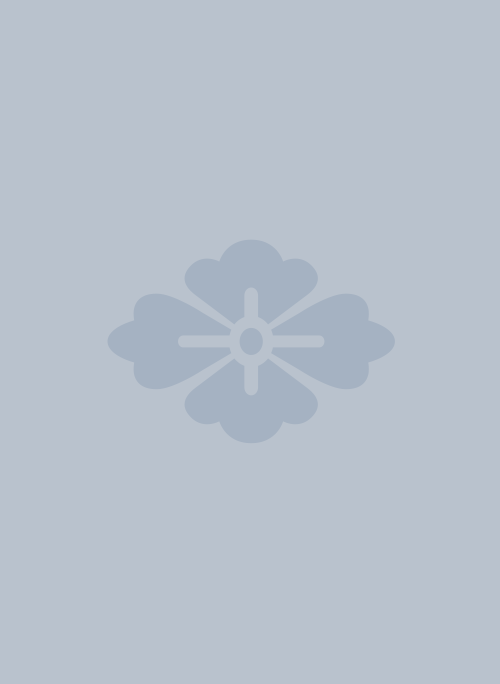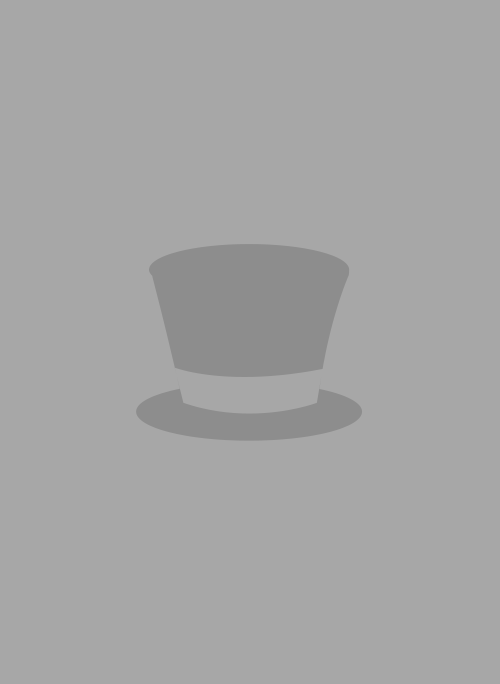陽が落ち始めた。
部屋が薄暗くなるのを、俺は畳の上にあぐらをかいたまま感じていた。
やがて妻は泣き止んで、腫れぼったくなった目で宙を見ていた。
泣き疲れているのだろうということ以外、何を考えているのか、その表情からは読み取れない。
でもこれだけはわかる。
彼女は、こんなことがしたくてわざわざ来たのではないということ。
誰も好き好んで、悲しくなることがわかっている場所に来たりしない。
もっと楽しい何かを期待して来たはずなんだ。
とは言っても…―
その「何か」が何なのか、俺にはよくわからないんだけど。
そもそも俺が、彼女に心配をかけないくらいしっかりした男だったら良かったんだ。