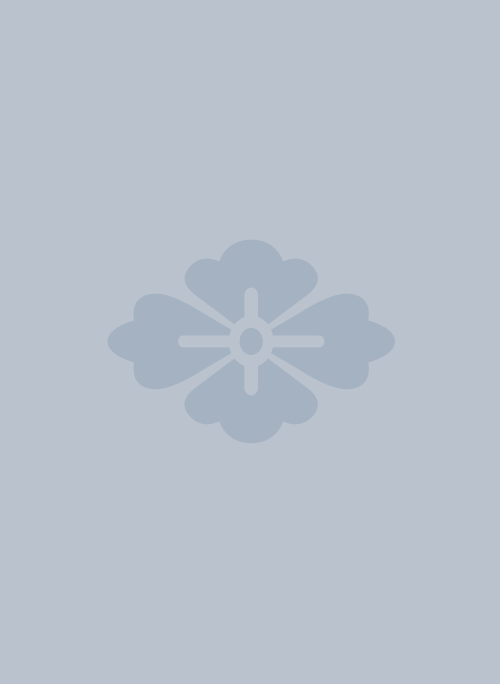その頃、小菊は小間物屋の中を物色していた。
物色というと感じが悪いが、ご飯を作ろうにも、小間物屋を手伝おうにも、どこに何があるのかわからないのだ。
いきなり店を開ける勇気はなかったため、とりあえずできることといったら、ご飯を作ることぐらいだ。
千之助がいつ帰ってくるかはわからないが、白飯ぐらいは炊いておいても差し支えないだろう。
そう思い、土間の辺りを探っていると、いきなり視界が暗くなった。
驚いて顔を上げると、いつの間に来たのか、狐姫が覗き込んでいる。
「何やってんだい。お宝なんざ、ここにゃないよ」
「っっ!」
驚きのあまり、息を呑んで固まる小菊に、狐姫はふん、と馬鹿にしたように鼻を鳴らす。
そして、小菊に抱えられている縞の猫に目をやった。
「とら、旦さんに出してもらったんかい」
狐姫の言葉に答えるように、猫は『にゃ』と鳴いた。
そうだ、この猫は虎にそっくりなのだ。
小菊は猫をまじまじと見た。
もっとも虎など、屏風絵でしか見たことはないが。
そんなことをしている間に、狐姫は店のほうに移動し、表の板戸を開けて、店を開いた。
「ほれ。何ぼさっとしてるんだい。さっさと暖簾かけて、掃除だよ」
「あ、は、はい」
物色というと感じが悪いが、ご飯を作ろうにも、小間物屋を手伝おうにも、どこに何があるのかわからないのだ。
いきなり店を開ける勇気はなかったため、とりあえずできることといったら、ご飯を作ることぐらいだ。
千之助がいつ帰ってくるかはわからないが、白飯ぐらいは炊いておいても差し支えないだろう。
そう思い、土間の辺りを探っていると、いきなり視界が暗くなった。
驚いて顔を上げると、いつの間に来たのか、狐姫が覗き込んでいる。
「何やってんだい。お宝なんざ、ここにゃないよ」
「っっ!」
驚きのあまり、息を呑んで固まる小菊に、狐姫はふん、と馬鹿にしたように鼻を鳴らす。
そして、小菊に抱えられている縞の猫に目をやった。
「とら、旦さんに出してもらったんかい」
狐姫の言葉に答えるように、猫は『にゃ』と鳴いた。
そうだ、この猫は虎にそっくりなのだ。
小菊は猫をまじまじと見た。
もっとも虎など、屏風絵でしか見たことはないが。
そんなことをしている間に、狐姫は店のほうに移動し、表の板戸を開けて、店を開いた。
「ほれ。何ぼさっとしてるんだい。さっさと暖簾かけて、掃除だよ」
「あ、は、はい」