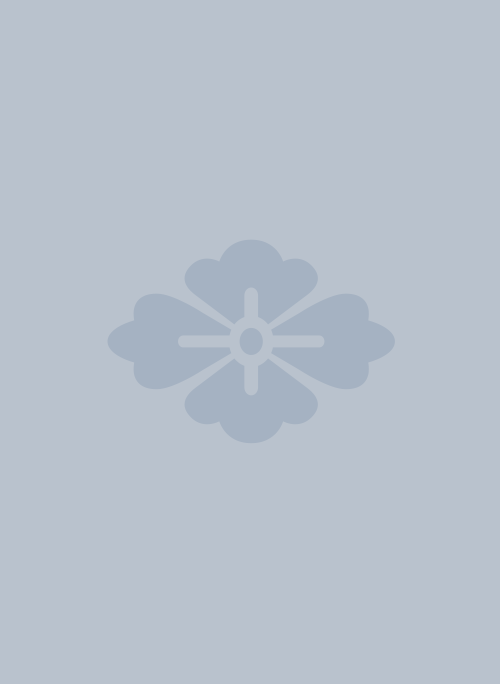「さっきそこの兄さんにも言ったがな、俺は三河出身なんだぜ」
さることながら、源九郎は明るめな口調を変えようとはしなかった。
ここで怖じけづいたような口調で物申せば、きっと舐められた態度をとられることだろう。
あくまで、対等、という位置にいたいのが源九郎の本音だった。
「………ほぅ」
三河、という単語に反応した政宗はおもしろそうに方眉を上げた。
「狸の土地か…」
「政宗様っ…!興が過ぎますぞ!」
狸、つまり殿のことを言っているんだな。
小十郎が止めてはいるが、源九郎自身もそれだけは否定できない。
金平糖のような甘味を好んだゆえのあの腹だ。
武将にとって、多少の体格も必要だとは思うが、彼はそれでも超過接種だろう。
「三河からとはまた、随分と長旅だったろうな、源九郎とやら。……どうだ?休むついでにその手に持つ槍を俺に見せてみよ」
「おう、話が分かるじゃねぇか。伊達さんよ」
「政宗様!いい加減にしてくだされ!」
小十郎が横で何やら言っているが、当の本人は俺の存在を認めている―――否、この俺がどれだけ使えるのかを見定めたいのかもしれない。
あの隻眼に映る色は疑惑。
「来い、源九郎。中庭にこいつを連れてゆけ」
「……………………御意」
明らかに不服そうに口を歪めた小十郎は、その色白の肌には到底似合わない剣幕で源九郎を睨んだ。
しかし幾千の戦を重ねてきた源九郎にとっては、彼の威嚇は何の影響もない。
やってやろうじゃねぇか。
源九郎の心の炎は燃え盛り、相対する小十郎に向かって口角を釣り上げた。