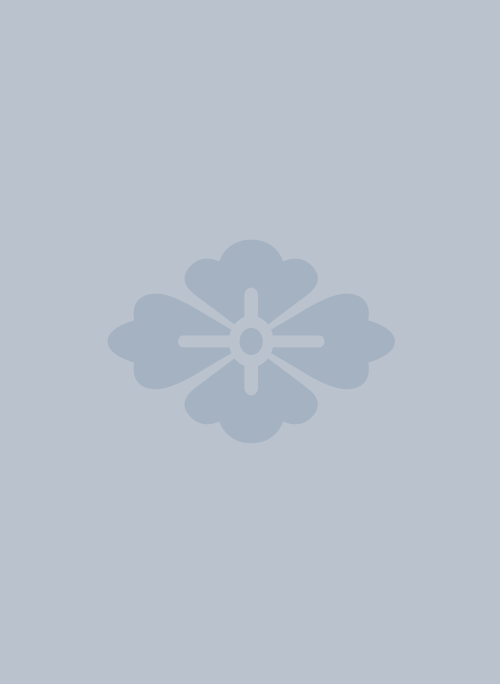まだ土埃の漂う中、源九郎は明けようとしている空を見上げた。
「一体、何を考えてるんだ……」
家康にしても、あの忍者にしてもどうして自分には何も知らさせてくれないのだろうか。
二人は確実に何かを企てている。
それが自分にとって吉なのか、凶なのか…――――
朝日が昇り、源九郎の顔に光が差す。
眩しそうに目を細め、顔の前に手をかざしながら舌打ちをした。
「明けちまったな」
場所を選ばずさっさと鍛練すればよかったのかもしれない。
どちらにしても、もう帰らなければとよがまた心配してしまうだろう。
とよの泣き顔とぎこちない笑みがそれぞれ思い浮かぶ。
源九郎は自然に頬を緩ませた。
女には疎い方だが、彼女は美しいと思う。
父に歯向かうまでの意思の強さは、かつて武士であった源九郎自身も尊敬してしまうほどだ。
凛とした声が耳を掠めるのが、くすぐったい。
その声を聞くとどうしても触れたくなってしまう。
源九郎はあの時彼女の頭に乗せた手を見つめる。
半蔵を掴もうとした手とは逆の方だ。