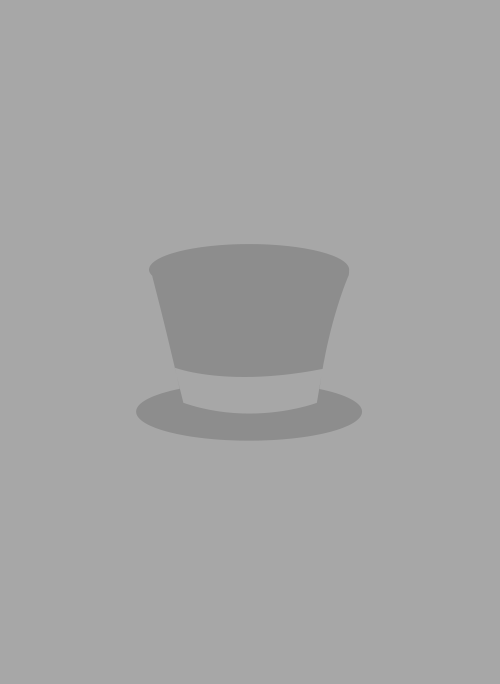「兄の戦死公報がまだ届かないのは、どういうことだと思う」
問題というのは、まさにそのことで、杉田さんと広田の話によれば、グアム島で戦闘があったのは夏のことだ。
けれど年の瀬になってなお、戦死公報を届けてくれるはずの役場からは何の音沙汰もなかった。
「公報より先に、戦友からの報告で知るなんてことあるんだろうか」
杉田さんが持ち帰ってくれた眼鏡は、ぼくも確認させてもらったところ、父の言うとおり確かに兄のものだった。
杉田さんの話にも何ら不自然なところはなかったことから、ぼくは、兄は事実、戦死したのだと受け入れていた。
それでも、国のために出征したというのに、国からの戦死公報なくして兄の人生に終止符を打つなど、納得がいかなかった。
「大方、大量の戦死者を出して国も混乱しているんだろう」
広田が難しい顔をして言った。
「俺の知り合いの家では、公報が来たにも関わらず生きて帰って来たという話も聞く。役場からの通知だからって信憑性も何もあったもんじゃないさ」
「そんなことが?そりゃあ、ご家族もさぞかし驚いたろうな」
「まあな。もう葬式まで済ませていたから、ひょっこり帰って来た息子を見てひっくり返ったってさ」
「無理もないよ。でもぼくに言わせれば、逆よりましだ」