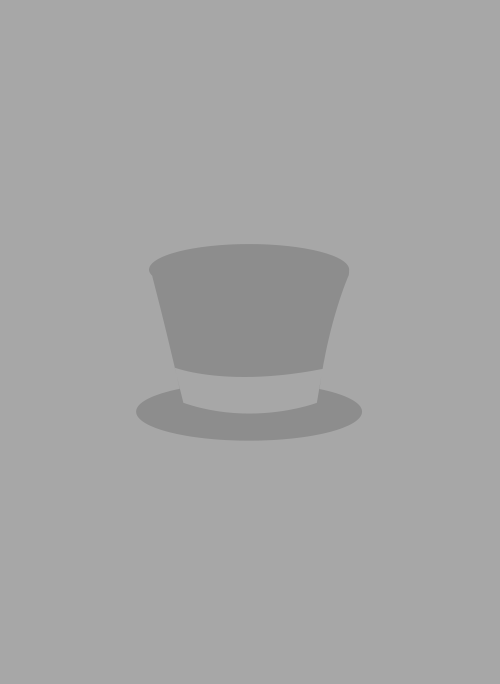思えば、きみとふたりで旅行をするのは初めてだった。
ぼくは、これまで頼ってきた親がいないとあって、ひとりの男として、また夫としてしっかりしなくてはと気を引き締めた。
幼い頃から日常を共にし、気心が知れているとはいえ、夫婦となったからには格好悪いところは見せたくなかった。
そんなぼくの決意を知ってか知らずか、仲居が去ると、きみは呑気に笑った。
「礼二さん、せっかくの温泉なのにそんなに緊張しちゃって」
「まだ父さんみたいに堂々と出来るほど人間が出来ていないんだから、仕方ないだろ」
ぼくがそっぽを向くと、きみは、
「怒ったの?」
と、ぼくのわき腹をくすぐった。
「わっ!やめろよ!」
「きゃーっ!あははは!」
お返ししてやろうとすると、きみが子供のように部屋を駆け回って逃げるから、ぼくも追いかけた。
高級旅館の一室が、そのときばかりはまるで昼休みの校庭のようだった。