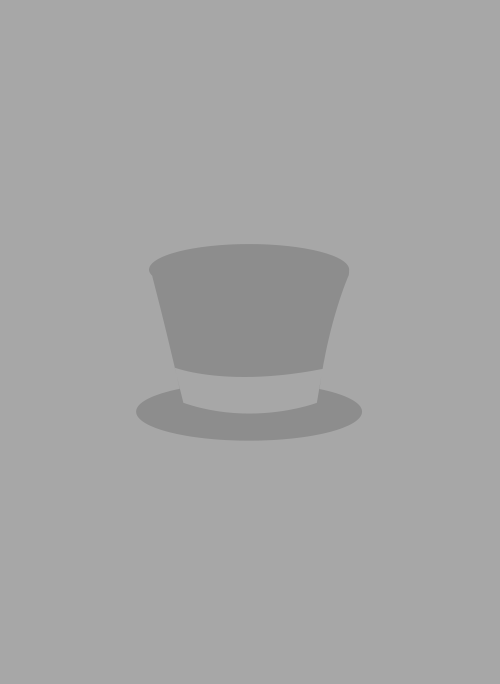(ぼくが、仲間を売った悪者に……)
それは間違いではなく、むしろ当たっていた。
けれどだからといって、そういう仕打ちを受けたいわけではない。
保身のために、今夜のことを忘れろと命じられ、ぼくは受け入れた。
去り際、宮崎さんはぼくの手に握られたカルミンを指し、
「大事に食えよ」
と笑った。
さっきまでの迫力のある鋭い視線は、そこにはなかった。
ぼくは頭を下げ、宮崎さんの背中を見送った。
ぼくは、身分を偽ってこの巡洋艦に乗り込み、世話になった先輩をひどい目に遭わせようとしている自分に嫌気がさした。
そして、温厚で気の優しい男だったに違いない宮崎さんを、こんな風にしてしまった軍隊にも。