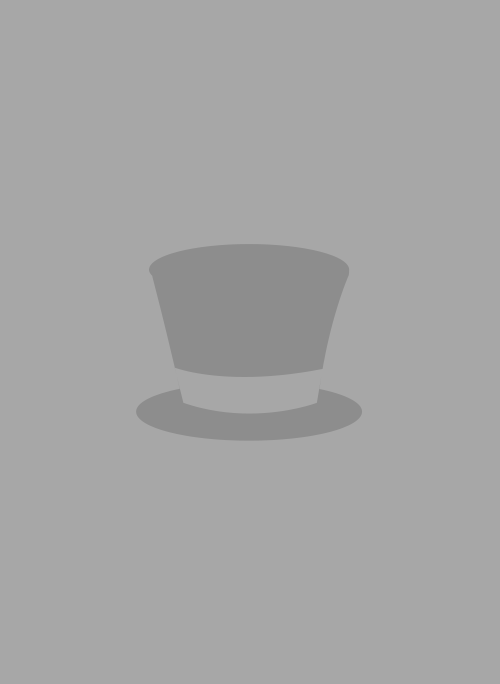夕食の準備中に艦内放送があったと宮崎さんは言ったが、ぼくには全然聞こえなかったし、外に出ればこんなにも激しい機動音が聞こえるというのに、それもわからなかった。
「自分は、船にはあまり乗ったことがないのですが、軍艦というのは室内にいれば音も静かですし、思いのほか揺れないものなのですね」
「そんなことはないよ。機動音なんて耳障りだし、時々ふわっと揺れていた」
「そう、ですか」
宮崎さんが隣の部屋の扉を開け、ぼくはもう一度卓に手を掛け、それを運んだ。
「まあ、そういうことにも気付かないほど夢中で働いていたということだろう。どうした。顔が赤いようだが、具合でも悪いか」
「何でもありません」
そう言うぼくの顔は、まるで茹でダコだった。
だって気付いてしまったのだ。
疲労からくるめまいだと思っていたふらつきが、実は船の揺れだったことに。
恥ずかしさでいっぱいになったぼくが正直にそのことを話すと、宮崎さんは大声で笑い、
「めまいでなかったにしろ、疲れてるには違いない。今日はもう休め」
と、ぼくを寝室に案内してくれた。