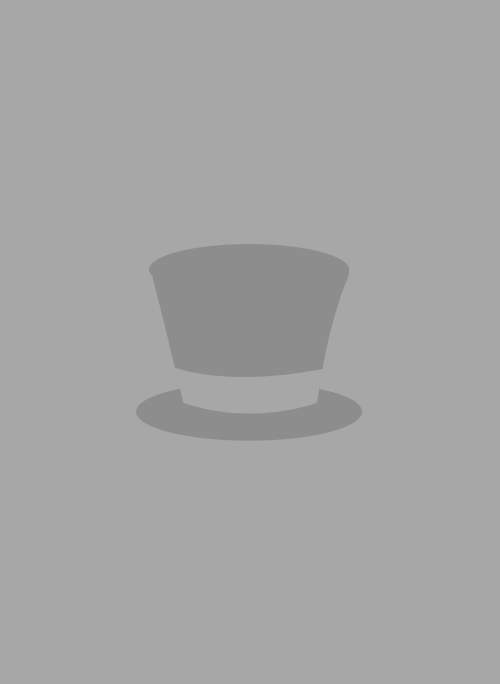「浅井さん、しばらく見ない間に若々しくなられたのでは」
「おっ、さすが相原。わかるか、実はな…」
そう言ってひと昔前の仕草とでも言おうか、小指をピンと突き立てて「いい女とできちまってな」と下品な笑いを浮かべた。
直人さんは呆れた様子で一言も発しない。
俺だって同じ気分だったが、あからさまに感情を表に出すわけにもいかない。
「これはお元気なことで。奥様にバレたら大変なことになりますね」
「いいさ、あんな古女房。どうせ俺の退職金が目当てなんだろうよ」
浅井がタバコをくわえたので、すかさず火をつけたライターを差しだす。
一度大きく白い煙を吐き出すと「いやぁ、本当にいい女なんだ。普段はツンとしてるくせに、あの時だけは甘ったるい声を出してさ」と黄色い歯を見せてにやつく。
聞く気にもならない。
だが今まで幾度か捜査情報を流してもらっているため、無下には扱えない。
「女にはうるさい浅井さんがそこまでおっしゃるのですから、きっと魅力的な女性なんでしょう。うらやましい限りです」
「おう、何てったって、ここがたまらん」
そう言って、浅井は自分の目尻をつついた。
何のことかわかりかねた俺は、作り笑いをたたえたまま小首を傾げた。
「おまえもいつかわかるさ。女にとってはコンプレックスでも、男にしてみりゃあ、それがとてつもなくそそるものだってことをよ」
「私にも早くそんな日が来るといいですね」
いつもこうだ。
自分の女遍歴を恥じらいもせずにペラペラと。
その上、お茶出しの若い衆をつかまえては、「いいか、女っちゅうのは…」と講釈をたれる。
浅井自身が納得するまで延々とそれは続き、やがてこちらが手渡した金の入った封筒をセカンドバッグに押し込んで「またな」と事務所を後にする。
浅井が帰った後は、必ず下の者に命じて塩をまく。
俺たちにとってあの男は、救世主にも疫病神にもなりうる危険なやつだ。
それから数日後だった。
浅井が自慢げに話していた例の女と、ホテルから人目を気にしながら出てくるのを見たのは。
なるほど。
横顔だけしか見えなかったが、なかなかいい女だ。
浅井が目尻を指して意味深に語っていた謎、それもわかった。
その女の右の目尻に、遠目からでもわかるほくろがあったのだ。
きっとそのことを言っていたのだろう。
その女は水商売を生業としている雰囲気でもなく、どことなく固い仕事に就いている、そんな感じだった。
そんな女が一体どうやって浅井と知り合うのか不思議に思ったが、所詮は他人事。
事務所に着いたら、暇つぶしにでも若い衆にこの話をしてやるか、そう思って俺は夜の街へと歩き出した。