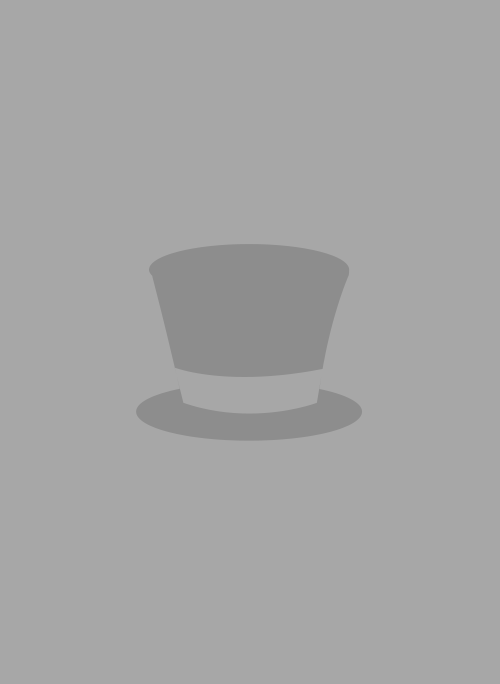時折こちらを見ることもあるが、俺には気付いていないようだ。
まあ、無理もないか。
もう10年以上も経つもんな。
なつみ園での最後の日。
まっすぐなその瞳を見て思った。
猫みたいだって。
一本の筋道を通すように、動じることなく相手を見据える。
今でも、相手を惹きつけてやまない瞳は健在だな。
その芯の通った眼差しを、いつか真正面で受けてみたいものだ。
それから半年以上経ってから、マコの酒を飲む機会が訪れた。
新しく他店からひきぬく予定のホステスと食事をした後に、Yesterdayに立ち寄った。
週末ともあって、いつも座るマスターのカウンターはいっぱいだった。
「片桐のカウンターでもよろしいでしょうか」
連れの女はあからさまに不満そうに口をとがらせたが、俺には願ってもないことだった。
「いらっしゃいませ」
柔らかな声が俺たちを出迎える。
そしてキャンドルを差し出したマコの手が一瞬止まった。
俺の左のこめかみに、痛いほどの視線。
思い出したか?
俺はもうだいぶん前からおまえのことに気付いてたさ。
内心笑いながら、俺はあえて何も言わずに連れの女をなだめていた。
機嫌を損ねた女はマコに無理難題をたたきつける。
「あたしに似合うカクテルを作ってちょうだい」
今までちやほやされてきた女にとって、マコのカウンターに回されたことがよっぽど気に入らなかったらしい。
とことん嫌な客になってやろう、そんなところだな。
所詮、その程度の女か。
マコは困惑した表情を浮かべている。
さぁ、どうする?
これからマコがどんなものを作るのか楽しみで、顔がにやついてしまう。
「かしこまりました」
力強い声。
そこには先ほどの困惑気味のマコはどこにもいなかった。
ひきしまった表情のバーテンダーが、俺たちを見ていた。
そう、あの凛とした眼差しをこちらに向けてくる。
あっという間に、深紅のカクテルを女の前に出してきた。
俺が誰だか察しているにもかかわらず、何の動揺も見せずに…