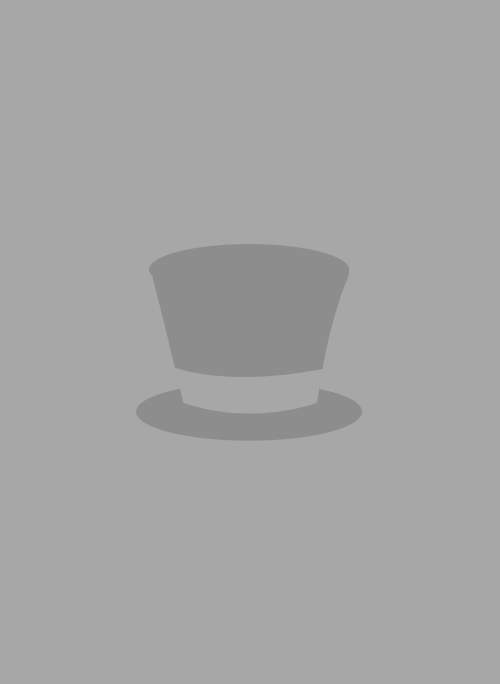ソファーでタオルケットにくるまったマコの前に、ホットブランデーを置いた。
だが彼女は手にとるどころか、目もくれようとはしない。
「飲め。少しは落ち着く」
向かいに座った俺とも目を合わさない。
しらみ始めた空が、カーテン越しに朝の訪れを告げる。
さっきからマコはずっとこの調子だ。
「知らない男に襲われた」とだけ言うと、黙りこくったままうつむいてしまったのだ。
おそらくマコを襲ったやつは、俺に怨みのあるやつだ。
須賀一家か?
それしか思い当たらない。
いや、今は犯人が誰かなんてどうでもいい。
マコを傷付けている根本的な原因は「俺」にあるのだから。
俺の女だと知って、襲ったに違いない。
直人さんのことが脳裏をかすめる。
彼はゆり子さんを想うがため、愛を告げない。
愛するがゆえに、それ以上踏み込まない。
この世界は危険がつきものだ。
周りの人間にどんな危害が加えられるか、わかったもんじゃない。
だから直人さんは愛する人を守るために、あえて「愛していない」フリをする。
なのに俺は…
マコを離したくない一心からそばに置き、こんな目に遭わせてしまった。
こんなことが起きるかもしれないとわかっていたのに…
こいつと離れるなんてできない、その俺の勝手な思いが彼女を辛い目に遭わせてしまった。
その罪悪感から、目の前のこの女を抱きしめてやることができなかった。
怖かっただろ、もう大丈夫だ、そんな言葉すらかけられない。
「おまえは…」
俺は立ち上がり、バルコニーのカーテンを開けた。
そこには、彼女がプランターに植えた紫と白の花が見事に咲き乱れていた。
「おまえはこのことを俺に黙っているつもりだったのか。服を内緒で処分しようとしたのは、そう思ったからだろ」
時折吹く小さな風に応えるように、葉を揺らす花たち。
だが、マコは何も言わない。
夜の仕事をしている以上、危険はつきものだとは前々から思っていたが、辞めろとは言えなかった。
楽しげに仕事の話をするあいつ。
よく親父さんの夢だった「MAKOTO」というカクテルをいつか完成させたい、どういうものがいいか、と相談を受けることもあった。
そんな様子を見ていると、とても言えなかった。
でも今が潮時なのかもしれない。
俺は大きく息をつくと、彼女を振り返って言った。