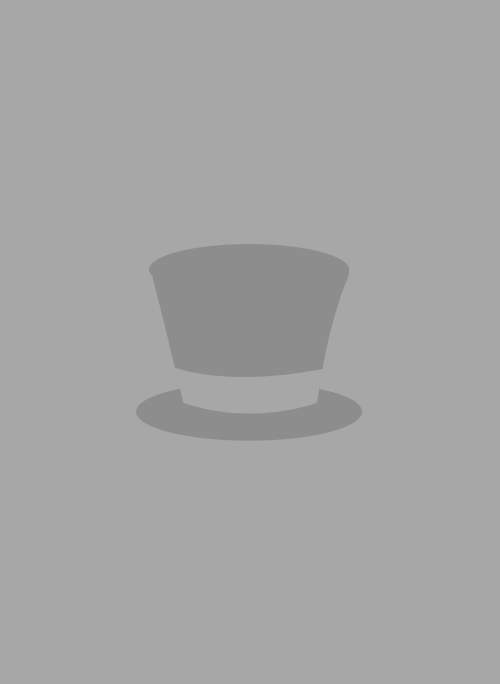毎日毎日、シトシトと降り続く雨。
そんな天気にいい加減飽きてきた頃、気持ちいいほどの青空が広がった。
「おい、調子はどうだ」
俺がベッドをのぞくと、車椅子に乗ったキヨさんがニコニコしていた。
若い看護師が俺を見るなり、ホッとしたように言う。
「ああ、お孫さんね、ちょうどよかった。屋上にあがりたいとおっしゃって」と俺に車椅子を押しやる。
「え?いや、俺は…」
「いいから早く押しな、泰輔!」
おかしそうに彼女は俺を振り返った。
ったく、誰が孫だよ。
しぶしぶ車椅子を押しながら、屋上に上がった。
「あー気持ちいいね!やっぱりこうでなくっちゃ。毎日ジトジトして気も滅入るよ」
空を見上げて豪快に笑っているつもりの本人だが、もう声はかすれてしまっている。
やるせなくて、俺も空を仰いだ。
本当だ、気持ちいいもんだな、こうやってみるのも。
久々に見たよ、空なんて。
眩しくて目を細めていた俺を、いつのまにかキヨさんは振り返って見ていた。
「…んだよ?」
照れくさい。
「今までありがとね」
「あ?何これきりみたいな言い方してんだよ」
礼なんか言われてどうしていいのかわからず、わざと無愛想に返す。
「これ店の合鍵。厨房の奥の階段を上がると、古いタンスがあるから。そこに土地の権利書やら印鑑、もろもろ入ってるから。持って行きな」
「バカ言え。俺にドロボウみたいな真似させんなよ。早く退院して、あんたから直接手渡してもらわないと後味が悪いだろ」
「ほんとはさ…」
キヨさんは視線を空に戻して、静かに話し始めた。
彼女は圭条会が立ち退きを迫ってることを、前々から近所の噂で知っていたらしい。
周りの店主も年だし、いざこざになっても面倒だからと、潔く店をたたもうという話でまとまっていたらしい。
でもその交渉に来た俺を見て、気持ちが変わったのだという。
「だってあんた、顔色もあんまり良くなかったし、ひょろひょろ痩せててさぁ。ああ、この子、ロクなもん食べてないなって…」
だから毎日、ああやって食わしてくれてたのかよ…
「俺はこう見えてもヤクザだぜ。あんたの店をつぶしにきたんだ」
「ヤクザだろうがカタギだろうが、そんなの関係ない。あんたはいい子だよ」
「は?いい子?バカか、意味がわかんねぇ」
「だってさぁ、いただきます、ごちそうさまって…言わなかった日はなかったよ」
「……」
「だからあんたはいい子に決まってる」