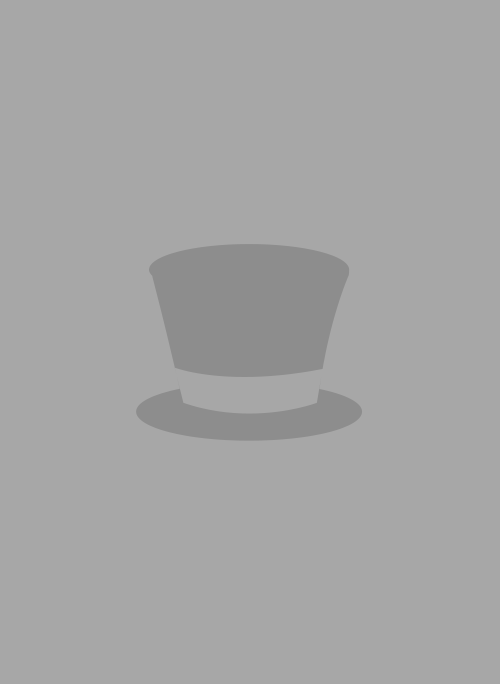~片桐真琴~
玄関のドアを開けると、たたきに小さな水たまりができていた。
濡れたお兄ちゃんの傘と靴。
部屋はいつも通り暗いのに、そこだけはまだ空気が動いていたかのよう。
…お兄ちゃん?
部屋をそっとのぞくと頭まですっぽりとふとんをかぶって眠っている。
雨が降り出したのは夜半過ぎ。
どこかに出かけていたのかな、そう思いながら私は自分の部屋に入った。
上着を脱いで姿を現す、私には大きすぎる淡いブルーのワイシャツ。
彼が貸してくれたもの。
大きくて、袖を何回も折った。
丈も長くて何だかワンピースみたい。
何より、ボタンを外そうとして女性ものとは違うことに改めて気付く。
左閉じのシャツ…
そこから微かに漂う彼の匂いに、たまらなく愛しさが込みあげてくる。
鏡に映る湿って少し乱れた髪と紅潮した頬。
泰兄…
そっと彼が触れた唇を指でなぞってみた。
すごく優しくて、情熱的なキスだった。
私にとっては初めての…
唇が離れた後、見つめ合ったまま私は彼に訊いた。
「私のことをまだ子どもだってあなたは前に言ったけれど、今もまだそう思ってる?」
「どうした急に」
低く息のような声で彼はそう言うと、私の冷たくなった頬を両手で包み込んだ。
「いいから答えて」
「…ああ、まだガキだと思ってる」
「そう…」
「でもそれがおまえの魅力でもある。焦る必要はない、ゆっくり世の中を見極めていけばいい」
「でも…」
「もう何も言うな。俺も何も訊かない」
泰兄は私をその胸に押し当てた。
その胸の中でじわじわとキスの実感が沸いてきて、私は次第に身を固くした。
スーツにしみこんだ煙草の匂い。
そして雨に濡れて余計に立ちこめる、泰兄の「男の香り」。
そんな中で私はどうしていいのかわからなかった。
だって、こんなこと初めてだったから。
彼の体温がシャツを通じて、頬に伝わってくる。
あったかい…
そのぬくもりに目を閉じると、私はためらいながらも彼の背中にゆっくりと手を回した。