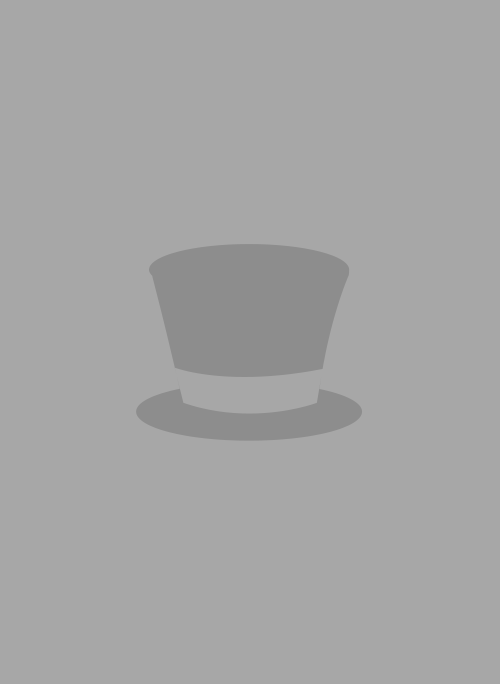真琴は泰輔兄さんがこめかみにケガをした日以来、ことあるごとに彼と同室の俺に「泰兄は?」と気にかけていた。
複雑な気持ちだった。
両親が亡くなってからというもの、真琴は俺以外の男には一切近寄らなかったし、関心すら持たなかった。
なのに、「泰兄はどこにいったの?」と毎日のように無邪気に訊いてきた。
真琴、お兄ちゃんがいるだろ、どうして泰輔兄さんのことをそんなに気にするんだ?
口にはしなかったけど、いつも心の中でそう訊ねていた。
あの時の嫉妬に似た…いやもう完全なる嫉妬だ。
それが今また俺を襲う。
「真琴…」
彼女は泰輔兄さんに肩を抱かれながら、店内に入っていく。
俺は背後を通る車のクラクションでやっと我に返った。
足先が痛いほどに冷たい。
でも胸は煮えたぎるように熱い。
冷たい雨の中、ひとり家路につく虚しさ、敗北感が全身をけだるくしていた。
俺は真琴を…
妹を連れて帰れなかった。
真琴は兄貴を頼らなかったんだ。
泰輔兄さんに助けを求めた。
俺は傘をさすのも億劫になった。
傘を開いたまま、手を下ろし歩いた。
すれ違う人たちが、俺を迷惑そうに見る。
そんなこと、今はどうでもいい。
ただ真琴を連れて帰れなかったことが、ショックだった。
その頬に降る雨をぬぐうことさえできない自分が、むなしかった。