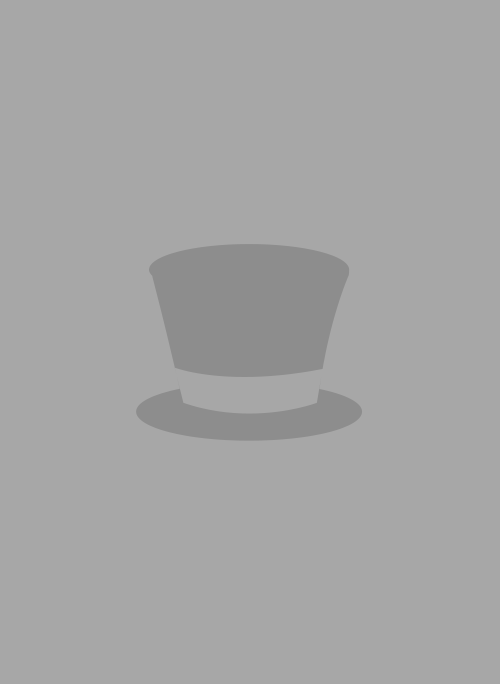俺はそんな思いを抱えて「その場所」に向かった。
詳しい場所を知っていたわけではない。
この本通りはきれいに区画された「夜の街」。
慣れない人間は、いくつもの同じような十字路を目の前にして迷子になってしまう。
俺だってその種の人間だ。
何度来てもよくわからない。
記憶をたどりながら、確かこのあたりだった、そんな感じで一軒一軒店を確認してゆく。
でもなかなか見つからなくて、焦りだけが募る。
多くの店は閉店し、ネオンは消されて辺りは暗い。
真琴…
次の通りにさしかかろうとした時だった。
数えるほどしか点いていない光の中で、ふたつの寄り添う影を見つけた。
雨がまるで霧のようにふたりのシルエットをにじませる。
男と女の情が交錯する、そういう光景はここではよくあることだ。
そう思って視線をそらした。
でも聞こえたんだ。
小さかったけれど、聞き覚えのある声。
でもそれは切なくて、助けを求めているようだった。
「泰兄…」って。
咄嗟にその影に目を凝らした。
真琴…?
そしてもう一つの背の高い影は「彼」に違いなかった。
泰輔兄さん…
ふたりはキスをしていた。
見る者でさえ融かしてしまいそうなほど熱くて、そして永遠に続くのではないかと思うほどの…
パチン、パチンと傘に落ちて弾ける雨粒の音が、妙に大きくて耳障りだった。
やはり、という気持ちと、なぜだ、という気持ちの狭間でこの胸がざわめく。
わかっていたことだけれど、いざ目の前に事実を突きつけられると人は焦り、とまどう。
俺も例にもれず、胸が苦しくなった。
あの時と同じだ。
なつみ園にいた頃と…