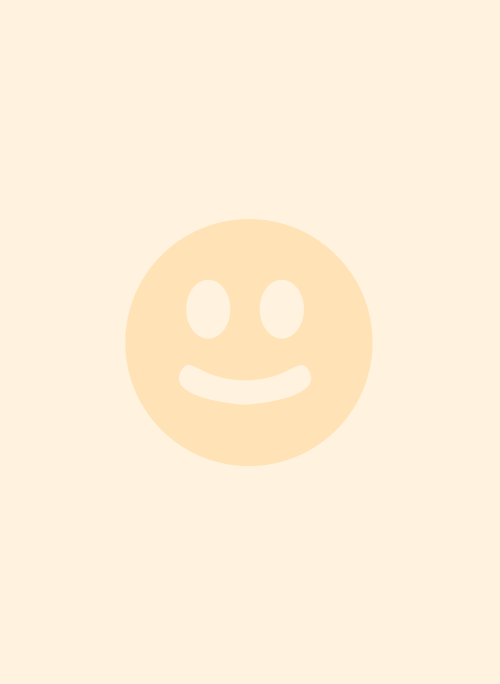のぼるアスミのくすんだ煙を見上げて、ふと彼女との思い出が頭をよぎりそうになった。かろうじてこらえた。きっとアスミは、ぼくに思い出されることを望んでいない。センセーショナルに報道されることを望んでいないのと同じ理屈だ。
だからこそ、アスミは、誰にも告げなかったのだ。だれにも相談しなかったのだ。人知れず、排気口からホースをつなぎ、ドアというドアに念入りに目張りをした。
アスミと、そのほかの世界に内側から線が引かれてしまった。つい先日、常務の娘と結婚したぼくも、そのほかの誰かと同じように、世界の一部にいるままだ。
太陽がかげり、命の匂いと一緒に空に溶けていく。
アスミと、世界の間に線引きしたのは、ぼくだ。
蝉の声がうるさい。
了
だからこそ、アスミは、誰にも告げなかったのだ。だれにも相談しなかったのだ。人知れず、排気口からホースをつなぎ、ドアというドアに念入りに目張りをした。
アスミと、そのほかの世界に内側から線が引かれてしまった。つい先日、常務の娘と結婚したぼくも、そのほかの誰かと同じように、世界の一部にいるままだ。
太陽がかげり、命の匂いと一緒に空に溶けていく。
アスミと、世界の間に線引きしたのは、ぼくだ。
蝉の声がうるさい。
了