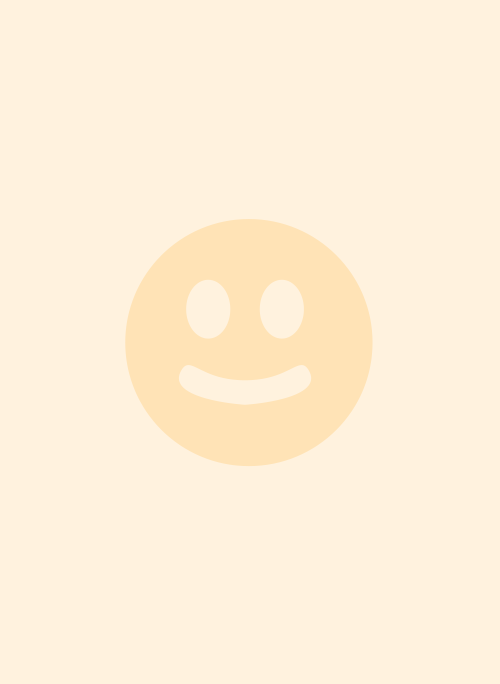後宮へと続く廊下は、まるでお伽噺だった。
ロヴィーサが生まれ育った王宮には、後宮などという色めく建造物は存在しない。王宮そのものだって、おそらくラディナ大国の大臣らの住まいよりみすぼらしいだろう。
国をより大きく、強くするために、政略結婚をしてこなかった結果である。アムーニアの国王は、代々、自然と恋をし、家庭を築き、家族を守るように国を守ってきた。当然、貧しいが、ロヴィーサはこれまで一度も自国を恥じたことはない。
父王や王妃に愛され、民に愛されて育ったことを誇りに思っている。贅の限りを尽くした廊下を見回して、それにしたってすごいわ、と、目を丸くしてただひたすら称賛するくらいに。
王妃の部屋は、後宮の一番奥まったところにあった。部屋の扉がすでに、祖国の錆びれた城門よりはるかに豪奢である。しっとりとしたレザーが張られ、金の装飾に縁どらている。そうしてそこにルビーやエメラルド、サファイヤといった色とりどりの宝石が散りばめられていた。
「皇后陛下。ロヴィーサ様が参られました」
淡々と紡ぐサーシャの声ではっとして、ロヴィーサは慌てて続ける。
「この度、貴国にご縁をいただきました、ロヴィーサでございます。デルフィナ陛下、僭越ながらご挨拶に参りました」
「ロヴィーサ殿ですか。どうぞお入りください」
閉ざされた扉の内から聞こえたのは、この世のものとは思えないほど、柔らかく、優しい声色だった。
大陸一のラディナ大国を治める正妃自ら発した声だと察し、瞬時にロヴィーサはデルフィナに好意を抱いた。
侍女二人がかりで扉が開かれた。デルフィナは、開かれたそこに立っていた。
「ロヴィーサ殿、我がラディナによくぞお越しいただきました。いらっしゃいますのを心よりお待ち申し上げておりました。さあ、中へ」
柔らかい声色にそん色ない温かい笑顔で出迎え、自らの手で自室へ招き入れてくれる。
世界広しといえど、このように振る舞える王妃がいるだろうか。いや、振る舞えるからこそ、大国の正妃なのだろう。
無礼だとわかってはいてもロヴィーサは、継ぐ言葉が浮かばない。なんて素晴らしいお方なのだろうと、デルフィナの歓待に呆然と応じるしかできなかった。
ロヴィーサが生まれ育った王宮には、後宮などという色めく建造物は存在しない。王宮そのものだって、おそらくラディナ大国の大臣らの住まいよりみすぼらしいだろう。
国をより大きく、強くするために、政略結婚をしてこなかった結果である。アムーニアの国王は、代々、自然と恋をし、家庭を築き、家族を守るように国を守ってきた。当然、貧しいが、ロヴィーサはこれまで一度も自国を恥じたことはない。
父王や王妃に愛され、民に愛されて育ったことを誇りに思っている。贅の限りを尽くした廊下を見回して、それにしたってすごいわ、と、目を丸くしてただひたすら称賛するくらいに。
王妃の部屋は、後宮の一番奥まったところにあった。部屋の扉がすでに、祖国の錆びれた城門よりはるかに豪奢である。しっとりとしたレザーが張られ、金の装飾に縁どらている。そうしてそこにルビーやエメラルド、サファイヤといった色とりどりの宝石が散りばめられていた。
「皇后陛下。ロヴィーサ様が参られました」
淡々と紡ぐサーシャの声ではっとして、ロヴィーサは慌てて続ける。
「この度、貴国にご縁をいただきました、ロヴィーサでございます。デルフィナ陛下、僭越ながらご挨拶に参りました」
「ロヴィーサ殿ですか。どうぞお入りください」
閉ざされた扉の内から聞こえたのは、この世のものとは思えないほど、柔らかく、優しい声色だった。
大陸一のラディナ大国を治める正妃自ら発した声だと察し、瞬時にロヴィーサはデルフィナに好意を抱いた。
侍女二人がかりで扉が開かれた。デルフィナは、開かれたそこに立っていた。
「ロヴィーサ殿、我がラディナによくぞお越しいただきました。いらっしゃいますのを心よりお待ち申し上げておりました。さあ、中へ」
柔らかい声色にそん色ない温かい笑顔で出迎え、自らの手で自室へ招き入れてくれる。
世界広しといえど、このように振る舞える王妃がいるだろうか。いや、振る舞えるからこそ、大国の正妃なのだろう。
無礼だとわかってはいてもロヴィーサは、継ぐ言葉が浮かばない。なんて素晴らしいお方なのだろうと、デルフィナの歓待に呆然と応じるしかできなかった。