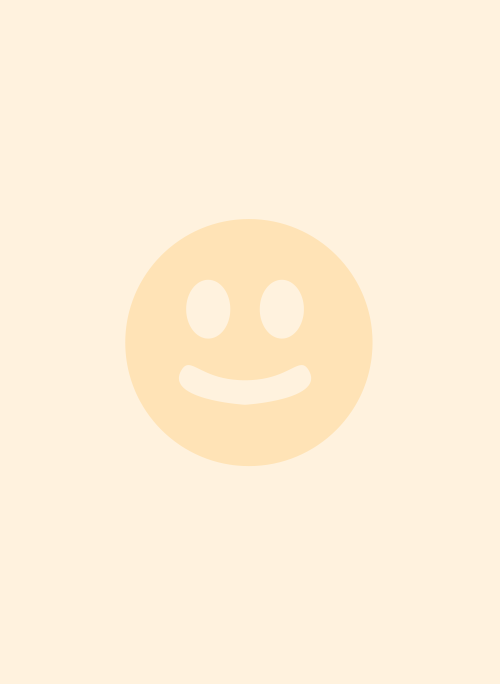アロワには、ロヴィーサが唇を噛んでいるように見えた。
だが、アロワには、それが彼女の中に無数にあるどの感情に由来するものなのかわからなかった。
「サーシャ。サーシャ、入れ」
リュシアンは、ロヴィーサの頬を親指でひと撫でして、手を引く。
「はい。失礼いたします」
うやうやしい仕草で入ってきた若い女を一瞥して、リュシアンは、
「今日からロヴィーサに付き添うサーシャだ。なにかあれば、これに言いつければいい」
「え、あ……え? へ、陛下!」
では、と立ち上がったリュシアンに、ロヴィーサも立ち上がる。
「ロヴィーサ」
呼ぶ声は、ひたすらに甘い。
「よくぞ我が国に来てくれた。心より愛そう。そなたのためならどんなことでもしよう。しかし――」
見つめる視線もとろけるように甘い。
「――しかし、女が政治に口を挟むのは感心しない。では、政務に戻る。晩には、歓迎の宴を開く。それまで、ゆるりと旅の疲れを癒してくれ」
呆然と立ちすくむロヴィーサの心情は、アロワに計りきれないが、ただ、ひとつはっきりとしていることがある。
広く、狭い。
あの後宮も、この王室も、またこの国さえも、ロヴィーサには、広すぎて、狭すぎる。
だが、アロワには、それが彼女の中に無数にあるどの感情に由来するものなのかわからなかった。
「サーシャ。サーシャ、入れ」
リュシアンは、ロヴィーサの頬を親指でひと撫でして、手を引く。
「はい。失礼いたします」
うやうやしい仕草で入ってきた若い女を一瞥して、リュシアンは、
「今日からロヴィーサに付き添うサーシャだ。なにかあれば、これに言いつければいい」
「え、あ……え? へ、陛下!」
では、と立ち上がったリュシアンに、ロヴィーサも立ち上がる。
「ロヴィーサ」
呼ぶ声は、ひたすらに甘い。
「よくぞ我が国に来てくれた。心より愛そう。そなたのためならどんなことでもしよう。しかし――」
見つめる視線もとろけるように甘い。
「――しかし、女が政治に口を挟むのは感心しない。では、政務に戻る。晩には、歓迎の宴を開く。それまで、ゆるりと旅の疲れを癒してくれ」
呆然と立ちすくむロヴィーサの心情は、アロワに計りきれないが、ただ、ひとつはっきりとしていることがある。
広く、狭い。
あの後宮も、この王室も、またこの国さえも、ロヴィーサには、広すぎて、狭すぎる。