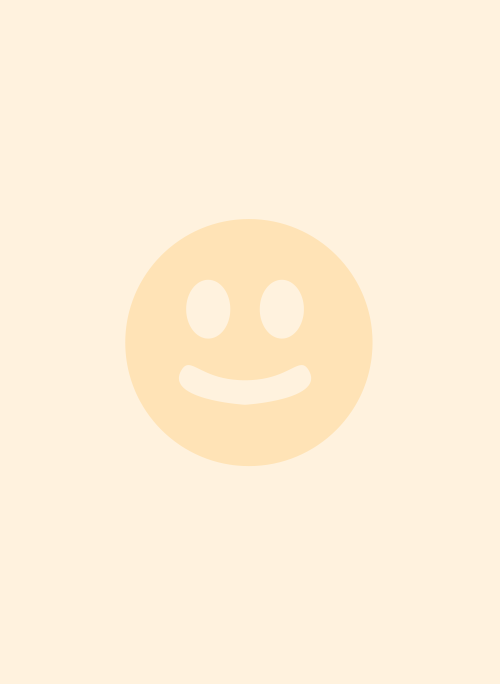「は」
と、沈黙を蹴破ったのはリュシアンだ。続けて、破裂音にも似た笑い声を上げる。
「ハハッ! それでこそロヴィーサだ。その目だ……」
リュシアンは、ロヴィーサの頬に手を伸ばした。
胸をなで下ろすアロワを尻目に、ロヴィーサはあからさまに眉をひそめる。
指先が触れる。
「私は、そなたをひとめ見たときから、ずっと長い間、その目に恋い焦がれていた」
指先は、耳へうわずり、手のひらが、頬をおおう。鍬の、剣の、まめがない手だ。美しい手だ。
そういうことなんだよ、ロヴィ。
アロワは、ため息をかみ殺す。
所詮は、世間知らずの王女様だ。
世間を知らないまま、ここまで年を重ねてしまったこの姫君には……。
と、沈黙を蹴破ったのはリュシアンだ。続けて、破裂音にも似た笑い声を上げる。
「ハハッ! それでこそロヴィーサだ。その目だ……」
リュシアンは、ロヴィーサの頬に手を伸ばした。
胸をなで下ろすアロワを尻目に、ロヴィーサはあからさまに眉をひそめる。
指先が触れる。
「私は、そなたをひとめ見たときから、ずっと長い間、その目に恋い焦がれていた」
指先は、耳へうわずり、手のひらが、頬をおおう。鍬の、剣の、まめがない手だ。美しい手だ。
そういうことなんだよ、ロヴィ。
アロワは、ため息をかみ殺す。
所詮は、世間知らずの王女様だ。
世間を知らないまま、ここまで年を重ねてしまったこの姫君には……。