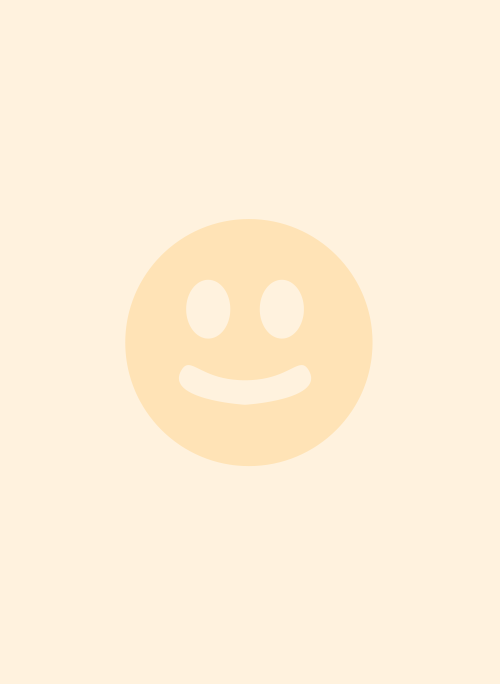「では、あなた様はどうして……」
アロワの喉から出てこられない、ここにいらっしゃったのですか、をロヴィーサは微笑んで察する。
「大変失礼な物言いかもしれませんが」ロヴィーサはひとこと断って、「ダヴィドにも利があるから、その背を差し出すのです」
「ダヴィド……?」
首を傾げるリュシアンに、
「私の愛馬です」
アロワは補足して、慎ましく佇むロヴィーサに目を眇める。
「とても聡く、なにより紳士ですわ」
ロヴィーサは、ふふっ、といたずらっ子のように笑っているが、言っていることはどぎつい。
祖国を、またその王女である自分をを飼い馬に例え、そして、ただの人質に非ず、と言外に匂わせているのだ。
なんつう女……、とアロワが胸のうちで毒づく。自分のような下の者にならまだしも、アリとゾウほどの力の差がある国、またその最高権力者に喧嘩を売っているも同じ。
しかも、これから夫になる王に、だ。正妻の座が約束されているならまだしも、王には第4王妃までいる。側室もごまんといるのだ。
まして、彼女の祖国アムニールは大陸で一、二を争う弱小国――この王の声ひとつでこれからの待遇が変わってくるというに……この目だ。
三十路手前の女がする目か。
ロヴィーサは、不思議な色合いの瞳に、焦がすほどの情熱を閉じこめて、まっすぐリュシアンを見つめる。
戦場でアロワは極まれにこの目と対峙する。そして必ず死闘になる。
この目はまっすぐ自分を見つめる。しかし、この目が見据えているのは、己の決意。
ロヴィーサの目は、まごうことなく、戦う者のそれだった。
アロワの喉から出てこられない、ここにいらっしゃったのですか、をロヴィーサは微笑んで察する。
「大変失礼な物言いかもしれませんが」ロヴィーサはひとこと断って、「ダヴィドにも利があるから、その背を差し出すのです」
「ダヴィド……?」
首を傾げるリュシアンに、
「私の愛馬です」
アロワは補足して、慎ましく佇むロヴィーサに目を眇める。
「とても聡く、なにより紳士ですわ」
ロヴィーサは、ふふっ、といたずらっ子のように笑っているが、言っていることはどぎつい。
祖国を、またその王女である自分をを飼い馬に例え、そして、ただの人質に非ず、と言外に匂わせているのだ。
なんつう女……、とアロワが胸のうちで毒づく。自分のような下の者にならまだしも、アリとゾウほどの力の差がある国、またその最高権力者に喧嘩を売っているも同じ。
しかも、これから夫になる王に、だ。正妻の座が約束されているならまだしも、王には第4王妃までいる。側室もごまんといるのだ。
まして、彼女の祖国アムニールは大陸で一、二を争う弱小国――この王の声ひとつでこれからの待遇が変わってくるというに……この目だ。
三十路手前の女がする目か。
ロヴィーサは、不思議な色合いの瞳に、焦がすほどの情熱を閉じこめて、まっすぐリュシアンを見つめる。
戦場でアロワは極まれにこの目と対峙する。そして必ず死闘になる。
この目はまっすぐ自分を見つめる。しかし、この目が見据えているのは、己の決意。
ロヴィーサの目は、まごうことなく、戦う者のそれだった。