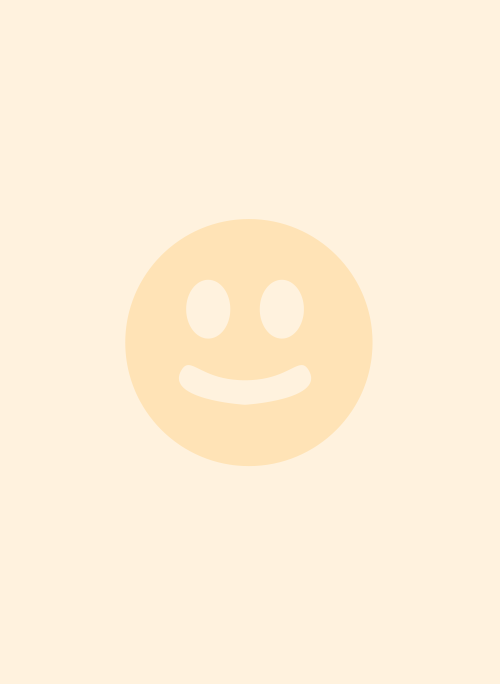国王のプライベートルームに、国王と新しい妃と騎士が各一名。
「大切な話」とやらがあるというに、寝台がすぐそこにある部屋につれてくるなんて。
そんな主の腹の内にアロワが見たのは、下心とか下心とか下心とか、主に下心とか。
主たるリュシアンは、入って早々サーバントにティーセットを頼みつつ、ロヴィーサにテーブル席を勧め、愛しの妃を見つめ放題である。
街の女どもにキャーキャー言われるうらやましい顔面、王という地位がなければただの変質者だ、と密かに思うアロワは完全なるお邪魔虫の位置に追いやられた。
その位置――出入りの扉の横に立ち尽くしているわけだが、とにかく居心地が悪い。
リュシアンは、早く出ていけオーラ全開だし、リュシアンの熱視線にあてられたロヴィーサは、テーブルに置いた手をもじもじさせている。
アロワだって早く出ていきたい。早く休養に入りたい。
暇をもらったその足で酒場へ行き、真っ昼間からバーボンをかっ食らって、その辺にいる女をひっかけ、事の後は、柔い抱き枕にして惰眠をむさぼりたいのだ。
この際遊女だってなんだってかまわない。美しすぎ奔放すぎ無自覚すぎ三ツ星王女にあてられて、自称百戦錬磨もいろいろと限界だ。
一刻の猶予も許されない。
だのに、ただでさえ甘いマスクをトロットロのトロにして、「ロヴィーサ……」と意味なく口にする主が視界に入れば、どっと疲れが襲ってくる。
その疲弊によって、三大欲求のうち一番やっかいかつ不名誉なそれがむくむくと倍増するという最悪なループに突入し、僭越ながら、話の開始を待たない決意をした。
「あの、ロヴィーサ様。お話というのは……」
「え、あっ、はい」
ロヴィーサがピクリとするのに連動してリュシアンまでピクリとするのはホント勘弁してほしいとアロワは、内心ため息をついた。
「大切な話」とやらがあるというに、寝台がすぐそこにある部屋につれてくるなんて。
そんな主の腹の内にアロワが見たのは、下心とか下心とか下心とか、主に下心とか。
主たるリュシアンは、入って早々サーバントにティーセットを頼みつつ、ロヴィーサにテーブル席を勧め、愛しの妃を見つめ放題である。
街の女どもにキャーキャー言われるうらやましい顔面、王という地位がなければただの変質者だ、と密かに思うアロワは完全なるお邪魔虫の位置に追いやられた。
その位置――出入りの扉の横に立ち尽くしているわけだが、とにかく居心地が悪い。
リュシアンは、早く出ていけオーラ全開だし、リュシアンの熱視線にあてられたロヴィーサは、テーブルに置いた手をもじもじさせている。
アロワだって早く出ていきたい。早く休養に入りたい。
暇をもらったその足で酒場へ行き、真っ昼間からバーボンをかっ食らって、その辺にいる女をひっかけ、事の後は、柔い抱き枕にして惰眠をむさぼりたいのだ。
この際遊女だってなんだってかまわない。美しすぎ奔放すぎ無自覚すぎ三ツ星王女にあてられて、自称百戦錬磨もいろいろと限界だ。
一刻の猶予も許されない。
だのに、ただでさえ甘いマスクをトロットロのトロにして、「ロヴィーサ……」と意味なく口にする主が視界に入れば、どっと疲れが襲ってくる。
その疲弊によって、三大欲求のうち一番やっかいかつ不名誉なそれがむくむくと倍増するという最悪なループに突入し、僭越ながら、話の開始を待たない決意をした。
「あの、ロヴィーサ様。お話というのは……」
「え、あっ、はい」
ロヴィーサがピクリとするのに連動してリュシアンまでピクリとするのはホント勘弁してほしいとアロワは、内心ため息をついた。