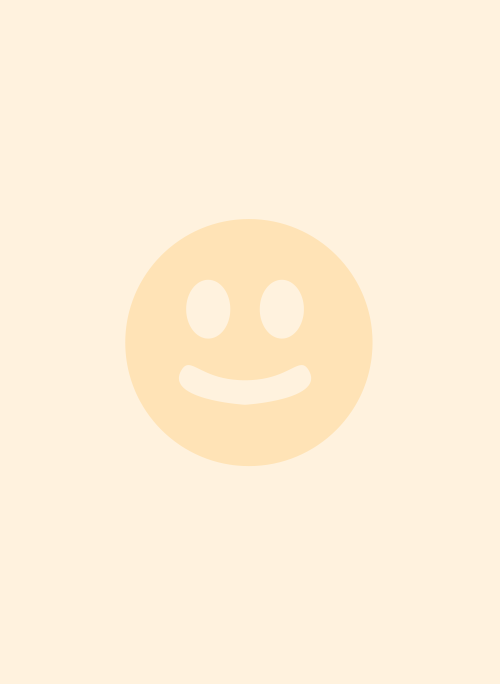たくさんの顔を持つ女だ。
綺麗やら美麗やら華麗やら、そんな形容詞をすべて取り払い、アロワは、ロヴィーサの印象を改める。
アレもその顔のひとつか、と、アロワは苦笑いせざるを得ない。
完膚なきまでに腰が引けて、珍妙な歩き方になっている王女――ああ、そういえば彼女は王女だったっけか。
道中何度思ったかわからない事実にふと脱線し、思考を戻す。
慎ましくあらわれたかと思えば、気品あふれる態度で大国の使者に後れを取らず、泣きそうに目を伏せていたかと思えば、大胆にドレスをめくりあげて馬にまたがり駆け回る。
そして今は、リュシアンに腰を抱かれて、想像を絶するへっぴり腰だ。へっぴり腰界でもなかなかお見かけしないレベルだろう。
男に慣れていないのだろうか。じゃあ、あの宰相――ケヴィンは。
と、アロワは考えるのが、もうなんだか面倒くさい。
ケヴィンはヘタレなんだろうと、アロワは勝手に決めつけ、無心で二人の後を追っていると、そこに伝令官がそろりと現れた。
歩きながら伝令官に耳打ちをうけ、アロワはにやりとする。
早く夜になんねえかなあ。
綺麗やら美麗やら華麗やら、そんな形容詞をすべて取り払い、アロワは、ロヴィーサの印象を改める。
アレもその顔のひとつか、と、アロワは苦笑いせざるを得ない。
完膚なきまでに腰が引けて、珍妙な歩き方になっている王女――ああ、そういえば彼女は王女だったっけか。
道中何度思ったかわからない事実にふと脱線し、思考を戻す。
慎ましくあらわれたかと思えば、気品あふれる態度で大国の使者に後れを取らず、泣きそうに目を伏せていたかと思えば、大胆にドレスをめくりあげて馬にまたがり駆け回る。
そして今は、リュシアンに腰を抱かれて、想像を絶するへっぴり腰だ。へっぴり腰界でもなかなかお見かけしないレベルだろう。
男に慣れていないのだろうか。じゃあ、あの宰相――ケヴィンは。
と、アロワは考えるのが、もうなんだか面倒くさい。
ケヴィンはヘタレなんだろうと、アロワは勝手に決めつけ、無心で二人の後を追っていると、そこに伝令官がそろりと現れた。
歩きながら伝令官に耳打ちをうけ、アロワはにやりとする。
早く夜になんねえかなあ。