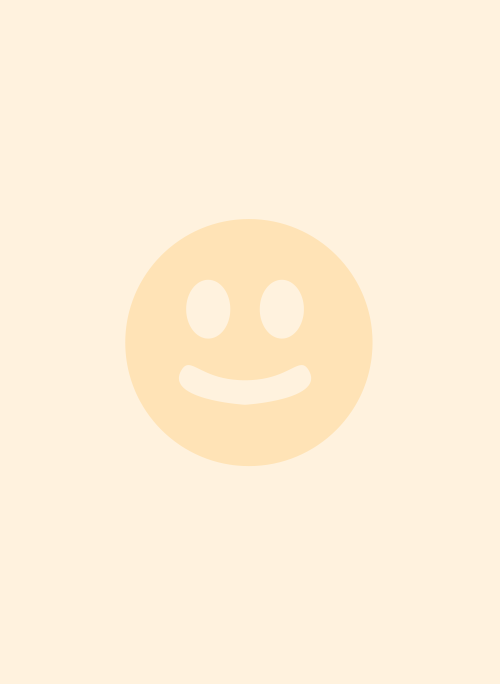「ロヴィーサ!」
前方から、声を上げながら駆け寄ってくるひとかげに、アロワは目を丸めた。
「へ、陛下!?」声も裏がえる。
「え、陛下!?」右に同じく。
ロヴィーサは、ぱちぱちと、天然カールのまつげを叩き合わせる。記憶と違う
、とばかりになんども。
「ロヴィーサ、よくぞ参られた!」
「お久しうございます、陛下。このたびは、アムニール、そして、わたくしロヴィーサに――」
と言い切るより前に、ロヴィーサは長い腕のなかに抱き込まれた。
「陛下!?」いきなりの包容に驚くも、まさか離せとは言えない。これがラディナの挨拶なんだと自分に言い聞かせて、「あ、ええと、このたびは、アムニール、そして、わたくしロヴィ――」
「ロヴィーサ。ああ、まさか本当に……夢のようだ。顔を見せてくれ」
「は、はは……」
あのロヴィがひきつり笑いしてる! と、アロワは吹き出しそうになるが、かろうじてこらえる。
「陛下。わざわざいらっしゃられなくとも、陛下のもとへお連れいたしましたのに」
が、置いてきぼり感が半端じゃなく、思わず口調にとげが生える。
「ああ、アロワ。ご苦労であった。報告はまたのちほど。下がってよいぞ」
とげなんか関係ない! ってくらいの弾んだ声だ。
……だれだ、これ。
アロワの知っている国王でないことは確かだ。
「ロヴィーサ。長旅で疲れただろう。中でゆるりとし――」
「いいえ、陛下」ロヴィーサは顔を上げてきっぱりと断る。「先に大切なお話がございます」
綺麗に整ったその顔が火がついたように赤く染まる。そんなリュシアンを尻目に、ロヴィーサはアロワに向いた。
「アロワも同席なさって」
前方から、声を上げながら駆け寄ってくるひとかげに、アロワは目を丸めた。
「へ、陛下!?」声も裏がえる。
「え、陛下!?」右に同じく。
ロヴィーサは、ぱちぱちと、天然カールのまつげを叩き合わせる。記憶と違う
、とばかりになんども。
「ロヴィーサ、よくぞ参られた!」
「お久しうございます、陛下。このたびは、アムニール、そして、わたくしロヴィーサに――」
と言い切るより前に、ロヴィーサは長い腕のなかに抱き込まれた。
「陛下!?」いきなりの包容に驚くも、まさか離せとは言えない。これがラディナの挨拶なんだと自分に言い聞かせて、「あ、ええと、このたびは、アムニール、そして、わたくしロヴィ――」
「ロヴィーサ。ああ、まさか本当に……夢のようだ。顔を見せてくれ」
「は、はは……」
あのロヴィがひきつり笑いしてる! と、アロワは吹き出しそうになるが、かろうじてこらえる。
「陛下。わざわざいらっしゃられなくとも、陛下のもとへお連れいたしましたのに」
が、置いてきぼり感が半端じゃなく、思わず口調にとげが生える。
「ああ、アロワ。ご苦労であった。報告はまたのちほど。下がってよいぞ」
とげなんか関係ない! ってくらいの弾んだ声だ。
……だれだ、これ。
アロワの知っている国王でないことは確かだ。
「ロヴィーサ。長旅で疲れただろう。中でゆるりとし――」
「いいえ、陛下」ロヴィーサは顔を上げてきっぱりと断る。「先に大切なお話がございます」
綺麗に整ったその顔が火がついたように赤く染まる。そんなリュシアンを尻目に、ロヴィーサはアロワに向いた。
「アロワも同席なさって」