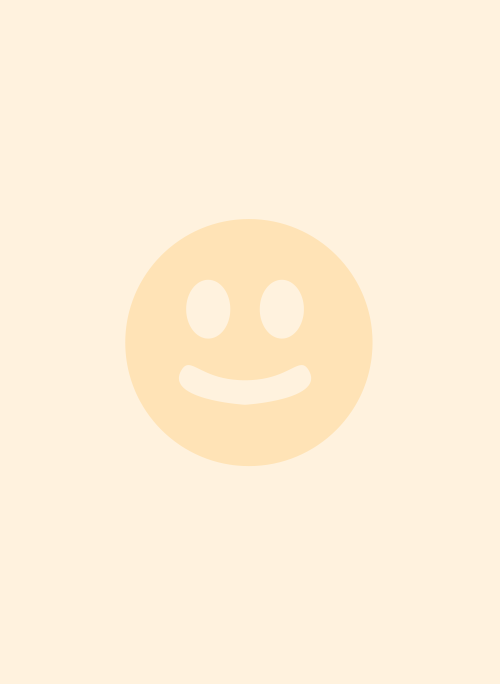アロワは、気づく。
「ふふ。本当に。宰相なんて似合わないことやって、ばかみたいよね」
他の誰がばかにしても、当人たちにとっては、なによりも大切なことだったのだろう、と。
喜びや嬉しさ以外を笑顔にかえてしまえるほどの感情なのだろう、と。
でも、それは――
「……宰相だってなかなか似合ってたけど」
「ふふ、ありがとう」
「……ありがとうって、ロヴィ」
「そうね、私が言うのはおかしいわね」
――置いてくるべき感情なのでは。
「と、いうことは、ケヴィンは俺より3つも年上か」
ロヴィーサは、ふ、と短く微笑む。
「見えないでしょ? 子供のころは逆に大人っぽくて、私がこんなだから、いつも助けてくれて」
「……子供のころから、か」
「ん? なに?」
「いや、こっちのはなし」
「そう」
ダヴィドの毛並みに沿って、ロヴィーサのほっそりした指が、つ、と下る。
つくりものの笑顔が静まったあとの物憂げな横顔が切ないほどに美しい。
そんな顔をさせる感情は置いてこなきゃいけないに決まってるじゃないか。
――置いてくることができるかどうかは、別として。
「ふふ。本当に。宰相なんて似合わないことやって、ばかみたいよね」
他の誰がばかにしても、当人たちにとっては、なによりも大切なことだったのだろう、と。
喜びや嬉しさ以外を笑顔にかえてしまえるほどの感情なのだろう、と。
でも、それは――
「……宰相だってなかなか似合ってたけど」
「ふふ、ありがとう」
「……ありがとうって、ロヴィ」
「そうね、私が言うのはおかしいわね」
――置いてくるべき感情なのでは。
「と、いうことは、ケヴィンは俺より3つも年上か」
ロヴィーサは、ふ、と短く微笑む。
「見えないでしょ? 子供のころは逆に大人っぽくて、私がこんなだから、いつも助けてくれて」
「……子供のころから、か」
「ん? なに?」
「いや、こっちのはなし」
「そう」
ダヴィドの毛並みに沿って、ロヴィーサのほっそりした指が、つ、と下る。
つくりものの笑顔が静まったあとの物憂げな横顔が切ないほどに美しい。
そんな顔をさせる感情は置いてこなきゃいけないに決まってるじゃないか。
――置いてくることができるかどうかは、別として。