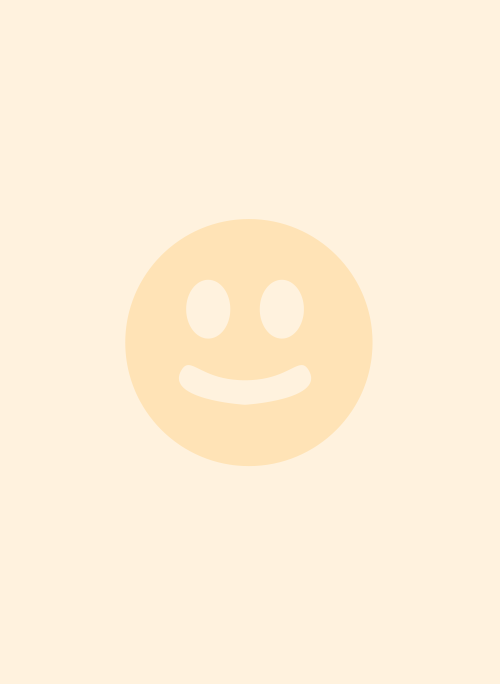なんだかんだで、一番驚いたのは門番だろう。
押しよせる民衆が引いたと思ったら、黒毛の馬が突進してくる。
ぶつかる! と慌てて身を屈めれば、太陽が遮られて陰になり、仰いで腰を抜かした。
黒い腹が頭上を通過し、後方で軽やかに着地した。
「し、しめろ! 閉門!」
我に返って門番が叫んだ頃には、美女がハニーゴールドの髪を翻して、はらり、馬から飛び降りるところだった。
「こら! 女だったら少しくらいエスコートさせろ!」
アロワが馬上から、そこは違うだろ、をわめけば、
「あら、どうして?」
ロヴィーサが、面倒くさいじゃない、とばかりににっこり微笑む。
「……まったく、君は」
呆れてダヴィドから降りるアロワを尻目に、ロヴィーサは美しい毛並みの首を撫でる。
「ふふっ。ダヴィド、よくやったわ。ありがとう」
ロヴィーサの頬に鼻をよせるダヴィドの首をアロワが反対からぺしりとたたく。
「なんだおまえ、さっきの暴れっぷりは演技か! 主人を騙すとは、いーい根性してんじゃねえか」
「騙すなんて心外よね、ダヴィド」
「それにしても」アロワはダヴィドの艶やかな横っ腹をさすりながら、「たいした馬の扱いだな」
「それはケヴィン直伝だもの」
「ケヴィン?」
「アムニールの宰相よ」
「ああ。あのスカしたガキか」
ロヴィーサはふふっと笑う。
「スカしたガキって。でも、彼、ああ見えて馬術だけじゃなくて剣の腕も立つのよ」
押しよせる民衆が引いたと思ったら、黒毛の馬が突進してくる。
ぶつかる! と慌てて身を屈めれば、太陽が遮られて陰になり、仰いで腰を抜かした。
黒い腹が頭上を通過し、後方で軽やかに着地した。
「し、しめろ! 閉門!」
我に返って門番が叫んだ頃には、美女がハニーゴールドの髪を翻して、はらり、馬から飛び降りるところだった。
「こら! 女だったら少しくらいエスコートさせろ!」
アロワが馬上から、そこは違うだろ、をわめけば、
「あら、どうして?」
ロヴィーサが、面倒くさいじゃない、とばかりににっこり微笑む。
「……まったく、君は」
呆れてダヴィドから降りるアロワを尻目に、ロヴィーサは美しい毛並みの首を撫でる。
「ふふっ。ダヴィド、よくやったわ。ありがとう」
ロヴィーサの頬に鼻をよせるダヴィドの首をアロワが反対からぺしりとたたく。
「なんだおまえ、さっきの暴れっぷりは演技か! 主人を騙すとは、いーい根性してんじゃねえか」
「騙すなんて心外よね、ダヴィド」
「それにしても」アロワはダヴィドの艶やかな横っ腹をさすりながら、「たいした馬の扱いだな」
「それはケヴィン直伝だもの」
「ケヴィン?」
「アムニールの宰相よ」
「ああ。あのスカしたガキか」
ロヴィーサはふふっと笑う。
「スカしたガキって。でも、彼、ああ見えて馬術だけじゃなくて剣の腕も立つのよ」