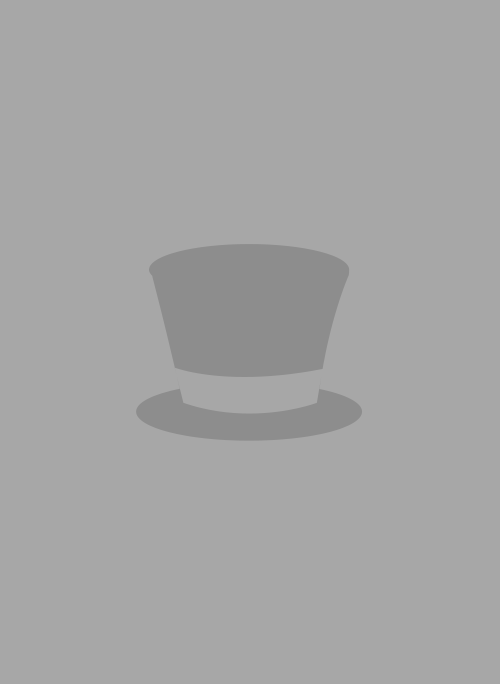胸に重苦しさを感じて、信太郎は唸った。
目を開けるとそこには自分に馬乗りになった3、4歳の小さな女の子が笑っていた。
「なんだ、おまえか。ったく、また勝手に入ってきて」
彼がのっそり起き上がると女の子はするするとベッドから下りた。
「ひとりで来たのか」
信太郎が訊ねると、屈託のない笑顔で答える。
「ううん、お父さんとお母さんも一緒」
「またかよ、あいつら」と大きなため息をつくと、信太郎は時計を見やり、ベッドを出た。
午前8時を少し過ぎていた。
階下では食器のぶつかる音がする。
階段を降りながら、「おまえらは泥棒か」と彼は言った。
その後を少女もついてくる。
「おはよう、信太郎」
「ごめんなさいね、落ち着かなくって」
小さなテーブルにトーストやらコーヒーやらを並べていた一組の男女が、さわやかな笑みを称えて顔をあげた。
「ここは俺ん家だ、勝手に入るなってあれほど言ってんのに」
苦笑しながら信太郎は寝癖のついた頭をかいた。