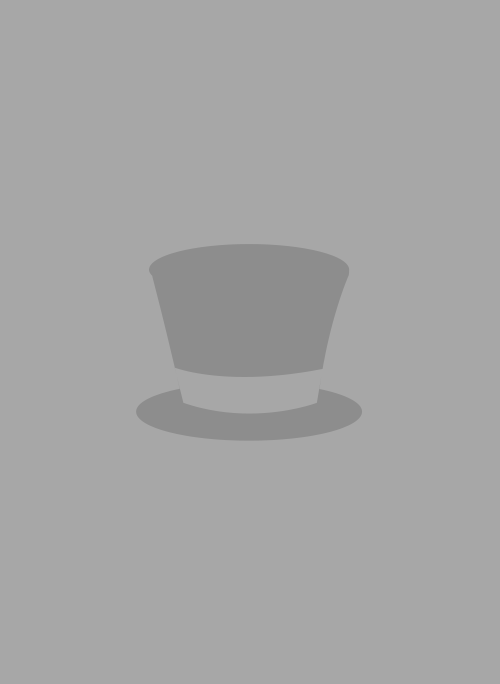その夜のことだった。その日は自分でも驚くほどに心が穏やかだった。
もやもやした霧が、なんの前触れもなく消えてゆくような感覚。
そのせいか、いつも見る見慣れた風景のはずなのに、どこか新鮮な気がした。
窓辺に手をかけた信太郎は、遠くの灯台の光をひとり眺めた。
四方を定期的に照らすその光は、真っ暗な海を渡ってゆく船には欠かせないものだ。
自分にもそんな道標があればいいのに、いつも思ってた。
何も考えずにその光だけを頼りに進んでいれば、迷うこともないのだから。
けれどそんな都合のいい光なんて、実際にはそう簡単に見つけられないのだ。
そう気付かせてくれたのは、ふたりの男。
ひとりは加瀬という元刑事。
そしてもうひとりは、偶然入った小さな教会の神父、山根。
来る日も来る日も、幾度となくも彼らとの会話を反芻し、そして考え悩んだ。
愛し続けるということは、その人を失った大きさを思い知らされることだと、加瀬は言った。
償うとは真っ直ぐに生き抜くことだと、そして今自分が持っているものに満足、感謝せよと山根は言った。
時間を追うごとに、彼らの言葉が惑う信太郎の心に溶けてゆくようだった。
まるで胸の奥に小さな小さな灯火が点るように。
そして今、何かが吹っ切れたように心の真ん中に清々しい風が通り抜けた。