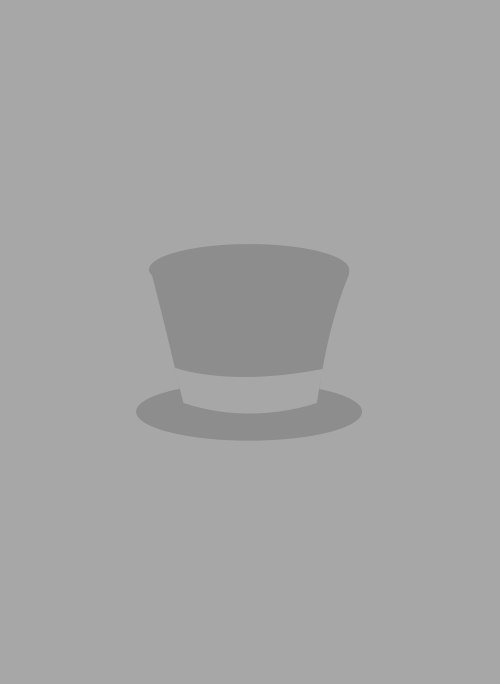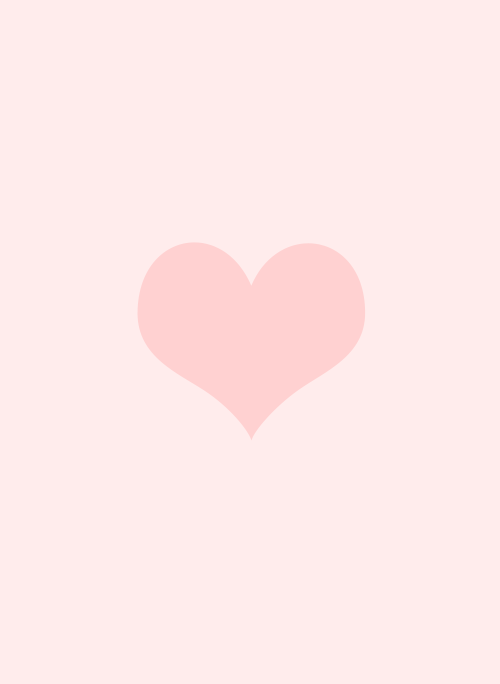せまい玄関で靴を脱いでいると、視界の隅で加瀬が床に置いてあったものを一ヶ所にかき集めていた。
「どうぞ、汚いとこだけど」という彼の言葉を合図に、信太郎は部屋に足を踏み入れた。
ぐるりと見渡してみても、本人が言うほど散らかっている様子はない。
「あの、何か出かける予定があったんじゃ…?」
そろそろと部屋の真ん中まで上がり込むと、信太郎は遠慮がちに訊いた。
「ああ、大した用事じゃないから気にしないで」
加瀬は笑うと「若い子向けの、気のきいたものがなくて申し訳ないんだけど」と小さなキッチンへと入っていく。
その時に彼が何気ない仕草で、チェストのフォトフレームを伏せたのを信太郎は見てしまった。
はっきりとはわからなかったが、映っていたのはおそらく若い男女。しかも女の方は真っ白なウェディングドレスを着ていたように思えた。
部屋にあがるように勧めた加瀬の「俺ひとりだから」と苦笑いした理由が、何となくわかったような気がした。
突っ立っている信太郎に「座って」とキッチンから声がかかった。
インスタントコーヒーを前に、男二人は小さなテーブルを挟んで向かい合っていた。
加瀬は信太郎が刑務所生活を語る間、真剣な顔で耳を傾けてくれた。
だが、出所した今に話が及ぶと急に黙りこくる信太郎に彼は何かを察したのか、無言のまま窓の外に目をやった。
優しい、とても優しい瞳をしていた。
「加瀬さん」
信太郎はコーヒーカップに目を落としたまま、訊いた。
「取り調べの時に、俺が…その…」
いいよどむ彼に代わって加瀬がどこかしら楽しそうに声をあげて笑った。
「『俺にだって君と同じ年くらいの時には、自分の命よりも大切に思う人がいた』って言ったことかな」
信太郎はこくりと頷いて「よく覚えていますね」と返した。
「あはは、本当のことだったからね。ハタチぐらいの時には、好きで好きで仕方ない人がいた」
「その人とはどうなったんです」
「結婚したよ」
なんだ、結局ハッピーエンドかよ、そう心の中で舌打ちした信太郎はすぐにそれを打ち消した。
つい今しがた彼は「独り身だから」と言ったばかりなのだ。
「え、でも今は…」
彼の部屋を思わず見回した。
どう見ても、やはり男ひとりの生活空間。
ふいに向かいの男があはは、と声をたてて笑った。