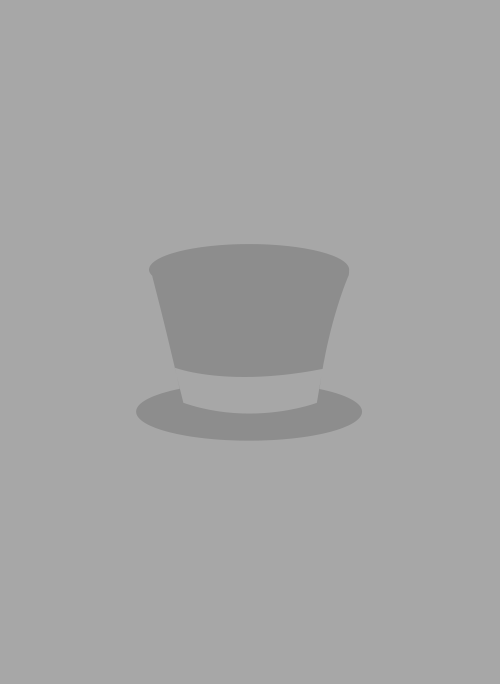彼ら、辻本雅樹、天宮信太郎、佐々倉夏海は、夏休みのこの夏祭りの日に集まった。
世間でよくいう幼なじみだ。
まだ日が落ちきらない、午後7時過ぎのことだった。
カランコロンと軽快なリズムを下駄で奏でながら、夏海が二人の青年の前に現れた。
「似合うね、なっちゃん」と、目を細めて優しく微笑みかける雅樹。
そして「高校生にもなってうかれすぎだろ」と憎まれ口をたたきながらも、照れたようにうつむく信太郎。
そんな二人の前で、彼女はおどけてモデルのようにクルッと身を翻した。
「どう?」
「うん、きれいだよ」
相変わらず優しい言葉を雅樹はかけてくれる。
「ありがとう、マーくん」
満面の笑みで夏海はそれに応えたが、「ほら、行くぞ」という信太郎の言葉に彼女はムッとして訊いた。
「信ちゃんは?何か言うことない?」
「ノーコメント」
そう言って、背を向けたまま彼は手をヒラヒラと耳元で躍らせた。
「かっわいくない」
信太郎の後ろ姿に頬を膨らませた夏海の肩を、雅樹が「行こう」とばかりにそっと押し、言った。
「照れてるんだよ、きっと」
「そっかなぁ」
雅樹に促されて踏み出した一歩は妙に陽気な音で、カランと響いた。
夏海を真ん中に、両脇を信太郎と雅樹が挟むようにして歩いてゆく。
「大学生になったら思いっきり三人で遊びたいな、旅行とかさ、いろんなことできるよね」と、雅樹が言った。
「げっ、やな奴。そう思うだろ、ナツ?」
「うん、ほんとよ、嫌味ー自分だけ頭いいからって。私たち大学生になれるかわかんないし」
そう言って夏海は信太郎にぺたりと寄り添った。
「こらこら、俺と距離を置かないでよ。深読みしすぎだって」
彼らと自分との距離を指差しながら雅樹は笑った。
「見て、信ちゃん。マーくんったら焦ってるよ」
「なっちゃんも意地が悪くなったなぁ、信太郎病だよ」
「おい、それはどういう意味だよ」と信太郎。
「信太郎病かぁ、それもやだなぁ」と言いつつ、雅樹と距離をとる夏海。
「だから、なっちゃん!俺との距離を広げるなって!」
あはは、そう声を立てると彼女は持っていたうちわで煽ぎながら、信太郎、雅樹のちょうど真ん中に位置を戻した。
そんな三人は、現在高校2年生。