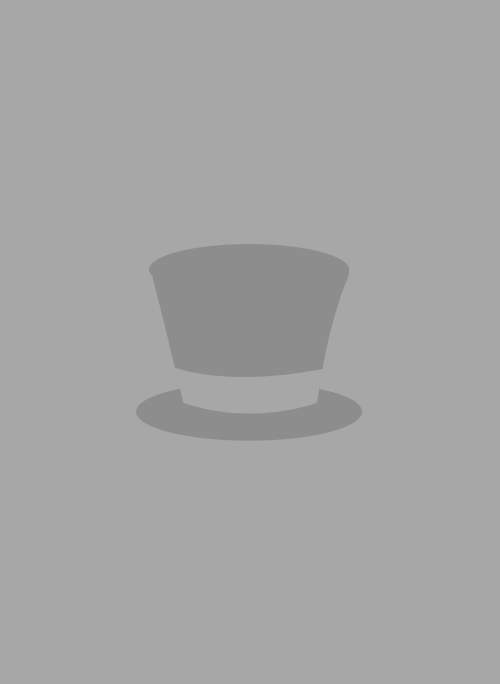「お父さん、ごめんね。こんな病気になっちゃって。迷惑ばっかりかけてるよね、私」
「馬鹿。つまらないことを言うんじゃない。迷惑なんて、これっぽっちも思ってない」
いささか怒ったような克彦の口調に、夏海は息のような声で笑うと、「お父さん、ありがとう」と窓の外に視線をやった。
また風がレースのカーテンを優しくひるがえす。
目を細めた娘の横顔が、柔らかな微笑みを浮かべた。
その姿が光に透けてしまいそうで克彦は細くて白い手を握りしめた。
「夏海」
「ねぇ、お父さん。こんな私でも生まれてきた意味があるとするなら」
夏海が克彦に潤んだ瞳を向けた。
「信ちゃんの生き甲斐になることだったのにな…」
娘の手を握る克彦の目が見開いた。
「なれなかったのかなぁ、私。信ちゃん、何の連絡もくれないし」
ふふっと力なく夏海を克彦は無言で強く抱きしめた。
強く、強く。
かけてやる言葉なんて見つからない。
何を言っても何の気休めにもならないことはわかっている。
現に信太郎は夏海を拒絶しているのだから。
こんなに彼を想っているのに。
こんなに彼を心配しているのに。
「信ちゃんのどんなに悲しいことも辛いことも、全部私に話してほしかったな。聞くことしかできなくっても、話せば少しは心が落ち着くってこともあるだろうし…」
壊れてしまいそうなそんな小さな娘の体を、克彦はただただ抱きしめた。