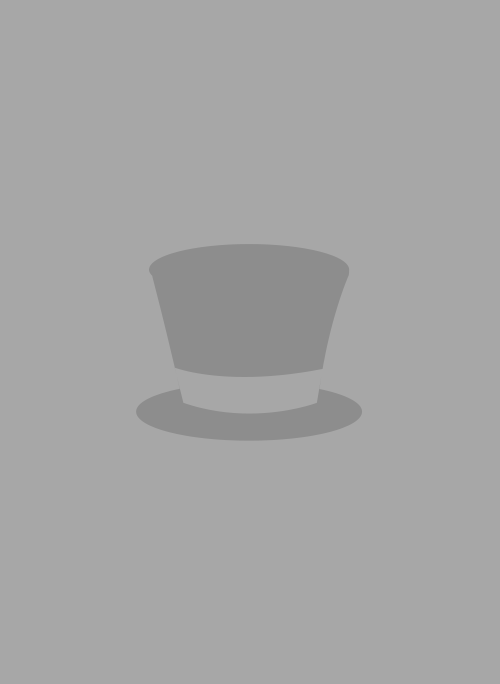「なんで笑うんだよ?」
「だってネタがきれるのが早すぎなんだもん」と彼女は顔を上げた。
うっすら涙がにじんでいたが、「たかだかおまえの呼び方に、そんなにたくさんレパートリーがあるわけないだろ」と言われ、思わずまた笑ってしまった。
目の前に立っている信太郎のアゴには分厚いガーゼが貼り付けられ、顔のいたるところには擦り傷だらけだった。
「武ばぁが心配してんぞ」
「……」
「雅樹もおまえを探しに浜まで下りてったんだぞ、人騒がせなやつだな、このバカナツ」
「ごめんね、信ちゃん…」
「まったくよぉ。雅樹にも後で礼くらい言っとけよ」
「そうじゃなくて!」
「あ?」
「…そうじゃなくて、放課後のケンカ…」
「……」
「私のせい、だよね」
「バカタレ、んなわけないだろ。あいつら、前から気に入らなかったんだよ。たまたま目が合ってつい手が出ただけだって」
嘘がヘタ…夏海は思った。
「でも…」
「あーもう帰ろう、腹減ったし」
まだ何か言いたげな夏海の言葉を遮ると、信太郎は彼女の手を取った。
その手がとても温かかったのを彼女は何年も経った今でも覚えている。
その温かさに、心に渦巻いたやり場のない思いがすっと融けていくように思えて、夏海は素直に来た道を戻った。
社宅に着くまで、信太郎はずっと手をつないでいてくれた。
何も言わず、ただ手をひいてくれた。
その後で、彼は宝物の天体望遠鏡で月を見せてくれた。
「俺、月が一番好きなんだ。毎日違って見えるから」
そんな彼からは微かに消毒薬の匂いがした。
この日以来、夏海に元気がないと信太郎は月や星を見せてくれた。
望遠鏡のレンズをのぞきながらピントを合わせると、いつもこう言って代わってくれたのだ。
「ほら、ナツ。見てみろ」と。