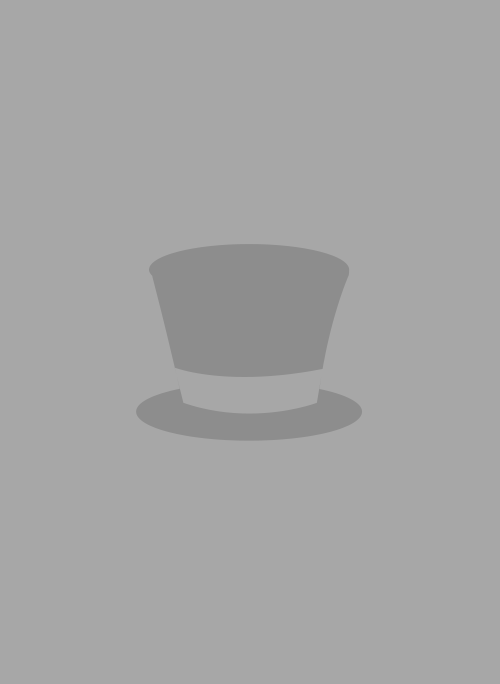胸が痛み、シャッっと彼女は勢いよくカーテンを引いた。
「なっちゃん?」
「信ちゃん、大変だったね」と言いながら、祖母の武子が心配そうにリビングに入ってきた。
ハリのないその年老いた声に、キッと振り返った夏海は叫んだ。
「おばあちゃんのせいだよ!信ちゃんがあんなにおっきなケガしたのは、おばあちゃんのせいなんだからね!もう絶対に参観日とか、学校に来ないで!!」
祖母を押しのけると、夏海は靴を履き家を飛び出した。
「なっちゃん!待ちなさい!」
背後から呼び止められたが、振り返らなかった。
母がいないことをバカにされて、悲しい、悔しい。
それをかばってケガをした信太郎に申し訳ない。
そして、祖母は決して悪くないとわかってて、あんなひどいことを言ってしまった自分に腹立たしさも感じる。
様々な感情が入り乱れて、夏海の目に涙が溢れた。
濡れた瞳にかまうことなく、彼女は近くの海が見下ろせる公園まで走った。
もう日は暮れて、海面は紫とも言えず、かといって黒とも言えない不気味な色が渦巻いていた。
『ナツミっていうのはね、なっちゃんが生まれた日、とっても海がきれいだったんだって。キラキラしてて今まで見たことがないくらいだったって、お母さんが言ってたの。だから海、という字を付けたいってお父さんにお願いしたんだって。こんな海みたいに輝いてほしいって。それで夏に生まれたから、夏の海と書いてナツミ…』
おばあちゃんにおんぶされて、よくここから海を見てそう聞いたな…膝を抱えて、夏海はベンチで小さくなった。
「私、無理。キラキラなんかできない。こんな海みたいに暗くて、どーんよりして…」
そう呟いた時だった。
「よくわかってんじゃん」と聞き覚えのある声が頭上から降ってきた。
「ほら、ウジウジ女、帰るぞ」
誰だかわかっていたので、彼女は顔を上げない。
「おい、そこのバカタレ。聞こえてるんだろ?」
「……」
「バカナツ」
「……」
「ナーツ?」
「……」
「佐々倉さーん」
「……」
「夏海さん?」
「……」
「えっと…」
その声が詰まったところで、夏海はとうとう噴き出した。
「なっちゃん」って絶対に「彼」はそう呼ばない。
どんなことがあっても。