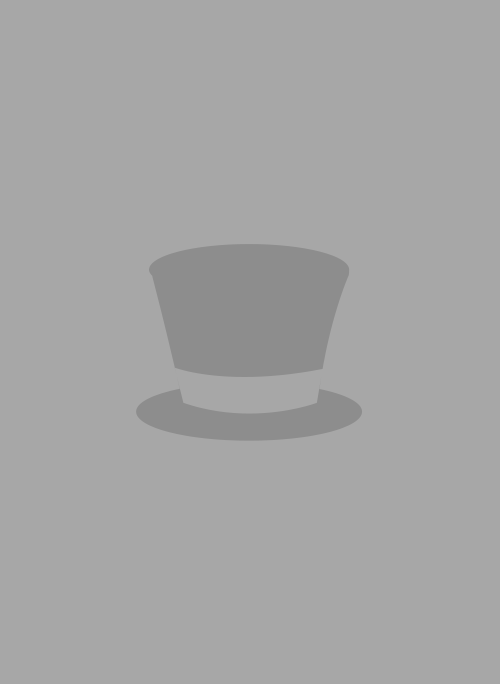「どうした?」
騒ぎを聞きつけた克彦と市原が、血相を変えて部屋に飛び込んできた。
「すみません、俺が点滴チューブを引っかけちゃって抜いちゃいました。本当にすみません」
弱り果てた顔をしてみせる雅樹に「違うよ!私が…」と夏海が横から口を出した。
「ほんとにごめんよ、なっちゃん」
それ以上言わせまいとする雅樹の言葉に、夏海は黙りこくる。
市原が慣れた手つきで新しい点滴針を夏海の静脈に差し込み、終わったら声をかけて、と部屋を出て行った。
克彦は先ほどの話で娘の姿をまともに見ていられないのか、廊下にいます、とだけ言って随分前に部屋を出ていったきりだった。
再び薬剤が一定のテンポで落ちてゆく。
それを何気なく見ていると、彼女が静かに切り出した。
「ねぇ、マーくん。さっきの話の続き…」
雅樹は「詳しくはよくわかんないんだけど」と前置きをした上であることを話した。
もしかすると、正当防衛が認められるかもしれないということ。
そして情状酌量を求める証人として、夏海や雅樹が裁判に出廷すること。
最後に、減刑を求める嘆願書を提出することを告げた。
その直後、夏海の希望を失った目に、一筋の光が射し込むのがわかった。
「私、何だってする。信ちゃんのためなら何だってする」
そんな彼女の決意を数日の間にくじいてしまうことになろうとは、あの時には考えもしなかった。
額に汗をにじませながら言いあぐねている雅樹の様子に、「信ちゃんのこと、でしょ?」とすかさず夏海が問うてくる。
彼は目を閉じると、2,3度小さく頷いた。
「信太郎のご両親に聞いたんだけど、あいつ…」
そこまで言って、また言い澱む。
「何?」
先を急かすように夏海は雅樹の横顔をのぞきこんだ。