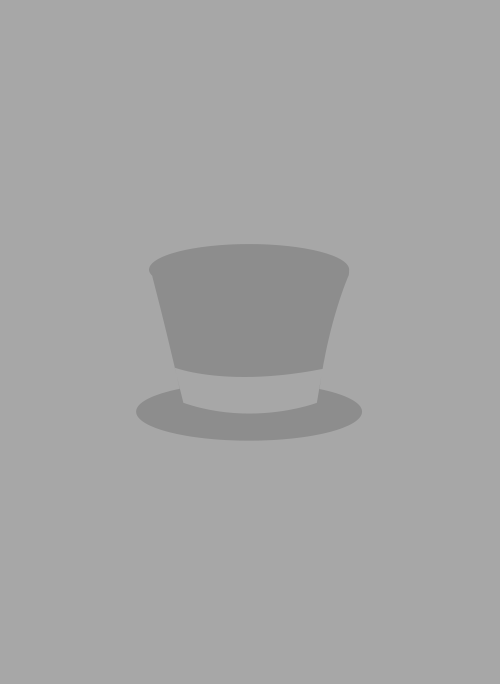「ねぇ、マーくん」
「ん?」
「ここにいるってことは、私、相当悪いんだよね」
「ははっ、何言ってるんだよ、なっちゃんは。ただの検査入院だろ?」
口元とは裏腹に、彼の目は決して笑ってはいなかった。
彼も何かしら知っているに違いない。
「でも検査だけなら、あの総合病院でも…」
「今はね、みんなが最新の医療を受けたがるんだ。武ばぁのこともあるから、克彦おじさんも慎重になってるんだよ」
夏海の言葉を遮るように、雅樹は一気に話し終えた。
優しさとは時に残酷なものだと、彼女は思う。
自分自身も傷付き、そしてさらに優しい嘘をつく彼をも傷付けかねない。
「ごまかさないで!」そう言ってしまえば、彼の優しさが無になってしまうのだから。
もうこの話はよそう、夏海は腰までかけてあったタオルケットをとると、こう言った。
「ねぇ、散歩に付き合ってくれる時間はある?」
額には汗がにじんでいた。
自分から言い出したことだから仕方ない。
ほんの2、3日まともに歩かなかっただけなのに、一歩踏み出す度に足がもつれてしまうのだ。
人間の身体なんて脆いものだと改めて気付く。
「車椅子、借りてこようか?」
よろける夏海をひやひやしながら見ていた雅樹が訊いてきた。
「いらない」
壁づたいに取り付けられた手すりを握りしめ、彼女は意地で何とか屋上までたどり着く。
太陽が容赦なく照りつけるそこは、厳しい暑さだ。
しかし冷房の効いた部屋にずっといた夏海には、かえってそれが心地いい。
夏の暑さを全身で感じられる。
「なっちゃん、こっち」
目を向けると、給水タンクの影に計算されたかのようにベンチが設置されてある。
二人は並んで腰を下ろした。
「やれやれ、だね」
雅樹がそう言って、突然おかしそうに笑い出した。
それにつられて「ほんと…やれやれって感じだね」と夏海も笑う。
そんな様子に、目を細めた彼はほっとしたように言った。
「やっと笑った」
「……」
小さな影だが、厳しい暑さは何とかしのげる。
夏の終わりにしては、蝉もまだまだ元気だ。
熱を帯びた風も、時折耳元でビュウッとその存在を知らせてくれる。
「実はさ…」
雅樹は膝に置いた手を握りしめると、視線を左右にせわしなく何度も動かした。