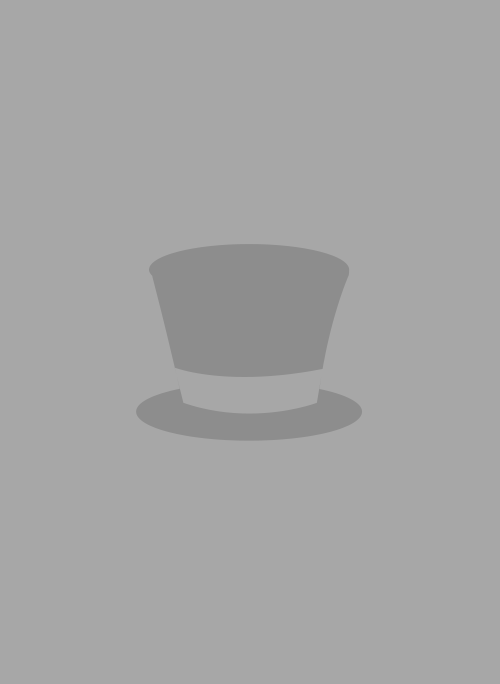「どうしてなっちゃんにはママがいないの?」
幼い夏海は幾度となくこんな質問を繰り返し、お誕生日やクリスマスのプレゼントには必ず「ママが欲しい」と答えるほどに、父や祖母を困らせた。
夏海の母親は彼女を生んだあと、すぐに亡くなった。
そのため、母の顔も声も、ぬくもりも彼女は知らない。
気がつけば、いつもそばには顔にシワのある祖母がいた。
参観日や運動会、いつも「母親」として祖母が出席してくれた。
周りの友達の母親には、こんなシワなんてない。
子ども心に恥ずかしさという感情が湧きあがってくるのを感じ、とても嫌だった。
小学5年の時のこと。
下校時に上級生の男子数人に夏海は呼び止められた。
「今日の参観日に、ひとりだけシワシワの人が来てたけど、誰の母ちゃんだよ」
「……」
こんな全校生徒が数十人といった小学校では、祖母が目立ってしまうのも無理はなかった。
「なぁ、佐々倉。誰の母ちゃんか知らないか?」
いたぶるような言葉と視線。
「……」
うつむいたまま握りしめた拳は、夏海の紺色のスカートをしわくちゃにした。
それが祖母を連想させる。
途端に、悔しさと祖母への嫌悪感が溢れ出てきた。
母親がいないのは自分のせいなのだろうか、だからこんなにもバカにされなくてはならないのか。
祖母は優しい、感謝している。
だけど、人前には出て欲しくない…
そんな複雑な気持ちが入り乱れて、浴びせられた言葉からすぐに祖母をかばうことなんてできなかった。
「おまえの『母ちゃん』じゃないのかよ」
「…違うもん。おばあちゃん、だもん…」
この時期の子ども特有のえげつなさが、夏海を激しく傷付ける。