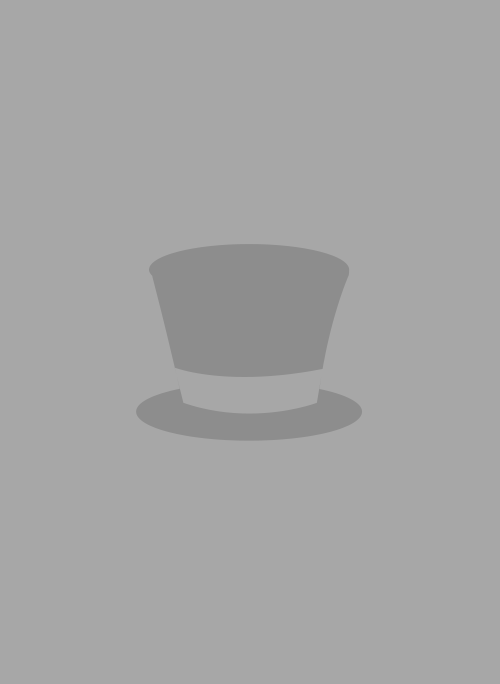「わかってるんだ。おまえ、俺となっちゃんをくっつけようとして、わざとひとり違う高校に行ったろ。自分だって彼女が好きなくせに。それで身をひいたつもりだったのか?あきらめるために他に恋人作ってさ。自分の気持ちに嘘ついてるやつにとやかく言われたくないんだ。俺がなっちゃんにキスしたことが気に入らないなら、正直にそう言えよ」
ふてくされたように信太郎は雅樹を見る。
「そんなやつになっちゃんを渡したくない」
「……」
「俺はなっちゃんが好きだ、だからキスをした」
波が静かに返した後の無数に泡立つ音が、今夜に限っては妙に大きく聞こえる。
「ふーん、よかったじゃん。映画のロケかと思うくらいの情熱的なキスシーンだったよ。ナツも今頃メロメロだって」
信太郎はかすれた口笛をヒューッと一度だけ吹いた。
ため息を一つつくと、雅樹は呆れたように力なく笑った。
「相変わらずだな、おまえは。素直になれるチャンスをやったのにな。今、素直になっとかなきゃ、後で後悔するぞ」
「はいはい、心に留め置きます」と信太郎は姿勢を正して敬礼をする。
「…ったく」
雅樹はその緩めた拳のまま、信太郎の胸を軽く押した。
「それよりさ、おまえあのビーチサンダルにいくら使ったんだよ」
「あ?200円だよ」
「嘘つけって」
「マジ」
「有り金全部とか?」
「なんで俺があいつのために、そこまでしなきゃなんないんだよ」
「またまた」
「うるさいんだよ、おまえは」
「あーあ、まずいな…あれはなっちゃんのポイント、高いだろうな」
「バカ言え」
「いいや、おまえはここぞって時にいっつもカッコいいことするからなぁ」
「何言ってんだよ」
信太郎はふん、と鼻で笑うと真顔で言った。
「雅樹の優しさには、誰もかなわないよ」と。
彼は幼なじみに真似て、足元の砂を蹴る。
月明かりに照らされて、舞い上がった砂は銀色に輝いた。
高校2年生の、夏の出来事だった。